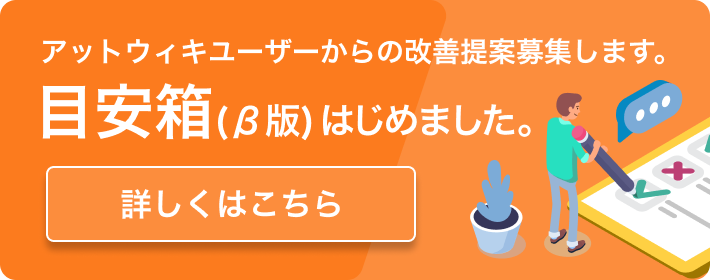< 【back】
アンティーク家具で内装された、小洒落た喫茶店。
珈琲を売りにしているだけあって、店のカウンターには豆が並び、店内には珈琲の香りが充満する。
「ここ、最近出来たんだ」
テーブルの、目の前の女性―にしては少女のような雰囲気の漂う女―は、珈琲を飲みながら微笑む。
「美味しくない?」
「ん?」
「コーヒー。さっきから飲んでないけど」
「ああ…」
彼女に言われ、エスプレッソを口に含む。
口に広がる優しい苦味と、鼻を抜ける香り。
少なくとも不味くはない。
では美味しいのか?
そう、美味しいのだろう。
「美味しい?」
「美味しいよ」
「うそ。美味しいって顔してない」
「そんなことはないよ」
「ふうん…」
彼女から視線をそらす。
正確には、味など分からなかった。
珈琲を売りにしているだけあって、店のカウンターには豆が並び、店内には珈琲の香りが充満する。
「ここ、最近出来たんだ」
テーブルの、目の前の女性―にしては少女のような雰囲気の漂う女―は、珈琲を飲みながら微笑む。
「美味しくない?」
「ん?」
「コーヒー。さっきから飲んでないけど」
「ああ…」
彼女に言われ、エスプレッソを口に含む。
口に広がる優しい苦味と、鼻を抜ける香り。
少なくとも不味くはない。
では美味しいのか?
そう、美味しいのだろう。
「美味しい?」
「美味しいよ」
「うそ。美味しいって顔してない」
「そんなことはないよ」
「ふうん…」
彼女から視線をそらす。
正確には、味など分からなかった。
「それにしても久しぶりだね」
「ああ」
女性は胸の前で軽く手を合わせると、すぐさま話題を変えた。
「ずっと、会えなかったから。また会えて嬉しいよ」
「ああ、俺もだよ」
「本当に?」
「本当だよ」
「そっかあ…」
彼女は懐かしむように、俺を見て目を細める。
「しばらく見ないうちに大人っぽくなったね」
「そうかな」
「うん。見違えちゃった」
「まあ…老けはしたかな」
「フフ、違うよ」
「そういうお前も…」
言おうとして、口をつぐんだ。
顔こそあまり変わらないが、全体的に痩せた気がする。
そして昔に比べ、髪の毛が短くなった。
「なに? あたしがどうしたの?」
「…いや、お前も大人っぽくなったなって」
「そう? それって褒めてるの?」
「ああ」
綺麗になった、と言うと、照れたように笑みを浮かべた。
「ああ」
女性は胸の前で軽く手を合わせると、すぐさま話題を変えた。
「ずっと、会えなかったから。また会えて嬉しいよ」
「ああ、俺もだよ」
「本当に?」
「本当だよ」
「そっかあ…」
彼女は懐かしむように、俺を見て目を細める。
「しばらく見ないうちに大人っぽくなったね」
「そうかな」
「うん。見違えちゃった」
「まあ…老けはしたかな」
「フフ、違うよ」
「そういうお前も…」
言おうとして、口をつぐんだ。
顔こそあまり変わらないが、全体的に痩せた気がする。
そして昔に比べ、髪の毛が短くなった。
「なに? あたしがどうしたの?」
「…いや、お前も大人っぽくなったなって」
「そう? それって褒めてるの?」
「ああ」
綺麗になった、と言うと、照れたように笑みを浮かべた。
それから他愛のない話を少しばかりし、時間を過ごした。
しかし、じきに店内に夕陽が差し始め、時計は5時を回っていた。
「…でね、近場に…」
「みずき、悪い」
「え?」
「時間だ」
「え?もう?」
「ああ。夕飯には帰るようにしてるんだ」
「そっか。稔、奥さんと、子供もいるもんね」
「…ああ」
同時に立ち上がると、特に名残惜しむこともなく。
会計を済ませ、また会おうと交わし笑って別れた。
しかし、じきに店内に夕陽が差し始め、時計は5時を回っていた。
「…でね、近場に…」
「みずき、悪い」
「え?」
「時間だ」
「え?もう?」
「ああ。夕飯には帰るようにしてるんだ」
「そっか。稔、奥さんと、子供もいるもんね」
「…ああ」
同時に立ち上がると、特に名残惜しむこともなく。
会計を済ませ、また会おうと交わし笑って別れた。
帰宅。
玄関まで行くと夕飯の臭いが漂う。今日は煮物だろう。
鍵を開け家に入ると、ぱたぱたと音が近づいてきた。
「お帰りなさい」
「ただいま」
「あ、もう。靴は揃えてねって言ってるじゃない」
「…ごめんなさい」
笑顔で出迎えてくれたが、靴を乱暴に脱ぎ捨て上がると、彼女は眉をひそめた。
しかし、怒りながらも、靴を直してくれるところがこの人らしい。
玄関まで行くと夕飯の臭いが漂う。今日は煮物だろう。
鍵を開け家に入ると、ぱたぱたと音が近づいてきた。
「お帰りなさい」
「ただいま」
「あ、もう。靴は揃えてねって言ってるじゃない」
「…ごめんなさい」
笑顔で出迎えてくれたが、靴を乱暴に脱ぎ捨て上がると、彼女は眉をひそめた。
しかし、怒りながらも、靴を直してくれるところがこの人らしい。
それからスーツをハンガーにかけ、シャワーを浴び、汗を流した。
風呂から上がると、食卓には夕食が並べられ、思った通り煮物が食卓に上がっていた。
「いただきます」
「いただきます」
言葉と同時に、いつものように発泡酒の缶を開ける。
が、開けたはいいが、いざ口まで運んだところで、それ以上進まない。
口を開いてはやめ、口を開いてはやめ。
結局食卓に置いた。
「…どうしたの?」
「ん?」
「それ、飲まないの?」
「んー…」
「会社で何かあったの?」
「いや…まあ…」
言葉を探しながら答えあぐねていると、彼女は発泡酒を取り上げた。
「答えないならあたしが飲む」
「あ、ちょっと」
「良いの?飲んでも」
「良くないよ。お腹の子に障るだろう」
「だから良いのって言ってるの」
「…」
敵わないな。この人には。
風呂から上がると、食卓には夕食が並べられ、思った通り煮物が食卓に上がっていた。
「いただきます」
「いただきます」
言葉と同時に、いつものように発泡酒の缶を開ける。
が、開けたはいいが、いざ口まで運んだところで、それ以上進まない。
口を開いてはやめ、口を開いてはやめ。
結局食卓に置いた。
「…どうしたの?」
「ん?」
「それ、飲まないの?」
「んー…」
「会社で何かあったの?」
「いや…まあ…」
言葉を探しながら答えあぐねていると、彼女は発泡酒を取り上げた。
「答えないならあたしが飲む」
「あ、ちょっと」
「良いの?飲んでも」
「良くないよ。お腹の子に障るだろう」
「だから良いのって言ってるの」
「…」
敵わないな。この人には。
意を決して、話すことにした。
「…今日の昼頃か…会社で仕事してた時にね、携帯に電話があったんだよ」
「うん」
「知らない番号だったけどさ、仕事相手かもなって思って取ったんだよ」
「うん」
「そしたら…」
「そしたら?」
「…みずきからだったんだ」
「え…? みずきって…如月みずきさん?」
「うん」
「…」
名前を告げると、彼女は口を開けたまま目を見開いた。
まさか予想もしてなかったのだろう。
もちろん、俺が電話を取った時も同じ反応をしたに違いない。あまりのことに覚えていないが。
「…今日の昼頃か…会社で仕事してた時にね、携帯に電話があったんだよ」
「うん」
「知らない番号だったけどさ、仕事相手かもなって思って取ったんだよ」
「うん」
「そしたら…」
「そしたら?」
「…みずきからだったんだ」
「え…? みずきって…如月みずきさん?」
「うん」
「…」
名前を告げると、彼女は口を開けたまま目を見開いた。
まさか予想もしてなかったのだろう。
もちろん、俺が電話を取った時も同じ反応をしたに違いない。あまりのことに覚えていないが。
「…そうなんだ、もう…」
「ああ。俺も忘れかけてたから。驚いたよ」
「そ、それで?」
「今すぐ会いたいって言われて。会社を早めに切り上げて、今日会ったんだよ」
「そんな、言われたから会ったって…!」
「会わないわけにはいかないよ。今後の事を考えたら」
「でも!稔くんに何かあったら…」
「…あるわけないじゃないか」
「人を殺したのよ!?無いわけないじゃない!」
「早紀さん…」
いつもは落ち着いているこの人が、明らかに狼狽している。
手に持った発泡酒の缶を、今にも落としそうだった。
「とにかく会った。それで昔の話をした。それだけで何も無かったよ」
「…様子はどうだった?」
「昔と変わらない…と言うと、そんなわけないけど」
話し方とか、雰囲気とか、大人になっていた。ような気がする。
久しく会っていなかったために、今一つ分からなかった。
「ああ。俺も忘れかけてたから。驚いたよ」
「そ、それで?」
「今すぐ会いたいって言われて。会社を早めに切り上げて、今日会ったんだよ」
「そんな、言われたから会ったって…!」
「会わないわけにはいかないよ。今後の事を考えたら」
「でも!稔くんに何かあったら…」
「…あるわけないじゃないか」
「人を殺したのよ!?無いわけないじゃない!」
「早紀さん…」
いつもは落ち着いているこの人が、明らかに狼狽している。
手に持った発泡酒の缶を、今にも落としそうだった。
「とにかく会った。それで昔の話をした。それだけで何も無かったよ」
「…様子はどうだった?」
「昔と変わらない…と言うと、そんなわけないけど」
話し方とか、雰囲気とか、大人になっていた。ような気がする。
久しく会っていなかったために、今一つ分からなかった。
「…あの事は話したの?」
「何も。俺からは触れなかったし、あいつも話さなかった」
「…」
あの事…。
彼女が、人を、殺めてしまったことだ。
もう何年前になるだろうか。
とにかく、ずいぶんと前だ。
「いつ、刑務所から出てきたの?」
「2ヶ月前って言ってたかな…」
「…また会うの?」
「分からない…けど、会おうとは言われた」
「会う気なの?」
「さあ。分からないよ」
「分からないって…もし稔くんに何かあったら…」
「早紀さん…」
心配してくれる気持ちは分かる。
しかし、みずきが俺に何かするとは思えなかった。
「何も。俺からは触れなかったし、あいつも話さなかった」
「…」
あの事…。
彼女が、人を、殺めてしまったことだ。
もう何年前になるだろうか。
とにかく、ずいぶんと前だ。
「いつ、刑務所から出てきたの?」
「2ヶ月前って言ってたかな…」
「…また会うの?」
「分からない…けど、会おうとは言われた」
「会う気なの?」
「さあ。分からないよ」
「分からないって…もし稔くんに何かあったら…」
「早紀さん…」
心配してくれる気持ちは分かる。
しかし、みずきが俺に何かするとは思えなかった。
早紀さんは肩を落としながら力なく、俺に発泡酒の缶を預けてきた。
それを受け取ってから、そのまま一気に飲み干す。
話してから、ようやく飲む気になれた。
「あいつもあいつで大変なんだよ。このご時世、不況で親の会社は倒産。それで両親とも自殺して」
「それは知ってるけど…」
「外に出てきてから、頼れる人がいなくて。今は相当苦労してるんだろう」
「…」
「頼れる人がいないなら、なるべく力になってあげたいんだよ」
「…稔くんは優しいね」
それが褒めているのか、皮肉なのか。
酔いの回り始めた今の俺には分からなかった。
それを受け取ってから、そのまま一気に飲み干す。
話してから、ようやく飲む気になれた。
「あいつもあいつで大変なんだよ。このご時世、不況で親の会社は倒産。それで両親とも自殺して」
「それは知ってるけど…」
「外に出てきてから、頼れる人がいなくて。今は相当苦労してるんだろう」
「…」
「頼れる人がいないなら、なるべく力になってあげたいんだよ」
「…稔くんは優しいね」
それが褒めているのか、皮肉なのか。
酔いの回り始めた今の俺には分からなかった。
それから、何度となく、みずきにちょくちょく会うようになった。
喫茶店や居酒屋に行って、自分たちの今の近況や、昔ばなしを語らう。
最初は二人とも遠慮していたし、再会を素直に喜べない節があった。
が、徐々に、そういう隔たりもなくなり。
塀の中の暮らしも聞いたり、あいつから喋るようにもなった。
「でねでね…」
「ふうん」
「うそー、稔がー!?」
話せば話すほどみずきは相変わらずみずきで。
髪の毛は短く、顔も大人びて。
外見こそ変わったが、中身は昔のまま、俺の知ってるみずきだった。
喫茶店や居酒屋に行って、自分たちの今の近況や、昔ばなしを語らう。
最初は二人とも遠慮していたし、再会を素直に喜べない節があった。
が、徐々に、そういう隔たりもなくなり。
塀の中の暮らしも聞いたり、あいつから喋るようにもなった。
「でねでね…」
「ふうん」
「うそー、稔がー!?」
話せば話すほどみずきは相変わらずみずきで。
髪の毛は短く、顔も大人びて。
外見こそ変わったが、中身は昔のまま、俺の知ってるみずきだった。
それでも。それでも―。
「ほんとさ、夏は暑いし、冬は寒いの。あそこって」
「お前、寒さに強くなかったっけ」
「それでも冬は寒かったよ。暖房も無いしさ」
「ふうん…」
「あとね、ちょっと痩せたからかな」
「…」
「毎年ね、冬が来るたび”あーやだなー”って。雪が降ったら布団の中で震えてたなー」
「…」
「あ、だからね、お風呂がすっごい楽しみだったの。時間は決められてたけど―」
それでも…。
再会した時より身近に感じてきたみずきだけど。
でも、こういう話を聞くと、みずきがまるで遠い世界に住んでいるかのように感じた。
「ほんとさ、夏は暑いし、冬は寒いの。あそこって」
「お前、寒さに強くなかったっけ」
「それでも冬は寒かったよ。暖房も無いしさ」
「ふうん…」
「あとね、ちょっと痩せたからかな」
「…」
「毎年ね、冬が来るたび”あーやだなー”って。雪が降ったら布団の中で震えてたなー」
「…」
「あ、だからね、お風呂がすっごい楽しみだったの。時間は決められてたけど―」
それでも…。
再会した時より身近に感じてきたみずきだけど。
でも、こういう話を聞くと、みずきがまるで遠い世界に住んでいるかのように感じた。
< 【back】