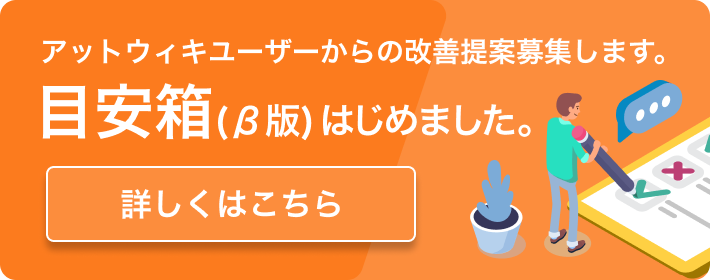「伊万里13」(2008/09/27 (土) 17:53:25) の最新版変更点
追加された行は緑色になります。
削除された行は赤色になります。
小さな先端を摘み転がしながら、藤宮は少女へ侵入する。白雪の如き肌は、桜を咲かせていた。
その心地は夢幻か、藤宮は女のように喘ぐばかり。
その快楽の酔いっぷりと来たら苦痛に身を捩じらせる少女など構いなく、
(ああ、これはたまらん)
なのであった。
「どうか抜きなさって。抜きなさって」
木の葉のような足で押し返そうとするも、藤宮、巨岩の如く動かず。
「蹴るでない。そうも動かれては我慢ならぬ」
小さき娘が動くたび、胎が擦れいちもつはどんどんと熱くなる。
粟粒のような理性が無惨に腰を動かすことを躊躇わせていた。
しかし言葉を聞かず蹴るばかりに藤宮は我慢ならず、とうとう動いてしまった。
その時の悲鳴といったら、絹と麻、どちらが裂けたものか。
「いたい。いたい。辛抱なりませぬ」
喚く娘など露知らず、藤宮は欲に脂をのせて昂ぶっていく。
(おお、これは良い。こちらこそ辛抱ならぬ)
伊万里、ついぞ諦めせめて和らごうと動きを合わせた。
これが藤宮にとってより昂ぶることとなったのは言うまでもない。
膏どころか必要な肉すらない少女の身体は背徳の悦びに薪を注ぐ。藤宮はくべららた火に燃えながら娘を突いた。
いっそう乱暴になったと思った転瞬、藤宮が伊万里に組み付きながら奥へ奥へと進む。そして、
(俺はこの娘の胎を満たしておる)
娘に欲を溶かしたのであった。
伊万里の白く繊細な透明さと怜悧さを兼ね備えた面に浮かんだのは、
その外見の幼さからは想像もつかない、ドロドロに蕩けた果実の腐臭にも似た、
あまりに妖艶であまりに淫蕩な微笑みであった。
吸い込まれる。
自分自身の意思をまるで無視して動く己の四肢に、
藤宮の理性は必死になって制御を取り戻そうと指令を送り続けるが、解き放たれた感情
―――獣欲という名の衝動に突き動かされる身体は、止まる事などありえないと言うかのように突き進む。
気が付けば、小さく柔らかな薄桃色の薔薇のような伊万里の唇と、藤宮の不器用な唇が重なり合っていた。
唇だけでは終わらない。終わるわけが無い。
まるで独立した意思を持ったかのように少女の真珠じみた歯を割って侵入した舌が、
その温かな口腔のナカを楽しむかのように這い回り、侵略する。
甘やかな唾液を貪り、荒々しく欲深く己の半分しか綯いな小さな舌を絡め捕ろうと、
そしてより奥へ奥へと侵入を果たそうと動き回る藤宮の肉体の一部分。
呼吸を塞がれた伊万里が、酸素を求めて苦しそうに喘ぐ……いや、あるいは快楽を貪るがゆえの嬌声であろうか。
どちらなのか知りたい。
今腕の中に居る少女の心を暴き、誰の眼からも隠された秘密の場所を自分の視線の下に曝け出させたい。
激しく胸を突き上げ、暴走気味に駆け巡る血液に乗って脳髄を打ち砕かんばかりに溢れ出す欲求に耐えられず、
耐えることなどハナから考えず、藤宮は少女の両足の間、
今だどんな男の前にも姿を見せた事が無いであろう部分へと指を這わせた。
ビクリと身体を震わせて、初雪を思わせる程に白く、
筋肉などまったくついていないかのように細く柔らかな脚が反射的に閉じられる。
あまりにもわずかな抵抗。けれど、その抵抗に脅えたように引っ込められた藤宮の手を、しかし伊万里の手が掴んだ。
迷子の子供を導く母親のように優しく、
漁師を誘うセイレーンの歌のように妖艶に、その手が藤宮の指先を、少女自身の秘所へと導いてゆく。
指先に伝わる熱いほどの熱と、そして指が沈んでゆきそうな肌の上を覆った―――ヌメリを帯びた感触。
「伊万里、濡れてる」
藤宮はそう、最愛の少女の耳元に熱い吐息とともに囁いた。
< 【[[back>伊万里12]]】 【[[next>伊万里14]]】 >
*注意
>性的表現を連想させたり、性的表現そのものが含まれる作品です
>これらに苦手意識や嫌悪感を抱く方が見るのはお勧めしませんが、文章なので18禁ではありません
小さな先端を摘み転がしながら、藤宮は少女へ侵入する。白雪の如き肌は、桜を咲かせていた。
その心地は夢幻か、藤宮は女のように喘ぐばかり。
その快楽の酔いっぷりと来たら苦痛に身を捩じらせる少女など構いなく、
(ああ、これはたまらん)
なのであった。
「どうか抜きなさって。抜きなさって」
木の葉のような足で押し返そうとするも、藤宮、巨岩の如く動かず。
「蹴るでない。そうも動かれては我慢ならぬ」
小さき娘が動くたび、胎が擦れいちもつはどんどんと熱くなる。
粟粒のような理性が無惨に腰を動かすことを躊躇わせていた。
しかし言葉を聞かず蹴るばかりに藤宮は我慢ならず、とうとう動いてしまった。
その時の悲鳴といったら、絹と麻、どちらが裂けたものか。
「いたい。いたい。辛抱なりませぬ」
喚く娘など露知らず、藤宮は欲に脂をのせて昂ぶっていく。
(おお、これは良い。こちらこそ辛抱ならぬ)
伊万里、ついぞ諦めせめて和らごうと動きを合わせた。
これが藤宮にとってより昂ぶることとなったのは言うまでもない。
膏どころか必要な肉すらない少女の身体は背徳の悦びに薪を注ぐ。藤宮はくべららた火に燃えながら娘を突いた。
いっそう乱暴になったと思った転瞬、藤宮が伊万里に組み付きながら奥へ奥へと進む。そして、
(俺はこの娘の胎を満たしておる)
娘に欲を溶かしたのであった。
伊万里の白く繊細な透明さと怜悧さを兼ね備えた面に浮かんだのは、
その外見の幼さからは想像もつかない、ドロドロに蕩けた果実の腐臭にも似た、
あまりに妖艶であまりに淫蕩な微笑みであった。
吸い込まれる。
自分自身の意思をまるで無視して動く己の四肢に、
藤宮の理性は必死になって制御を取り戻そうと指令を送り続けるが、解き放たれた感情
―――獣欲という名の衝動に突き動かされる身体は、止まる事などありえないと言うかのように突き進む。
気が付けば、小さく柔らかな薄桃色の薔薇のような伊万里の唇と、藤宮の不器用な唇が重なり合っていた。
唇だけでは終わらない。終わるわけが無い。
まるで独立した意思を持ったかのように少女の真珠じみた歯を割って侵入した舌が、
その温かな口腔のナカを楽しむかのように這い回り、侵略する。
甘やかな唾液を貪り、荒々しく欲深く己の半分しか綯いな小さな舌を絡め捕ろうと、
そしてより奥へ奥へと侵入を果たそうと動き回る藤宮の肉体の一部分。
呼吸を塞がれた伊万里が、酸素を求めて苦しそうに喘ぐ……いや、あるいは快楽を貪るがゆえの嬌声であろうか。
どちらなのか知りたい。
今腕の中に居る少女の心を暴き、誰の眼からも隠された秘密の場所を自分の視線の下に曝け出させたい。
激しく胸を突き上げ、暴走気味に駆け巡る血液に乗って脳髄を打ち砕かんばかりに溢れ出す欲求に耐えられず、
耐えることなどハナから考えず、藤宮は少女の両足の間、
今だどんな男の前にも姿を見せた事が無いであろう部分へと指を這わせた。
ビクリと身体を震わせて、初雪を思わせる程に白く、
筋肉などまったくついていないかのように細く柔らかな脚が反射的に閉じられる。
あまりにもわずかな抵抗。けれど、その抵抗に脅えたように引っ込められた藤宮の手を、しかし伊万里の手が掴んだ。
迷子の子供を導く母親のように優しく、
漁師を誘うセイレーンの歌のように妖艶に、その手が藤宮の指先を、少女自身の秘所へと導いてゆく。
指先に伝わる熱いほどの熱と、そして指が沈んでゆきそうな肌の上を覆った―――ヌメリを帯びた感触。
「伊万里、濡れてる」
藤宮はそう、最愛の少女の耳元に熱い吐息とともに囁いた。
< 【[[back>伊万里12]]】 【[[next>伊万里14]]】 >
表示オプション
横に並べて表示:
変化行の前後のみ表示: