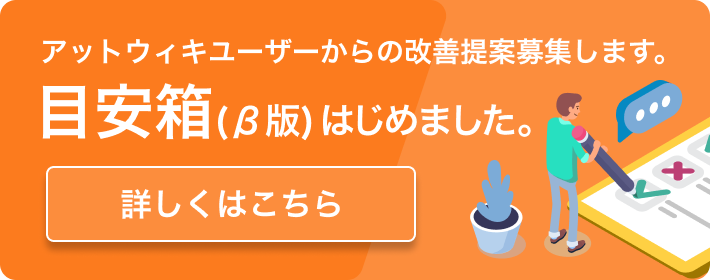「ひめ13」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る
ひめ13 - (2008/09/27 (土) 15:26:14) のソース
< 【[[back>ひめ12]]】 【[[next>ひめ14]]】 > 電子音。 文明の利器……は、どうでもいい。 ベッドの上で身体を半回転させ、耳につく電子音を放つ物体を激しく叩く。 毎朝のこととはいえいい加減に飽きてきた時計の音を夢うつつで呪いつつ、まどろみから意識をすくい上げる一瞬の脱力感を 名残惜しみつつ楽しむ。 一応朝に強い体質の自分は、姉さんと違って二度寝三度寝の誘惑に負けることは無いのだ。 ベッドから上体を起こして遮光カーテンを開け放ち、さわやかな朝の日差しを感じつつ大きく伸びをして、僅かに残った眠気を あくびと一緒に身体の外に追い出す。 ベッドから降りる頃には、もう完全に頭はすっきりしていた。 朝食の準備をする。 と言っても、今日は卵を洗って大きめの茶碗を用意するだけだ。 週に一度の朝食サボりデーである今日のメニューは、卵かけご飯。 醤油と混ぜてといた卵を、タイマーでついさっき炊きあがったばかりの白米にかけるだけ。 驚異的な手軽さで、これまた驚異的な美味さを発揮するこの手抜きメニューは、人類の宝と言っても過言ではないはずだ。 まったく、朝食からタンパク質しか頭にない地域の人たちは損をしている。こんなに美味しい朝ご飯を知らないなんて。 …………人の嗜好をとやかくいう程の人間ではないことは分かっているので、脳内冗談はこれくらいにしておく。 さて、卵かけご飯が大好きなお姫様を起こしに行かなくてはいけない。 コンコンと、姉の部屋のドアをノックする。 まああり得ないだろうが、万が一にも姉さんが俺より先に目を覚ましていて、億が一にも自分一人で着替えようなどという、 雪どころかメテオでも降ってきそうな事態が起こった場合に備えてのことだ。 案の定、返事はない。きっとまだ幸せそうな顔で夢の中を散歩しているのだろう。 ドアを開ける。 相変わらずの、少女趣味と言うのだろうか、可愛らしい部屋。その中でも殊更可愛らしい、部屋の中心に位置するベッドの中で、 この部屋で一番可愛らしい姉がすやすやと寝息をたてていた。 「すー…………すー…………」 ああ、ベイダー卿の呼吸もこんな感じだったら、ルークは一発でダークサイドに籠絡されていただろう。 毎朝起こすのを僅かに躊躇させるほど満ち足りた寝顔が、呼吸に合わせてゆっくりと動く薄い胸につられて揺らいでいる。 本当に、こんな姉が自分よりも年上だなんて、未だに信じられない。 ほんの少しだけ姉の顔に見とれた後、もう満足したので起こしに掛かる。 まずは、軽く肩に触れてゆさゆさと揺さぶる。 ゆさゆさゆさ。 「姉さん、姉さーん」 俺の腕の動きと一緒に動く姉の顔。うんうんと多少うなりはするものの、まだ起きる気配はない。 次は頬をぺちぺちとはたく。 ぺちぺちぺちぺち。 「姉さーん、朝だよー」 姉の頬は程よい肉付きで、ぺちぺちの感触は非常に良く、かつ大抵はこの方法で起きてくれるので、 実に重宝している技なのだが、今日は思いの外目を覚まさない。 ぺちぺちという手応えと共に、相変わらず起きることを全力で拒否するようなうんうんという唸りは聞こえるものの、 未だ夢心地のようだ。 今日はしぶといな、と思いつつ、最終的かつ確実な方法をとる。 それは、布団を引っぺがすこと。冬限定の技ではあるが、夏は暑がって寝付きも良くないので、 冬以外にこの第三段階までくることはそうそう無いのだ。 「といや!」 姉のもこもことした布団を一気に引っぺがす。 ベッドの上には、フリルで飾られた小さな姉だけが残った。 一瞬の後、すぐさま冬の寒気に陵辱され始めた姉は、あっという間にふりふりの身体を丸めて身を抱き、フリルの塊になる。 が、それも束の間。 寒さに抵抗できないことを本能が悟ると、途端に意識に頼るべく脳が姉を起こしに掛かる。 「うぅ…………稔くん………寒……い……」 姉の口から人間の言葉が漏れ出る。どうやら目を覚ましたようだ。 ある意味で小動物的な姉が寒がっているのを見るのは心が痛むが、起きてくれないのだから仕方がない。 「姉さん、ほら、朝だよ」 そう言いながら布団をかけ直してあげようとすると、 「さーむーいー」 と言いながら、姉は俺の腰の部分に体当たりをかましてきた。 「うおぁ!?」 よろける。が、姉は軽いので、少し踏ん張って後ろに倒れるのを防ぐ。 姉は体当たりをした勢いで俺の腰にしがみつき、 「うー……うぅぅ」 と唸り声をあげつつ、俺から体温を奪おうとしている。 「姉さん、そんなところにしがみついてても暖かくはならないよ」 そう言いつつ、姉から奪った布団で姉の下半身を包む。 「んぅー……稔くんー」 布団に包まれた姉は、徐々に脱力していきながらふにゃふにゃと二度寝に入ろうとする。 「姉さん、起きて」 崩れゆく姉を両手でがっしりとホールドし、ベッドから引きずりおろして、布団だけをベッドに残す。 「姉さん、おはよう」 「んー……おはよう、稔くん」 頭に血液が十分にのぼっていないのであろうか、どことなく無意識で喋っているような印象がある。 が、とりあえず自立しているので良しとしよう。 「姉さん、今日は卵かけご飯だよ」 ちなみに、夕べにも一度言っておいた。 「んむー、卵? ごはん?」 「そう、卵かけご飯」 姉はぐしぐしと両手で目を擦ると、まだ眠気の抜けきらない顔で俺を改めて見る。 「…………食べる~」 漫画に描いたように眠そうな顔で、こっちを見ているのが楽しい。 それにしても、朝食が大嫌いな姉が進んで食べようとする卵かけご飯は、重ね重ね偉大だ。 どうせなら毎朝そうしたいほどであるが、流石に栄養が偏るのでやめておこう。 それに、たまにの刺激にしないと、姉も飽きてしまうだろう。 心理学的に何と言っただろうか? 確か、刺激への順化とか何とか。 「ほら、姉さん、歩いて。顔洗いに行かないと」 「うんー……洗う……」 文字通り夢うつつのふよふよした足取りで洗面所に向かう姉。 無事に洗面所までたどり着いたことを確認しつつ、茶碗にご飯をよそって姉を待つべく、俺は居間へと引き返した。 「いただきます」 「……いただきます」 サボりデーの日は、姉の「いただきます」の前に無駄な沈黙があまり入らない。 ちなみに、朝食の挨拶前の無駄な沈黙の数で、その日の姉の機嫌は大体分かってしまう。 「稔くん、お醤油とって」 「んっ」 自分の卵に醤油を垂らして、醤油差しを姉に渡す。 ちなみに、俺はちょびっとだけ醤油を入れる派で、姉は黄身の周りに二重の輪ができるくらいの醤油を入れる。 熱々の湯気が立つご飯の真ん中に少しだけ箸で隙間を作り、といた卵をそこに流し込む。 お行儀が悪いのは百も承知で、流し込んだ卵をご飯と軽く混ぜ合わせ、あとはただひたすら食べるのみ。 ほこほこの炊きたてご飯に新鮮な甘い卵、日本の誇る万能調味料醤油という最強の朝ご飯向け三重奏を一口頬張ると、 なんだか不思議と頭がしゃきりとしてくる。 「ん~」 普段は嫌々朝食を摂っているが、卵かけご飯とフレンチトーストだけは美味しく頂く姉は、眠そうだがご満悦のようだ。 朝からものを食べることに抵抗のない自分には、姉の気持ちがよく分からない。 きっとそれは生理痛の分からない男、金的ダメージが分からない女のように、この先もずっと分からないのかも知れない。 が、そんな姉を朝から幸せにしてくれる卵かけご飯は偉大なのだ。 「姉さん、醤油とって」 「んー、はい」 ご飯の残りが少なくなったところで、少し醤油を足す。最後の辛い味を楽しむのもまた一興。 七味をかけてみるのも面白いかも知れない。今度やってみよう。 「えへへー、ごちそうさま」 珍しく姉の方が早く食事を終えた。 いくら好物とは言え、やはり朝食が苦手なことに変わりの無い姉は、俺の半分程度のしかご飯が入らない茶碗を使っている。 しかし食べるペースは普段よりも圧倒的に速いため、俺が姉さんに合わせるまでもなく食事は終わる。 「…………んふ?」 食事の終わった姉さんは、食前よりかは遙かに目の覚めた表情で、俺が食べ終わるのを楽しそうに眺めていた。 朝食後の姉さんは歯を磨き、俺は茶碗を洗うのが恒例になっている。 ざぶざぶと茶碗を洗い終える頃には、姉もちょうど洗面所から出てくるので、入れ替わりに俺も歯を磨く。 そうして俺も歯を磨き終わる頃になると、大体いつもこれくらいの時間でインターホンが鳴る。 今日も居間の方から、玄関のぴーんぽーんというマヌケなインターホンが聞こえてきた。 特に気にとめずにおくと、カチャリと鍵の回る音がする。うちの合い鍵を持っているのは伊万里だ。 そうして鍵を外すと、扉を開けようとして、 「ふみゃっ!?」 当然のごとく上のUの字チェーンに、がちゃんと引っかかる。 毎度のことなので特に気には留めないが、あいつもいい加減学習したらどうなのだろうか。 「みのりーん、あーけーてー」 玄関からは悲しくなるくらい間の抜けた伊万里の叫びが聞こえてくる。 「ちょっと待ってろよー」 玄関に向かい、Uの字チェーンを外すと、制服に身を包んだ幼馴染みが、相変わらずの薄幸オーラを醸しながらそこにいた。 「うぅ……みのりん、チェーン外しておいてよー」 「チェーン掛けて無かったら、うちはノーセキュリティーじゃないか」 「だから、朝起きたら外すとか」 「忙しいんだ、悪いけど」 伊万里は「よよよ」と鳴き真似で崩れ落ちる。これもほぼ一週間のインターバルで同じ事の繰り返しなので、気にしない。 「それより、姉さんを手伝ってほしいんだけど」 伊万里がほぼ毎朝うちに来てくれる理由の一つに、姉の着付けが大きい。 姉の服はとにかく難解だ。基本的に、一人ですんなり着られるものはそんなに多くない。例えそれが、学校に着ていくシャツだとしても。 何故かボタンが背中にあったり、脇腹のところで結う皮のひもがあったり、その他諸々。校則的にはどうなのだろうか? 伊万里は進んでその着付けを手伝ってくれているので、有り難い。伊万里が来なかったら、俺がやる羽目になるのだろうから。 「うん、分かったよ。みのりん、覗いちゃだめだからね?」 俺が未だかつて覗こうとした事があっただろうか。 「アホなこと言ってないで、頼んだ」 「はいはーい。ひめお姉様ー、お着替えですよー」 元気よく言いながら、居間に消えていったと思ったら姉を引っ張りながらあっという間に二階に上がっていく。何という早業。 さて、自分も見とれている場合ではない。さっさと制服を着てしまおう。暖房のない玄関は寒い。 階段を上る。しかし、何故姉はあんなに着るのが難しい服が好みなのだろうか。 準備が済んだ。 伊万里に着付けて貰った今日のシャツは、背中を皮のひもで縛るタイプのようだ。 ブレザーを着たら首もとのひもしか見えない上に、コートを着ると完全に隠れてしまう。 まあ、見えないところの美というのは、日本人の遺伝子に組み込まれたモノなのかも知れない。 それに関してとやかく言うことは無いだろう。 「じゃあ、行こうか」 そう言って居間のテレビを消し、皆で玄関に移動して靴を履く。 姉は靴も複雑だが、流石に靴まで伊万里の手を借りる必要は無い様だ。 「いってきまーす」 「いってきます」 「いってくるー」 誰も居なくなる家に、三人でいってきますの挨拶をするのもすっかり習慣になってしまった。 最初に提言したのは伊万里だが、なかなか悪くない習慣だとおもう。 鍵を掛け、一度ノブを引いて鍵が掛かったことを確認すると、三人で喋りながら学校への道を歩き始めた。 < 【[[back>ひめ12]]】 【[[next>ひめ14]]】 >