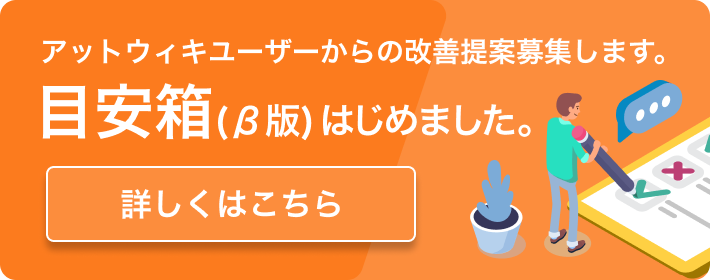完結編・その2
<子どもたち>
UGNと書かれたパラソルの下、ふんふんふんふん、と鼻歌を歌っている青年がいた。
千城寺薫(せんじょうじ・かおる)。UGNのエージェントで研究者であり、中枢評議員直属の特権階級者。
……と書くととんでもなくすごい人間のように思えてくるが、実質はちょっとマッドの気の入った不思議な発言を繰り返す自由気ままな、それでも有能な研究者である。
薫は一通り歌って満足したのか、いつものように笑顔で呟く。
千城寺薫(せんじょうじ・かおる)。UGNのエージェントで研究者であり、中枢評議員直属の特権階級者。
……と書くととんでもなくすごい人間のように思えてくるが、実質はちょっとマッドの気の入った不思議な発言を繰り返す自由気ままな、それでも有能な研究者である。
薫は一通り歌って満足したのか、いつものように笑顔で呟く。
「海はいいねぇ。まさにリリンの―――」
「言っておくけど。海はそもそも世界にあったものであって人間の生み出したものじゃないわよ。
あと、あなたが言うとその台詞は色々とシャレにならない気がするわ、薫」
「言っておくけど。海はそもそも世界にあったものであって人間の生み出したものじゃないわよ。
あと、あなたが言うとその台詞は色々とシャレにならない気がするわ、薫」
青年の隣に座っている白衣の少女がじとっとした目で見て、言った。
少女の名はテレーズ=ブルム。UGNの中枢評議員の一人で、薫と同じ研究畑の人間であり、彼の直属の上司でもある。
金の巻き毛と湖のように深い青の瞳。そんな少女がUGNの最高意思決定機関の一員だというのは、やはり見た目からは想像もつかないだろう。
そんな不機嫌そうなテレーズに、いつもどおりに薫はたずねた。
少女の名はテレーズ=ブルム。UGNの中枢評議員の一人で、薫と同じ研究畑の人間であり、彼の直属の上司でもある。
金の巻き毛と湖のように深い青の瞳。そんな少女がUGNの最高意思決定機関の一員だというのは、やはり見た目からは想像もつかないだろう。
そんな不機嫌そうなテレーズに、いつもどおりに薫はたずねた。
「あれ、そういえばテレーズちゃんは泳がないの?せっかく海に来てるんだよ?海。オーシャン」
「わざわざ英語で言い直さなくてもわかるわよ。
あのね、薫。わかってるの?」
「わざわざ英語で言い直さなくてもわかるわよ。
あのね、薫。わかってるの?」
こめかみに青筋を浮き立たせつつテレーズが尋ねる。
その空気をまっっったく読まず、薫は問い返した。
その空気をまっっったく読まず、薫は問い返した。
「え?なにがだい?」
「私がここにいる理由よっ!」
「私がここにいる理由よっ!」
ばん!と砂浜を叩いて激昂するテレーズ。
テレーズ・ブルムは先ほども言ったとおりUGNの最高意思決定機関である中枢評議会、その12人のうちの1人である。
本来はぽんぽんとこんなところにこれる立場の人間ではない。
薫は言った。
テレーズ・ブルムは先ほども言ったとおりUGNの最高意思決定機関である中枢評議会、その12人のうちの1人である。
本来はぽんぽんとこんなところにこれる立場の人間ではない。
薫は言った。
「だから、海に遊びに来たんでしょ?」
「ちがうわよっ!なんでそんなノンキなのよあなたはっ!?」
「ちがうわよっ!なんでそんなノンキなのよあなたはっ!?」
ばんばん。
砂浜を叩くものの、そこにやはり迫力は皆無である。
薫はそれにいつもの笑顔で応える。
砂浜を叩くものの、そこにやはり迫力は皆無である。
薫はそれにいつもの笑顔で応える。
「冗談ですよ冗談。暑くてテレーズちゃんもイライラしてるんじゃないかっていうちょっとした気を紛らわせるためのボクの細やかな心遣い」
「余計にイライラするだけだから次からやめて頂戴」
「了解。で―――ここに来たっていうのは、例の事件のことでしょう?」
「余計にイライラするだけだから次からやめて頂戴」
「了解。で―――ここに来たっていうのは、例の事件のことでしょう?」
そう促されて、テレーズはえぇ、と表情から怒りを抜いて答えた。
「もともと、雄吾が新しく作った支部であるアキハバラ支部っていうのは、UGN内でもとても危うい立場にあるのよ。
日本支部幹部の何人かがUGNの中枢評議員を数人抱き込んで作った支部で、ある程度人材の融通なんかは利くようになってるけど、集まってる人員がマズいのよ。
支部を与えられては全滅させる、あの長瀬明の部下だった<運命の導き手>。
UGNの一部の暴走によって生み出された異能、それを今も持つ<ファルコンブレード>。
かつて中枢評議会の動きすら停止させた、綾渕宗二の教え子<シルクスパイダー>。
さらにはUGN中枢へアクセスするための鍵、その後継者である<タクティカルヴォイス>。
他にも色々。これまで世界に巨大な変革をもたらしかねない事件に関わってきた人間ばかり。
一括監視できるといえば聞こえはいいけど、彼らの人間性を無視して話をするなら、いつでも世界にケンカ売れるメンバーなのよ」
「テレーズちゃんは人間性を無視したりしないでしょ?」
「そう考える人間もいるってことよ。
そこで、どういう力が働いたのかはわからないけどその街が隔離された。そして、それをアキハバラ支部が解決した。
どういうことなのか説明をもらわなきゃいけないけど、日本支部長が色んな反対を押し切って作った支部だから、日本内で尋問できる立場にいる人間はいない。
だから、それなりに面識のある私がくることになったのよ」
日本支部幹部の何人かがUGNの中枢評議員を数人抱き込んで作った支部で、ある程度人材の融通なんかは利くようになってるけど、集まってる人員がマズいのよ。
支部を与えられては全滅させる、あの長瀬明の部下だった<運命の導き手>。
UGNの一部の暴走によって生み出された異能、それを今も持つ<ファルコンブレード>。
かつて中枢評議会の動きすら停止させた、綾渕宗二の教え子<シルクスパイダー>。
さらにはUGN中枢へアクセスするための鍵、その後継者である<タクティカルヴォイス>。
他にも色々。これまで世界に巨大な変革をもたらしかねない事件に関わってきた人間ばかり。
一括監視できるといえば聞こえはいいけど、彼らの人間性を無視して話をするなら、いつでも世界にケンカ売れるメンバーなのよ」
「テレーズちゃんは人間性を無視したりしないでしょ?」
「そう考える人間もいるってことよ。
そこで、どういう力が働いたのかはわからないけどその街が隔離された。そして、それをアキハバラ支部が解決した。
どういうことなのか説明をもらわなきゃいけないけど、日本支部長が色んな反対を押し切って作った支部だから、日本内で尋問できる立場にいる人間はいない。
だから、それなりに面識のある私がくることになったのよ」
部下のあなたもここにいたしね、とため息とともに告げるテレーズ。
ふむふむなるほど、と言って、意地悪く目を細める薫。
ふむふむなるほど、と言って、意地悪く目を細める薫。
「つまり、テレーズ・ブルム評議員どのは彼らに余計なちょっかいが加わらないように霧谷支部長と『おはなし』しに日本に来たってことでいいのかな?」
「―――別に。たいしたことはしてないわよ、私はUGNと世界の混乱が本当にないのかどうか雄吾に聞きにきて、確信が得れたってだけだし」
「―――別に。たいしたことはしてないわよ、私はUGNと世界の混乱が本当にないのかどうか雄吾に聞きにきて、確信が得れたってだけだし」
目線をそらしてそう告げるテレーズ。
くすくす、と笑いをもらしながら薫は言う。
くすくす、と笑いをもらしながら薫は言う。
「まったく。お優しいねテレーズちゃんは」
「あのね薫。あんまり茶化してると今すぐあなたを中東あたりに飛ばしてみたくなるから、自分の命が惜しければやめてくれる?」
「あのね薫。あんまり茶化してると今すぐあなたを中東あたりに飛ばしてみたくなるから、自分の命が惜しければやめてくれる?」
はいはい降ー参、と告げて両手を挙げる薫。
テレーズは中枢評議員の一人だ。UGNの、オーヴァードの、それ以上に今の世界を続けていくための選択をとることに躊躇いはない。
けれど、彼女もオーヴァードとして、一人の人間として、自分の下で日夜日常を守り続けている同じオーヴァード達を切りすてるという選択をよしとはしない。
厳しいが優しい。甘いが強い。それがテレーズ・ブルムを端的に表す言葉であると言えるだろう。
テレーズは中枢評議員の一人だ。UGNの、オーヴァードの、それ以上に今の世界を続けていくための選択をとることに躊躇いはない。
けれど、彼女もオーヴァードとして、一人の人間として、自分の下で日夜日常を守り続けている同じオーヴァード達を切りすてるという選択をよしとはしない。
厳しいが優しい。甘いが強い。それがテレーズ・ブルムを端的に表す言葉であると言えるだろう。
「それでさテレーズちゃん。結局なんで海にいるの?」
その言葉に一瞬う、とつまるテレーズ。
今の話は日本に来た理由であって海に来た理由じゃないよねー、と歌うように薫は言う。
テレーズは一見ただの道化師気取りのバカのようなこの部下の、本質をすぱんと見抜いてしまうこういうところが頼もしく、また苦手だった。
ぎゅ、と白衣を握り締め、彼女はうつむいて言う。
今の話は日本に来た理由であって海に来た理由じゃないよねー、と歌うように薫は言う。
テレーズは一見ただの道化師気取りのバカのようなこの部下の、本質をすぱんと見抜いてしまうこういうところが頼もしく、また苦手だった。
ぎゅ、と白衣を握り締め、彼女はうつむいて言う。
「雄吾が……」
「霧谷氏がどうかしたかい?」
「……『せっかく日本くんだりまで来たんですから、実地検分も含め、彼らに一日付き添ってみてはいかがでしょう?
あぁ、それは自分で言っておきながら名案です。ではチケットはこちらにありますので。旅館の方にはこちらから言っておきましょう』って」
「霧谷氏がどうかしたかい?」
「……『せっかく日本くんだりまで来たんですから、実地検分も含め、彼らに一日付き添ってみてはいかがでしょう?
あぁ、それは自分で言っておきながら名案です。ではチケットはこちらにありますので。旅館の方にはこちらから言っておきましょう』って」
薫はなにやら背後に暗いものを背負っているテレーズの空気をやはり無視。
「つまり、バカンスを楽しみに来たってことでいいのかい?」
「よくないわよっ!私がここにいるせいで滞ってる仕事がどれだけあると思って……っ!」
「じゃあ帰ればいいじゃない。実地検分だけなら僕がやっておくからさ」
「運転手に繋がらないのよっ。雄吾がどんな手を使ってるのかなんかわからないけどっ!」
「よくないわよっ!私がここにいるせいで滞ってる仕事がどれだけあると思って……っ!」
「じゃあ帰ればいいじゃない。実地検分だけなら僕がやっておくからさ」
「運転手に繋がらないのよっ。雄吾がどんな手を使ってるのかなんかわからないけどっ!」
もはや涙目なテレーズ。
それににこにこしながら薫は返す。
それににこにこしながら薫は返す。
「まぁ、いいんじゃない?こんな日があってもさ。
霧谷日本支部長のことだし、テレーズちゃんがいなくなることで起きることくらいは計算に入れてるだろうと思うよ?」
「それはそうだけど……って、それとこれとは話が別でしょっ!?」
「どれとどれの話が別って言ってるのかは分からないけど。
キミは帰る手段がなくて、キミがいないことで起きる不利益もおそらくは最低限に軽減される。
さらには、ここにいる面子はさっきキミが言ったようにUGNへの不利益をもたらす可能性がある。
けれど、君自身がその人間性を保証できれば、もう少し彼らの身辺も落ち着くんじゃないのかな?なんてね」
霧谷日本支部長のことだし、テレーズちゃんがいなくなることで起きることくらいは計算に入れてるだろうと思うよ?」
「それはそうだけど……って、それとこれとは話が別でしょっ!?」
「どれとどれの話が別って言ってるのかは分からないけど。
キミは帰る手段がなくて、キミがいないことで起きる不利益もおそらくは最低限に軽減される。
さらには、ここにいる面子はさっきキミが言ったようにUGNへの不利益をもたらす可能性がある。
けれど、君自身がその人間性を保証できれば、もう少し彼らの身辺も落ち着くんじゃないのかな?なんてね」
うぅ、と可愛らしさからかけ離れたうめき声。
彼女は一つため息をついて、力を抜く。
彼女は一つため息をついて、力を抜く。
「……わかったわよ。今日一日だけなんだからね」
「はっはっは、日本支部長もよろこんでくれるんじゃないのかなぁ」
「はっはっは、日本支部長もよろこんでくれるんじゃないのかなぁ」
まったく、と彼女が呟いたその時だ。
「あれ、女の子だー」
ぱたぱたぱたぱた、と砂浜の上を駆けてくる軽い足音。
何事かとテレーズがそちらを向くと、そこには長くくせのない金髪をポニーテールにまとめた空色の瞳の少女だ。テレーズよりも年上のように見える。
エミリア・ラウラ。真也と同じくファントムセルの実験体。しかし割と能天気でポジティブな占い師を目指すイタリア娘。真也と同じく、ゆにばーさるの助っ人の一人だ。
鮮やかな赤が基調で黒のバラの図柄、ストラップなし、後ろは紐で止める形のワンピース、黒のパレオという派手な水着を着た彼女は薫のほうを向く。
薫は紫帆を追いかけてここ数日ゆにばーさるに贅沢に入り浸っていたので、ゆにばーさるの面々とも面識があるのである。
何事かとテレーズがそちらを向くと、そこには長くくせのない金髪をポニーテールにまとめた空色の瞳の少女だ。テレーズよりも年上のように見える。
エミリア・ラウラ。真也と同じくファントムセルの実験体。しかし割と能天気でポジティブな占い師を目指すイタリア娘。真也と同じく、ゆにばーさるの助っ人の一人だ。
鮮やかな赤が基調で黒のバラの図柄、ストラップなし、後ろは紐で止める形のワンピース、黒のパレオという派手な水着を着た彼女は薫のほうを向く。
薫は紫帆を追いかけてここ数日ゆにばーさるに贅沢に入り浸っていたので、ゆにばーさるの面々とも面識があるのである。
「薫さんのお友達?」
「うん、お友達お友達。テレーズちゃんって言うんだ、仲良くしてあげてね」
「ちょっと薫っ!?」
「うん、お友達お友達。テレーズちゃんって言うんだ、仲良くしてあげてね」
「ちょっと薫っ!?」
薫のいきなりの行動にテレーズがあわてるも、彼はあわてず騒がずテレーズに耳打ちする。
「彼女はXナンバーズとやらの一人だよ。キミが実地検分しておいた方がいい人間に入るんじゃないのかな?」
その言葉にほんの少し詰まり、しばらく逡巡するものの、テレーズは納得がいかなそうにぽつ、と答えた。
「……テレーズ・ブルムよ」
「よろしくね、テレーズ。あたしはエミリアっ!」
「えぇ。よろしく、エミリア」
「よろしくね、テレーズ。あたしはエミリアっ!」
「えぇ。よろしく、エミリア」
人懐っこい笑みを見せるエミリアに、同じく笑みを返すテレーズ。
そこへもう一人駆けてくる少女がいた。
そこへもう一人駆けてくる少女がいた。
「エミリアさんっ、やっと見つけたっ!」
亜麻色の髪をいつもの通りに高い位置でお下げにしている、薄いエメラルドの大きな瞳の少女。エミリアと同じファントムセルからの逃亡仲間、アイヴィ・ノールズだ。
薄い水色に濃い藍色のツタがからみついたような模様のツーピースでスカート型の水着。胸の前の細い白の紐リボンが風に揺れる。
慌てた様子のアイヴィに、やはりいつもどおり能天気に尋ねるエミリア。
薄い水色に濃い藍色のツタがからみついたような模様のツーピースでスカート型の水着。胸の前の細い白の紐リボンが風に揺れる。
慌てた様子のアイヴィに、やはりいつもどおり能天気に尋ねるエミリア。
「どうしたのアイヴィ。走ると転ぶよ?」
「別にそんなことはどうでもいいんですっ!真也さんにエミリアさんを連れてきてもらえないかってお願いされたんで呼びにきたんですよっ!」
「え。真也が?なんで?」
「みんなで遊ぶから一緒にやろう、って言われましたけど……」
「別にそんなことはどうでもいいんですっ!真也さんにエミリアさんを連れてきてもらえないかってお願いされたんで呼びにきたんですよっ!」
「え。真也が?なんで?」
「みんなで遊ぶから一緒にやろう、って言われましたけど……」
具体的に何で遊ぶかは聞いていない、ということらしい。
しかしエミリアは真也が呼んでるなら、と言ってテレーズを見た。
しかしエミリアは真也が呼んでるなら、と言ってテレーズを見た。
「テレーズも一緒に行こっ!せっかく海に来てるんだもん、みんなで一緒に遊ぼうよ!」
「え、えぇっ!?」
「それは名案だ。僕はちょっとここで荷物を見てるから、テレーズちゃんも遊んでおいで」
「ま、待って!待ちなさい薫!」
「エミリアさん、嫌がっているみたいですし無理矢理連れて行く、というのはちょっと……」
「えー?アイヴィだって同じ年頃のお友達ほしいでしょ?薫さんのお知り合いってことはUGN関係の人なんだろうし」
「え、えぇっ!?」
「それは名案だ。僕はちょっとここで荷物を見てるから、テレーズちゃんも遊んでおいで」
「ま、待って!待ちなさい薫!」
「エミリアさん、嫌がっているみたいですし無理矢理連れて行く、というのはちょっと……」
「えー?アイヴィだって同じ年頃のお友達ほしいでしょ?薫さんのお知り合いってことはUGN関係の人なんだろうし」
関係、どころかその運営に関わる一人だという。
ともあれ、エミリアにそうイタズラっぽい笑顔で言われたアイヴィは言葉に詰まる。
彼女はもともと孤児であり、その後は世界的に著名なピアニストになり、その後はFHの実験体として扱われてきた。
ピアノのレッスン自体は恩師と二人きり、FHの実験体は基本的に彼女よりも年上の人間ばかりと、これまで同年代の子どもと、子どもらしい遊びをしたことはない。
エミリアはそんなことおかまいなしに言っているわけだが、その言葉はピンポイントを突いてしまい、二の句が告げない。
そんなアイヴィの様子を見て、事情を紙の上からとはいえ知っているテレーズはしばらく逡巡するものの、彼女はその躊躇を断ち切ってアイヴィの手を取って歩き出す。
ともあれ、エミリアにそうイタズラっぽい笑顔で言われたアイヴィは言葉に詰まる。
彼女はもともと孤児であり、その後は世界的に著名なピアニストになり、その後はFHの実験体として扱われてきた。
ピアノのレッスン自体は恩師と二人きり、FHの実験体は基本的に彼女よりも年上の人間ばかりと、これまで同年代の子どもと、子どもらしい遊びをしたことはない。
エミリアはそんなことおかまいなしに言っているわけだが、その言葉はピンポイントを突いてしまい、二の句が告げない。
そんなアイヴィの様子を見て、事情を紙の上からとはいえ知っているテレーズはしばらく逡巡するものの、彼女はその躊躇を断ち切ってアイヴィの手を取って歩き出す。
「行くわよっ」
「え、え。テレーズさんっ!?」
「さん付けなんかいらないわよ、どうせ同い年くらいでしょ―――アイヴィ」
「え、え。テレーズさんっ!?」
「さん付けなんかいらないわよ、どうせ同い年くらいでしょ―――アイヴィ」
その言葉に一瞬きょとん、とした後、アイヴィは心底嬉しそうに二度、三度と頷いた。
「うん―――うん、うんっ!行きましょう、テレーズっ!」
「あ、待ってよ二人ともっ!あたしも行くよー!」
「あ、待ってよ二人ともっ!あたしも行くよー!」
そう言って、エミリアは手を繋いでいる二人を追いかける。
そんな光景を見ながら、薫がふふふ、と笑う。
そんな光景を見ながら、薫がふふふ、と笑う。
「UGNの評議員があんな表情してるなんて、誰も信じないだろうねぇ」
薫の横にいたテレーズのミミズクがくるっくー、と鳴いた。
<浜辺といえば>
「えー……というわけで。結希が疲れて休んでるんで、暇だろうってこの連中に引っぱられてきた檜山ケイトです」
「おい審判?誰に向かって言ってるんだー?」
「うるさいな放っておいてくれよっ!?」
「おい審判?誰に向かって言ってるんだー?」
「うるさいな放っておいてくれよっ!?」
浜辺にモルフェウス能力で特設されたビーチバレー会場。
そこにいるのは遠泳対決をしたものの、まだ若さの有り余っている体力自慢と、人数が足りないからと集められた子供達である。
ケイトは半分やけになりつつ、それでもルールを告げる。
そこにいるのは遠泳対決をしたものの、まだ若さの有り余っている体力自慢と、人数が足りないからと集められた子供達である。
ケイトは半分やけになりつつ、それでもルールを告げる。
「ルールは普通のビーチバレーに則ったルールでやる。ただし、一チーム二人じゃなくて三人って特別ルールでやるからね。
チーム分けはやっぱり顔なじみと組んだほうがわかりやすいだろうってことで、さっき言ったとおりのチームでやってもらう。
それからエフェクト使用についてだけど、まずは暴走した時点で失格。次に、ボールが一個しかないからボール自体に危害を加えた時点でも失格とする。
もちろん、コートの外の相手チームに直接エフェクトで攻撃しても失格だからね」
「ケイトくん、『糸』でボール拾ったりとかするのは?」
「ボールへの危害、に当たるから却下」
「はいはーい。<漆黒の拳>でアタックの威力上げるのはー?」
「ダメに決まってるだろっ!?なんで大丈夫だと思ってるんだ!」
チーム分けはやっぱり顔なじみと組んだほうがわかりやすいだろうってことで、さっき言ったとおりのチームでやってもらう。
それからエフェクト使用についてだけど、まずは暴走した時点で失格。次に、ボールが一個しかないからボール自体に危害を加えた時点でも失格とする。
もちろん、コートの外の相手チームに直接エフェクトで攻撃しても失格だからね」
「ケイトくん、『糸』でボール拾ったりとかするのは?」
「ボールへの危害、に当たるから却下」
「はいはーい。<漆黒の拳>でアタックの威力上げるのはー?」
「ダメに決まってるだろっ!?なんで大丈夫だと思ってるんだ!」
はぁ、とため息とついて、ケイトは力なく続けた。
「……じゃあ、チームごとに作戦会議開始ー。五分で終わらせてくれ」
はーい、と元気な声が響いた。
<チーム・オリジンの場合>
「まぁ、体力だけでいくなら俺らが負けるわけないよな」
ふふん、と胸を張って隼人が言う。実際問題、参加するチーム中、隼人・椿・狛江の三人組はもっとも身体能力の高いチームである。
白兵系3種と俗に言われるエグザイル・キュマイラ・ハヌマーンが一種ずついる時点で、体を動かすことにおいてはトップクラスであった。
そんな隼人をたしなめるのは、やはり相棒の椿だ。
白兵系3種と俗に言われるエグザイル・キュマイラ・ハヌマーンが一種ずついる時点で、体を動かすことにおいてはトップクラスであった。
そんな隼人をたしなめるのは、やはり相棒の椿だ。
「隼人。いくら得意分野でも、気を抜いたらだめ。どのチームもそんなことはわかってるんだから、その慢心をつきにくるはず。やるからには勝ちにいかないと」
そう真面目に言う椿に、少しバツが悪そうにわかってるよ、と答える隼人。
これもまた、いつもの通りの光景である。
そしてもう一人。目をキラッキラと輝かせているチームメンバーがいる。
その彼女を見て、隼人がものすごく心配げに尋ねた。
これもまた、いつもの通りの光景である。
そしてもう一人。目をキラッキラと輝かせているチームメンバーがいる。
その彼女を見て、隼人がものすごく心配げに尋ねた。
「ところで、なぁ狛江」
「え?なに隼人っ!?あたしは早くやりたいんだけどビーチバレー!」
「念のために聞くが……お前、バレーのルール知ってるのか?」
「え?なに隼人っ!?あたしは早くやりたいんだけどビーチバレー!」
「念のために聞くが……お前、バレーのルール知ってるのか?」
そうもの凄く心配そうに尋ねられた狛江。
それもそのはず。一応学生生活を送っていたことのある狛江ではあるが、基本的に頭の中は空手のことが9割を占めている。
彼女がそれ以外のことは瑣末事と済ませる脳内構造をしているのは、隼人も椿も把握済みである。
しかし、心配された方はそんなことどこ吹く風である。
狛江はむ、と唇を尖らせて隼人に言った。
それもそのはず。一応学生生活を送っていたことのある狛江ではあるが、基本的に頭の中は空手のことが9割を占めている。
彼女がそれ以外のことは瑣末事と済ませる脳内構造をしているのは、隼人も椿も把握済みである。
しかし、心配された方はそんなことどこ吹く風である。
狛江はむ、と唇を尖らせて隼人に言った。
「失礼な!あたしだってバレーくらい見たことあるんだから!」
「ほー、意外だ。スポーツは空手以外見ないもんだと思ってたが」
「アレでしょ?とにかく飛んできたボールを地面に叩きつければいいんでしょ?」
「それバレーだけどバレーじゃねぇっ!?」
「ほー、意外だ。スポーツは空手以外見ないもんだと思ってたが」
「アレでしょ?とにかく飛んできたボールを地面に叩きつければいいんでしょ?」
「それバレーだけどバレーじゃねぇっ!?」
そのやりとりを聞いた椿が一つため息。
「……狛江。とにかくあなたの近くに上がったボールは叩きつけてもいいよ。ただし、ネットの向こう側の地面に叩きつけるようにだけ気をつけて。後ネットには触らない」
「あ、やっぱりそれでいいんだ?うんっ!それなら頑張っちゃうよー!」
「私が基本レシーブを受けるから、隼人は自分で打つなり狛江にトス上げるなりブロックするなり好きにして。
たぶん、レシーブなら私が一番できると思うから」
「まぁ、そうだな。それが一番無難か……んじゃ、後は相手の出方を見ながら変更ってことで」
「あ、やっぱりそれでいいんだ?うんっ!それなら頑張っちゃうよー!」
「私が基本レシーブを受けるから、隼人は自分で打つなり狛江にトス上げるなりブロックするなり好きにして。
たぶん、レシーブなら私が一番できると思うから」
「まぁ、そうだな。それが一番無難か……んじゃ、後は相手の出方を見ながら変更ってことで」
そこまで言ったところで、狛江が何かを期待するように手を突き出していることに気づく隼人。
ジト目で率直な感想を漏らす。
ジト目で率直な感想を漏らす。
「……何やってんだお前」
「え?確かバレーってこういうのチームでやらなきゃいけないんじゃなかったっけ?」
「やらなきゃいけないわけじゃない。あれはまぁなんていうか。そう、気合入れみたいなもんだ」
「んじゃやろうよっ!あたし、バレーやるのもはじめてなんだからさっ!」
「え?確かバレーってこういうのチームでやらなきゃいけないんじゃなかったっけ?」
「やらなきゃいけないわけじゃない。あれはまぁなんていうか。そう、気合入れみたいなもんだ」
「んじゃやろうよっ!あたし、バレーやるのもはじめてなんだからさっ!」
形から入るのってどうなんだ、と隼人が肩をすくめて視線を戻すと、そこには狛江の手の上に手を重ねる椿の姿。
……その光景に隼人が見事な足ズッコケをやらかしかけたのは内緒である。
……その光景に隼人が見事な足ズッコケをやらかしかけたのは内緒である。
「なにやってんだよ椿っ!?」
「言ったでしょうやるからには全力で、って。ほら隼人も。少しはやる気出して」
「言ったでしょうやるからには全力で、って。ほら隼人も。少しはやる気出して」
いつもやる気のない相棒に対するいつもの言葉に、いつもどおり大きくため息をつきつつ、へいへい、とその手の上に手を重ねる隼人。
いつもどおりのその光景をまぶしそうに確認すると、狛江は嬉しそうに言った。
いつもどおりのその光景をまぶしそうに確認すると、狛江は嬉しそうに言った。
「チルドレンズー、ファイっオー!」
「狛江、チルドレンズってネーミングはちょっと……」
「もうちょっと捻れよお前」
「狛江、チルドレンズってネーミングはちょっと……」
「もうちょっと捻れよお前」
<チーム・アライブの場合>
紫帆は、あまりの展開の速さにちょっぴり呆然としていた。
司のカキ氷屋台を手伝っていたら、いきなりミナリにずるずる引っぱっていかれ、なし崩し的にビーチバレーに参加することになった彼女。
近くにいたテレーズも連れてこられたのか、ぶつぶつと『だから私は研究畑の人間でこういう体使うのは苦手なんだってば……』とか『逃げようかなぁ』とか言っている。
ミナリは、燃えていた。
具体的にはバレーコートを睨んで某アニメ製作会社の名を冠す立ち方で立っているくらいに燃えていた。
司のカキ氷屋台を手伝っていたら、いきなりミナリにずるずる引っぱっていかれ、なし崩し的にビーチバレーに参加することになった彼女。
近くにいたテレーズも連れてこられたのか、ぶつぶつと『だから私は研究畑の人間でこういう体使うのは苦手なんだってば……』とか『逃げようかなぁ』とか言っている。
ミナリは、燃えていた。
具体的にはバレーコートを睨んで某アニメ製作会社の名を冠す立ち方で立っているくらいに燃えていた。
「―――いいですか。紫帆、テレーズさん。私たちのすべきことは、ただ一つです」
困ったように紫帆はえーと、と呟いて答える。
「えーと、優勝すること?」
「そんなことはどうでもいいんです」
「そんなことはどうでもいいんです」
一言のもとにずばっと切って捨てられる。はい?と首を傾げる紫帆。
ミナリは負けず嫌いだからビーチバレーでも負けるのは嫌なんだろうと聞いたのだが、紫帆の思ったこととは違ったらしい。
置いてきぼりの紫帆に言って聞かせるように、びしぃっ!とあるチームを指差す。人を指差しちゃいけません。
そこには、男二人に女一人の、このビーチバレーにおいては非常に珍しく男の多い編成のチームがあった。
ミナリは負けず嫌いだからビーチバレーでも負けるのは嫌なんだろうと聞いたのだが、紫帆の思ったこととは違ったらしい。
置いてきぼりの紫帆に言って聞かせるように、びしぃっ!とあるチームを指差す。人を指差しちゃいけません。
そこには、男二人に女一人の、このビーチバレーにおいては非常に珍しく男の多い編成のチームがあった。
「あそこを、正確にはあそこにいる二人を矯正することですっ!」
……ビーチバレーでどうやって矯正するんだ。
閑話休題。
紫帆は指差されている二人を見て、言った。
閑話休題。
紫帆は指差されている二人を見て、言った。
「えーと、以蔵君と勇くんだっけ?委員長は確かに二人のこと苦手そうだもんね」
「苦手じゃありません!あまりのふがいなさに腹が立つんですっ!
聞けば、オーヴァードの自覚もなしに幼馴染にそういう話をするわ、みだりにエフェクトを使い倒すわ、女の子にはとりあえず声をかけるわ……どれだけボンクラなの!?
同じ職場で働きながら、私が彼らにどれだけ目を光らせてたかわかるっ!?」
「あー……そういえば、以蔵君と勇君女性のお客さんには必ず声をかけてたっけ。
もみじさんと委員長が毎回どついては止めてたよね」
「苦手じゃありません!あまりのふがいなさに腹が立つんですっ!
聞けば、オーヴァードの自覚もなしに幼馴染にそういう話をするわ、みだりにエフェクトを使い倒すわ、女の子にはとりあえず声をかけるわ……どれだけボンクラなの!?
同じ職場で働きながら、私が彼らにどれだけ目を光らせてたかわかるっ!?」
「あー……そういえば、以蔵君と勇君女性のお客さんには必ず声をかけてたっけ。
もみじさんと委員長が毎回どついては止めてたよね」
えぇ、と頷いてミナリはもみじを見る。
「三室戸さんは、とてもしっかりとした気丈な人です。
アレらと一緒にいることなくきちんとUGNに所属してくれればどれだけの部署が潤うか……。
まぁ、そこは本人の意思を尊重してイリーガルでも全然構わないんですが。
ともかく、それはそれとしてアレらに関わるのは三室戸さんの意思次第なので問題ないのですが、もう少しアレらはUGNとしての意識を持つべきなんです!」
「えーと……つまり、UGN魂を見せてやるってことでいいの?」
「なんですかUGN魂って。
ともかく、やるべきことはただ一つ。私たちの手で、あの二人の精神をぎったんぎったんに叩きなおすことなのっ!」
アレらと一緒にいることなくきちんとUGNに所属してくれればどれだけの部署が潤うか……。
まぁ、そこは本人の意思を尊重してイリーガルでも全然構わないんですが。
ともかく、それはそれとしてアレらに関わるのは三室戸さんの意思次第なので問題ないのですが、もう少しアレらはUGNとしての意識を持つべきなんです!」
「えーと……つまり、UGN魂を見せてやるってことでいいの?」
「なんですかUGN魂って。
ともかく、やるべきことはただ一つ。私たちの手で、あの二人の精神をぎったんぎったんに叩きなおすことなのっ!」
……はい、と頷くしかない紫帆。
紫帆はこの状況に同じく巻き込まれたテレーズを見た。
ちょっと慰めあおうと思ったのだ―――が。
紫帆はこの状況に同じく巻き込まれたテレーズを見た。
ちょっと慰めあおうと思ったのだ―――が。
「くるっくー」
目が点になる。
テレーズのいたところには、彼女がいつも肩に乗せていたミミズクがいる。そのミミズクは白いボードを支えていた。
テレーズのいたところには、彼女がいつも肩に乗せていたミミズクがいる。そのミミズクは白いボードを支えていた。
『ミナリの趣味には付き合ってられないわ。この子を置いていくので頑張ってちょうだい byテレーズ』
byとか結構お茶目だな中枢評議会評議員。
燃えるミナリと能天気にくるっくーと鳴くミミズクの間に立って、なんだか途方に暮れる紫帆であった。
燃えるミナリと能天気にくるっくーと鳴くミミズクの間に立って、なんだか途方に暮れる紫帆であった。
<チーム・ストライクの場合>
「なんかいいんちょが俺を熱烈に見てる気がするんだけど、照れるな。コレがモテの特権ってヤツ?」
「はっはっは、安心したまえ以蔵君。彼女が見てるのは僕だ、君が照れる必要なんかこの世のどこにもないんだよ」
「……あたしにはなんか睨んでるようにしか見えないんだけど」
「はっはっは、安心したまえ以蔵君。彼女が見てるのは僕だ、君が照れる必要なんかこの世のどこにもないんだよ」
「……あたしにはなんか睨んでるようにしか見えないんだけど」
もみじ、正解。
ともかく、ともみじは言った。
ともかく、ともみじは言った。
「まぁ、なし崩し的にビーチバレーやることになっちゃったんだけど……以蔵、勇くん。一言言っとくわ」
「なんだいもみじ。愛の告白か?こんなところで照れるぜ」
「君が照れる必要なんてどこにもないって言っただろう。僕への愛の告白に決まってるじゃないか」
「うるせぇっ、お前はもとの世界の紅葉ちゃんといちゃついてろよっ!
いや、そっちの紅葉も俺のもんだ!なんか本編でもみじはもみじのもんだって言ったようなするけどあれは気の迷いだったっ!」
「……僕の紅葉を愚弄すると、いくら以蔵君でも許さないよ?いや、もともと君にあげる女性なんて一人もないけどねっ!」
「ほほう、許さなけりゃどうするって?アァ?」
「ここで雌雄を決しようか。浜辺に真っ赤な華を咲かせてあげよう」
「人の話を聞きなさいあんたら」
「なんだいもみじ。愛の告白か?こんなところで照れるぜ」
「君が照れる必要なんてどこにもないって言っただろう。僕への愛の告白に決まってるじゃないか」
「うるせぇっ、お前はもとの世界の紅葉ちゃんといちゃついてろよっ!
いや、そっちの紅葉も俺のもんだ!なんか本編でもみじはもみじのもんだって言ったようなするけどあれは気の迷いだったっ!」
「……僕の紅葉を愚弄すると、いくら以蔵君でも許さないよ?いや、もともと君にあげる女性なんて一人もないけどねっ!」
「ほほう、許さなけりゃどうするって?アァ?」
「ここで雌雄を決しようか。浜辺に真っ赤な華を咲かせてあげよう」
「人の話を聞きなさいあんたら」
額をつきつけおしへしごりごりさせている二人の上に、重力で強化された二刀流ハリセンが飛ぶ。
もちろんやったのはもみじだ。
シャルやモルガンがいればツッコミをそっちに任せることもできるのだが、シャルはあの事件後すぐに帰国、モルガンは今もアキバでログイン中である。
砂に頭をうずめた二人をジトッとした目で見て、ハリセンを片方しまい、ソラリスっぽく二人にエフェクトを使用して感情を沈静化させる。
もちろんやったのはもみじだ。
シャルやモルガンがいればツッコミをそっちに任せることもできるのだが、シャルはあの事件後すぐに帰国、モルガンは今もアキバでログイン中である。
砂に頭をうずめた二人をジトッとした目で見て、ハリセンを片方しまい、ソラリスっぽく二人にエフェクトを使用して感情を沈静化させる。
「で、人の話を聞く準備はできたのかしら?」
「ふぁーい」
「イケメンチェンジ!はいはい、どうぞもみじさん」
「ふぁーい」
「イケメンチェンジ!はいはい、どうぞもみじさん」
おのおのの返事を返していそいそと焼けた砂浜に正座する二人組。返事が違うだけでほとんど対応の変わらない奴らである。
ため息をつくと、もみじは腰に片手を当ててびしっと人差し指を立てる。
ため息をつくと、もみじは腰に片手を当ててびしっと人差し指を立てる。
「とりあえず、相手の女の子に目を取られないこと」
「なんだよ、ヤキモチか?」
「ふふ。もみじさん、かわいい」
「ハリセンでホームランされたくなかったら少し黙ってて二人とも」
「なんだよ、ヤキモチか?」
「ふふ。もみじさん、かわいい」
「ハリセンでホームランされたくなかったら少し黙ってて二人とも」
ぶんっと素振りした姿は場外にもって行きそうなホームラン狙いのフルスイング。
本気で球扱いさせられかねないと理解したのか、二人は黙りこくる。
よろしい、と言って、彼女は続ける。
本気で球扱いさせられかねないと理解したのか、二人は黙りこくる。
よろしい、と言って、彼女は続ける。
「いい?このビーチバレーって、男女比1対2くらいなの。女の子オンリーのチームもあるくらいだしね。
だから、ちゃんとボールだけ見てなさい。女の子に見とれるのは禁止。見蕩れたらその時点で私の拳で殴り倒すわよ」
「なんだよ、やっぱり俺へのヤキモチか。かわいいぜもみじ」
「僕へのヤキモチを焼いてくれるとは思いませんでした。やはり、あなたも僕に……」
だから、ちゃんとボールだけ見てなさい。女の子に見とれるのは禁止。見蕩れたらその時点で私の拳で殴り倒すわよ」
「なんだよ、やっぱり俺へのヤキモチか。かわいいぜもみじ」
「僕へのヤキモチを焼いてくれるとは思いませんでした。やはり、あなたも僕に……」
おぉっと。バッターホームラン予告ですね。彼女調子いいみたいですしね、どう思いますか。
えぇ、今の彼女ならビーンボールでもホームランできそうな気がしますよ。
えぇ、今の彼女ならビーンボールでもホームランできそうな気がしますよ。
「ま、待ったもみじ!そのフルスイングは人間に向けるもんじゃなくてボールに!ボールに向けてっ!?ねぇっ!?
「そ、そうですもみじさん!それに確か選手への攻撃は禁止のはずではっ!?」
「ナイス勇!そうだよもみじ、そんな物騒な攻撃は人に向けちゃいけないんだぜっ!?」
「残念ね。禁止なのは―――相手コートへの攻撃限定よっ!」
「そ、そうですもみじさん!それに確か選手への攻撃は禁止のはずではっ!?」
「ナイス勇!そうだよもみじ、そんな物騒な攻撃は人に向けちゃいけないんだぜっ!?」
「残念ね。禁止なのは―――相手コートへの攻撃限定よっ!」
かっきーん、という音が場外まで聞こえそうなフルスイング。二つの大物が浜辺に舞う。
39℃の蕩けそうな日、炎天下の夢Let's Go Let's gameだった。
……ビーチバレーやれよお前ら。
39℃の蕩けそうな日、炎天下の夢Let's Go Let's gameだった。
……ビーチバレーやれよお前ら。
<チーム・エクソダスの場合>
真也はとりあえず他チームの惨状を見た後、たずねた。
「……なぁエミリア、アイヴィ。君たちはちゃんとバレーボールのルール知ってるよね?」
オーヴァードに常識は通用しないとか思ったのかもしれない。たぶんそれは至極正しいが。
その言葉に、エミリアは唇を尖らせる。
その言葉に、エミリアは唇を尖らせる。
「むー。なに、真也ってば知らないの?イタリアはバレーのプロリーグまであるんだから。
うちはそんなに裕福じゃなかったけど、基本的なルールくらいはわかるよ?」
「あぁ、そういえばエミリアはイタリア出身だっけ。だったら安心かな。アイヴィは?」
うちはそんなに裕福じゃなかったけど、基本的なルールくらいはわかるよ?」
「あぁ、そういえばエミリアはイタリア出身だっけ。だったら安心かな。アイヴィは?」
X島を脱出するまでの話を聞いてはいた真也はそれで納得する。スポーツ関連の知識はアスリートの真也は強いのである。<知識:スポーツ>持ってなさそうだけど。
アイヴィはしばらくきょろきょろしながら、あれーテレーズがいないー、と呟いていたものの、真也の問いに答える。
アイヴィはしばらくきょろきょろしながら、あれーテレーズがいないー、と呟いていたものの、真也の問いに答える。
「え?あ、はい……そうですね、見たことはあります。何回か招待状をいただいて、先生に気分転換に連れて行ってもらったことがありますんで」
「そうか。なら少しはルールわかるね。まぁ……こんなこともそんなにないだろうから、楽しみながらやればいいんじゃないかな」
「そうか。なら少しはルールわかるね。まぁ……こんなこともそんなにないだろうから、楽しみながらやればいいんじゃないかな」
ぐるん、と腕を回しながらそう言う真也。
それに不安そうな顔をしていたアイヴィはくすりと笑って言った。
それに不安そうな顔をしていたアイヴィはくすりと笑って言った。
「うん、そうですね」
「そうそうっ!一緒にたのしもーよ、アイヴィ」
「せっかく海に来たんだし、僕らは思い切り楽しもうよ」
「そうそうっ!一緒にたのしもーよ、アイヴィ」
「せっかく海に来たんだし、僕らは思い切り楽しもうよ」
笑顔で頷く少女達。
夏の海でのビーチバレー、それは日常を奪われた彼らにとってはかけがえのない夏の思い出になることだろう。
夏の海でのビーチバレー、それは日常を奪われた彼らにとってはかけがえのない夏の思い出になることだろう。
「とにかく飛んできたの全部打つよっ!」
「バレーのルールに則りさえすればなにしても問題ないんですよね。ふふ、ふふふ」
「あーもう。他の皆さんに迷惑かけないようにやんなきゃダメだって言ってんでしょうが」
「バレーのルールに則りさえすればなにしても問題ないんですよね。ふふ、ふふふ」
「あーもう。他の皆さんに迷惑かけないようにやんなきゃダメだって言ってんでしょうが」
……相手が日常を逸脱しまくってる、というのはこの際目をつぶった方がいいような気もする。