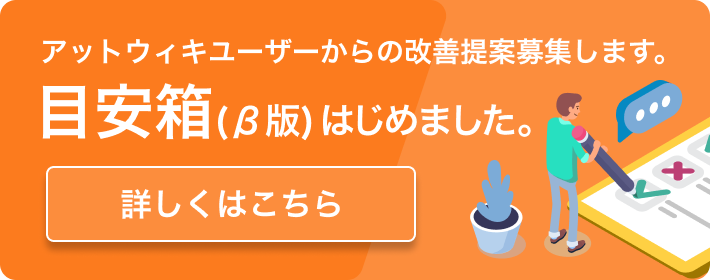拝啓 遠い昔にお空の向こうに行ってしまったご先祖様。
わたくしも色々な場所に行った経験があるのでありますが、こんな事態は初めてでどうしたらいいかわかりません。
わたくしも色々な場所に行った経験があるのでありますが、こんな事態は初めてでどうしたらいいかわかりません。
「お前、初めて見る」
「わ、わたくしもあなたに会うのははじめてであります。初めて同士でありますな」
「……可愛い」
「はい?」
「可愛い子、抱きしめる。私も幸せ。キュウ」
「いえいやあのキュウって、ちょっと待ってほしいでありますよーっ!?」
「わ、わたくしもあなたに会うのははじめてであります。初めて同士でありますな」
「……可愛い」
「はい?」
「可愛い子、抱きしめる。私も幸せ。キュウ」
「いえいやあのキュウって、ちょっと待ってほしいでありますよーっ!?」
ここがどこなのかを確認する間もなく、意外と大きな胸に挟まれて窒息しかけているこの状況を何とかする方法を、今すぐわたくしに届けてください。電波で。
***
「吸血鬼。ヴァンパイア。カインの使徒。
呼び方なんてどうでもいいがネ、そういうものがいるとするなラ、彼らは非常に可哀想な生き物だと思わないかネ?」
「吸血鬼。ヴァンパイア。カインの使徒。
呼び方なんてどうでもいいがネ、そういうものがいるとするなラ、彼らは非常に可哀想な生き物だと思わないかネ?」
誰にともなくそう語るのは、『東の狂人』。
彼はいつもと変わらない含みのある笑顔を浮かべながら、言葉を続ける。
彼はいつもと変わらない含みのある笑顔を浮かべながら、言葉を続ける。
「ニンニクが食べられないかラ、太陽が浴びられないかラ、十字架に触れば死んでしまうかラ。
どれも違うヨ。彼らには最大にして最悪の弱点が存在すル」
どれも違うヨ。彼らには最大にして最悪の弱点が存在すル」
血のように赤いフルボディの注がれたグラスをくるりと回し、言葉は続く。
「それは『人間がいなければ生きていけない』という点サ。
彼らは自分達がエサとする人間の血がなければ生きていけなイ。生まれてから死ぬまデ、一定期間にエサの血を摂取しなければ生きることすらかなわなイ。
その生き方ハ、まるで先天性の重病を背負った人間が一生薬を飲まなければならないのと変わらなイ。
そんな状態で不老不死なんて与えられたラ、私ならすぐにでも太陽を浴びて死にたくなるところだと言いたいネ!」
彼らは自分達がエサとする人間の血がなければ生きていけなイ。生まれてから死ぬまデ、一定期間にエサの血を摂取しなければ生きることすらかなわなイ。
その生き方ハ、まるで先天性の重病を背負った人間が一生薬を飲まなければならないのと変わらなイ。
そんな状態で不老不死なんて与えられたラ、私ならすぐにでも太陽を浴びて死にたくなるところだと言いたいネ!」
クツクツとした笑い声。
まるで、今までの自分の発言が全て笑い飛ばせる戯言である、とでも言うように。
まるで、今までの自分の発言が全て笑い飛ばせる戯言である、とでも言うように。
「もっとモ、今回の『吸血鬼』は本当に人間の血を必要としているようには見えないんだがネ」
***
「これで17人目なんだってなー、まったく何やってんだよ。
この島は平和な時は退屈で人が殺せるくらいに平和だっつーのに、平和じゃない時は人が死に続けるくらい平和じゃねーってぇのな!
色々とあだ名持ってる連中は多いが、今度の『吸血鬼』クンはまた派手なデビューを飾ってんなぁ。
つーかむしろあだ名しかないのってジョップリンのヤツくらいだと思ってたが、『吸血鬼』の野郎はアレと並ぶことでも考えてんのかね?
ヒャハハハハハハ! どう思うよ、クズ!」
「『吸血鬼』が男か女かもわかってないわけだがな」
この島は平和な時は退屈で人が殺せるくらいに平和だっつーのに、平和じゃない時は人が死に続けるくらい平和じゃねーってぇのな!
色々とあだ名持ってる連中は多いが、今度の『吸血鬼』クンはまた派手なデビューを飾ってんなぁ。
つーかむしろあだ名しかないのってジョップリンのヤツくらいだと思ってたが、『吸血鬼』の野郎はアレと並ぶことでも考えてんのかね?
ヒャハハハハハハ! どう思うよ、クズ!」
「『吸血鬼』が男か女かもわかってないわけだがな」
白いワゴンにもたれかかった金髪女と、がっしりとした男がそんな会話をしていた。
金髪の女は、この島唯一の「DJ」。
そんな彼女と話している男は「自警団の番犬」。
彼らが話をしているのは、この『島』で最近起きている連続殺人のことについてだ。
金髪の女が、クズと呼んだ番犬に、やはり笑いながら話しかける。
金髪の女は、この島唯一の「DJ」。
そんな彼女と話している男は「自警団の番犬」。
彼らが話をしているのは、この『島』で最近起きている連続殺人のことについてだ。
金髪の女が、クズと呼んだ番犬に、やはり笑いながら話しかける。
「なんだ? クズは『吸血鬼』が女な方がいいってか?
ヒハハ、この真性マゾ野郎。そういうこと言ってっと毛布ん中で噛みつくぜ」
「……まだ陽も高いうちから何を言ってる」
「しかしアレだな、『吸血鬼』ってヤツは風情がねぇな。
そもそも吸っただけで殺しちまうくらい大量に血を奪うなんざ、よっぽど腹ペコなのかね!
その空きっ腹に大量のニンニクぶち込んでやったら死ぬのかねあぁいう連中は?」
ヒハハ、この真性マゾ野郎。そういうこと言ってっと毛布ん中で噛みつくぜ」
「……まだ陽も高いうちから何を言ってる」
「しかしアレだな、『吸血鬼』ってヤツは風情がねぇな。
そもそも吸っただけで殺しちまうくらい大量に血を奪うなんざ、よっぽど腹ペコなのかね!
その空きっ腹に大量のニンニクぶち込んでやったら死ぬのかねあぁいう連中は?」
そんな、女の意味のない問いに、男は本当にどうでもよさげに答える。
「さあな。どっちにしろ、俺のやることは一つしかない」
「ヒャハハハハハハ! それもそうだ、お前みたいなクズ野郎にできることなんざ一つしかないってのな!」
「ヒャハハハハハハ! それもそうだ、お前みたいなクズ野郎にできることなんざ一つしかないってのな!」
男の言葉に、女は心底楽しげに笑った。
***
おかしな『島』の中にある、おかしな連中の集まるラーメン屋。
そこには今、虹色の頭の男と銀髪のゴスロリ少女が隣の席でラーメンをすすっていた。
おかしな『島』の中にある、おかしな連中の集まるラーメン屋。
そこには今、虹色の頭の男と銀髪のゴスロリ少女が隣の席でラーメンをすすっていた。
「な、竹さんのラーメンは絶品だろ?」
「隼人の言ったとおりでありますなっ! ニンニクラーメンチャーシュー抜きがこんなにおいしいものだとは……!」
「戌井、今すぐその子にチャーシュー返せ。でなきゃ出てけ」
「ひでぇ! 俺今日は支払いの時に今までのツケ一緒に払おうと思ってたのに!」
「ツケだけ置いてさっさと出てけ」
「さらに容赦なくなった!」
「隼人の言ったとおりでありますなっ! ニンニクラーメンチャーシュー抜きがこんなにおいしいものだとは……!」
「戌井、今すぐその子にチャーシュー返せ。でなきゃ出てけ」
「ひでぇ! 俺今日は支払いの時に今までのツケ一緒に払おうと思ってたのに!」
「ツケだけ置いてさっさと出てけ」
「さらに容赦なくなった!」
困ったね、と言わんばかりにぺちんと虹色頭の男は自分の額を叩く。
そんな彼から目線を外し、このラーメン屋の店主・通称竹さんが迷惑な常連客の連れてきた少女に話しかける。
そんな彼から目線を外し、このラーメン屋の店主・通称竹さんが迷惑な常連客の連れてきた少女に話しかける。
「にしても、見ない顔だな。お前さん最近この島に来たのか?」
「初めてお目にかかるでありますよ。わたくしノーチェと申す者であります。
今は西と東の境目で、日がな一日占い師やって生計立ててるのでありますよ」
「初めてお目にかかるでありますよ。わたくしノーチェと申す者であります。
今は西と東の境目で、日がな一日占い師やって生計立ててるのでありますよ」
戌井に奪われたチャーシューを返してもらいながらノーチェが言った言葉に、竹さんは眉をしかめる。
「占い師ねぇ……病院といい占い師といい、ここ最近これまで『島』になかった職業が増えてくな。
どっちも生計立てられるような仕事なのか? 特にお前さんはトロそうだからな、売り上げを襲われそうな気がするんだが」
「病院のことはよくわからないでありますが、わたくしこれでも逃げ足には自信がありましてな。
今日は、隼人が占いしたお礼にいいところに連れていってくれると言ったのでついてきたのでありますよ」
「いや、それはダメだろう」
「俺もそう思う」
「隼人までっ!?」
どっちも生計立てられるような仕事なのか? 特にお前さんはトロそうだからな、売り上げを襲われそうな気がするんだが」
「病院のことはよくわからないでありますが、わたくしこれでも逃げ足には自信がありましてな。
今日は、隼人が占いしたお礼にいいところに連れていってくれると言ったのでついてきたのでありますよ」
「いや、それはダメだろう」
「俺もそう思う」
「隼人までっ!?」
***
東区画、ある路地裏。
死体の発見報告を聞いて、スペイン系の伊達男とプロレスラーのような体格のつり目の大男―――『東の護衛部隊』のうちの2人が現場に到着していた。
ふむ、と色男が死体を見て一言。
死体の発見報告を聞いて、スペイン系の伊達男とプロレスラーのような体格のつり目の大男―――『東の護衛部隊』のうちの2人が現場に到着していた。
ふむ、と色男が死体を見て一言。
「俺、男の死体をじっくり見る趣味はないんだけど」
「そんな奴がいるなら目の前からフランケンシュタイナーで消してやる」
「ゲ。あんなアクロバティックな技もできんの?」
「お前の体で試してやろうか?」
「冗談。お前の太ももに挟まれるくらいなら頭ブチ抜いて死んだ方がマシだ」
「そんな奴がいるなら目の前からフランケンシュタイナーで消してやる」
「ゲ。あんなアクロバティックな技もできんの?」
「お前の体で試してやろうか?」
「冗談。お前の太ももに挟まれるくらいなら頭ブチ抜いて死んだ方がマシだ」
もちろん、愛すべき女の子がしてくれるなら俺はどんなことでも受け入れるけどね、と色男。
そんな軽口に苛立たしげに舌打ちしながら、大男が死体の首筋を覗き込む。
そこにあるのは二つの小さな傷跡。
それは、ここ最近島内で起きている連続殺人で殺された死体たちと同じ特徴だ。
首筋に二つの小さな傷跡、そして体のほとんどの血液が奪われるという殺され方。
日常的に人の死ぬこの島において、その死に方は非常に珍しい―――というよりも、ほぼ見られない死に方だ。
銃で撃たれた死体、刃物で切られた死体、鈍器で潰された死体、関節がねじくれた死体、薬漬けの死体などは珍しくないが、血が抜き取られた死体などそうはない。
そんな軽口に苛立たしげに舌打ちしながら、大男が死体の首筋を覗き込む。
そこにあるのは二つの小さな傷跡。
それは、ここ最近島内で起きている連続殺人で殺された死体たちと同じ特徴だ。
首筋に二つの小さな傷跡、そして体のほとんどの血液が奪われるという殺され方。
日常的に人の死ぬこの島において、その死に方は非常に珍しい―――というよりも、ほぼ見られない死に方だ。
銃で撃たれた死体、刃物で切られた死体、鈍器で潰された死体、関節がねじくれた死体、薬漬けの死体などは珍しくないが、血が抜き取られた死体などそうはない。
まるで殺すのが目的よりも、別の目的があって結果的に死んでしまった、というような。
だからこそ、この事件の犯人は『吸血鬼』というあだ名で呼ばれているのだった。
だからこそ、この事件の犯人は『吸血鬼』というあだ名で呼ばれているのだった。
「確かに『吸血鬼』ヤロウの仕業みたいだな。
―――見てて気持ちのいいモンでもねぇ、さっさと死体処理屋に任せるか」
「オイオイ、死体処理屋じゃなくて医者だろ?」
「ウチの隊長に初対面で『ナースなメイド服着てわたしの天使になってくれないか』とか言う性格破綻者は医者とは言わねぇ」
―――見てて気持ちのいいモンでもねぇ、さっさと死体処理屋に任せるか」
「オイオイ、死体処理屋じゃなくて医者だろ?」
「ウチの隊長に初対面で『ナースなメイド服着てわたしの天使になってくれないか』とか言う性格破綻者は医者とは言わねぇ」
言いながら、彼はその性格破綻者に向けて連絡をとるために携帯を取り出した。
***
「つまりですね、事件なわけですよ!」
「……はぁ」
「……はぁ」
ノーチェは、いきなり彼女の出している店の前までやって来てそう宣言した少女に面食らった。
少女の顔はかなり整っており、可愛らしい、と言っても差し支えない。その隣にいる顔の似た少年は頭を抱えている。
その2人をじっくりと見比べた後、ノーチェは少女の方に顔を向けて尋ね返す。
少女の顔はかなり整っており、可愛らしい、と言っても差し支えない。その隣にいる顔の似た少年は頭を抱えている。
その2人をじっくりと見比べた後、ノーチェは少女の方に顔を向けて尋ね返す。
「で、何が事件なんでありますか?」
「何を言っているんです。今この島で一番の話題と言えば『吸血鬼』の事件に決まってるじゃありませんか!」
「えぇと……それで、その事件がどうかしたのでありますか?」
「何を言っているんです。今この島で一番の話題と言えば『吸血鬼』の事件に決まってるじゃありませんか!」
「えぇと……それで、その事件がどうかしたのでありますか?」
当然と言えば当然のその質問に、少女―――シャーロットは答えた。
「吸血鬼と言えば不思議! 魔法とかそんな感じの生き物でニンニクとか十字架とか太陽がダメなはずです!
えぇと、そんなわけで占い師とかいう不思議な職業をしてるあなたは吸血鬼なはずで太陽が苦手ですよね!?」
「姉さん、今真昼なんだけど……」
「お日様燦々でありますなー」
えぇと、そんなわけで占い師とかいう不思議な職業をしてるあなたは吸血鬼なはずで太陽が苦手ですよね!?」
「姉さん、今真昼なんだけど……」
「お日様燦々でありますなー」
沈黙。
「え、えぇっと……そう! ニンニク、ニンニクはお嫌いですよねっ!?」
「この間、ラーメン屋さんでニンニクラーメンチャーシュー抜きを食べてましたよね?」
「あぁ、あそこのラーメンおいしいでありますな」
「この間、ラーメン屋さんでニンニクラーメンチャーシュー抜きを食べてましたよね?」
「あぁ、あそこのラーメンおいしいでありますな」
さらに沈黙。
「ふ、ふふふふふ。いいでしょうこれは私への挑戦と受け取りました!
いつか必ずあなたが吸血鬼であると証明してみせましょう、私の名にかけて!」
「姉さん、また何か変なものに影響されたね……?」
いつか必ずあなたが吸血鬼であると証明してみせましょう、私の名にかけて!」
「姉さん、また何か変なものに影響されたね……?」
そして去っていく姉弟を見ながら、一人取り残されたノーチェは呟いた。
「うーん……凄い方でありましたなぁ。わたくしも気をつけねば」
***
西区画、幹部の私室。
「―――『吸血鬼』については、何かわかった?」
「すまない」
「すまない」
自身の「影」である「忠犬」にそう告げた彼女は、しかし彼から望んでいた答えを返してもらえずに少し不満げに眉を寄せる。
「太飛からも情報が得られないというのは、流石に異常な事態ね。
何か見落としていることでもあるのかしら。誠一、あなたは何か気づいたことは?」
「……少し、思ったことがある」
何か見落としていることでもあるのかしら。誠一、あなたは何か気づいたことは?」
「……少し、思ったことがある」
珍しい、と思いながら彼女はその言葉をさえぎらない。
「影」は発言を許可されたと考え、言葉を続けた。
「影」は発言を許可されたと考え、言葉を続けた。
「やはり、普通に殺すのならば血液を抜くのは時間がかかりすぎる。
手段と時間はもちろんのこと、両陣営の手の入らない場所を確保してまでそんなことをする必要性がわからない」
「わからない、というのが思ったこと?」
「殺すのが目的ならば、そこまで時間をかける必要はない」
手段と時間はもちろんのこと、両陣営の手の入らない場所を確保してまでそんなことをする必要性がわからない」
「わからない、というのが思ったこと?」
「殺すのが目的ならば、そこまで時間をかける必要はない」
その言葉に、西区画の幹部であるところの彼女は眉をひそめる。
「―――もしかして『吸血鬼』の仕業だ、なんて馬鹿なことを考えているの?」
「そうでないとするなら、『殺すこと』が目的ではないのだと思う。
奪った血を目的とするのが吸血鬼だとするなら、案外死体でも目的なのかもしれないな」
「そうでないとするなら、『殺すこと』が目的ではないのだと思う。
奪った血を目的とするのが吸血鬼だとするなら、案外死体でも目的なのかもしれないな」
もっとも、この島では集めようと思えば死体なんていくらでも手に入るんだが、と皮肉気に笑いながら「影」は言った。
***
「大丈夫でありますかー? ねぇ、大丈夫でありますかってば」
「大丈夫でありますかー? ねぇ、大丈夫でありますかってば」
倒れているのは、成人に少し届かないくらいに見える少女。
その少女に、ノーチェはぺちぺちとほっぺたを叩いて覚醒を促す。
その少女に、ノーチェはぺちぺちとほっぺたを叩いて覚醒を促す。
「もう大丈夫でありますから、そろそろ起きてほしいのでありますよー……」
ノーチェは、背後からはがいじめにされて襲われている少女を発見。助けようと駆け寄ると、襲っていた相手は逃げてしまったのだ。
ぐったりとしているものの、外傷のない少女を起こして安全なところまで送り届けようと思っていたノーチェは、少女に語りかける。
その時だ。
ぐったりとしているものの、外傷のない少女を起こして安全なところまで送り届けようと思っていたノーチェは、少女に語りかける。
その時だ。
バルルルルルルrrrr……
遠くから、何かのうなりが近づいてくるのが聞こえる。
まるでエンジン音のようだが、それは上の方から聞こえてくる。
この島で車に乗って移動するものはいるが、さすがに空飛ぶ車なんて非常識なものを持っていた人間はいなかったはずだ。
なんだろう、とノーチェが上に視線を向けると―――
まるでエンジン音のようだが、それは上の方から聞こえてくる。
この島で車に乗って移動するものはいるが、さすがに空飛ぶ車なんて非常識なものを持っていた人間はいなかったはずだ。
なんだろう、とノーチェが上に視線を向けると―――
―――ビルの屋上から木の板を斬りつけて減速しながら、両手に一本ずつのチェーンソーを持った非常識な女性が降りてくるところだった。
彼女はまるで「猫」のように、しなやかに空中で一回転しながら音も立てずに着地し、ノーチェの鼻先に激しく回転を続けるチェーンソーを突きつける。
いきなりの事態にぴぃっ!? となにやら可愛らしい悲鳴を上げるノーチェに、チェーンソーの爆音にも関わらず女性は話しかける。
いきなりの事態にぴぃっ!? となにやら可愛らしい悲鳴を上げるノーチェに、チェーンソーの爆音にも関わらず女性は話しかける。
「アハハッ、ねえねえ貴方美咲に何してるの? 何してたの? もしかして血を採ろうとしてたっ?
ねえねえねえねえ答えてよ、答えてください。貴方がこの島に来た『吸血鬼』なの? 美咲も襲おうとしてたの? 答えてくださいよ!」
「ま、待ってぇぇぇぇええええっ!? わ、わたくしちょうど通りかかったただの占い師でありますからー!」
「すみませーん! 全然聞こえないですよぅ占い師さん!」
「聞こえてる! 絶対聞こえててやってるでありますよねっ!?」
ねえねえねえねえ答えてよ、答えてください。貴方がこの島に来た『吸血鬼』なの? 美咲も襲おうとしてたの? 答えてくださいよ!」
「ま、待ってぇぇぇぇええええっ!? わ、わたくしちょうど通りかかったただの占い師でありますからー!」
「すみませーん! 全然聞こえないですよぅ占い師さん!」
「聞こえてる! 絶対聞こえててやってるでありますよねっ!?」
***
月の下、島の中。
「……そろそろ、潮時というやつですか」
1人。その人物はただ、海を見ていた。
思ったよりも、追求の手が伸びるのは早かった。
さすがは大きな組織の人間だ。もう少し、実験のための材料をそろえたかったのだが。
思ったよりも、追求の手が伸びるのは早かった。
さすがは大きな組織の人間だ。もう少し、実験のための材料をそろえたかったのだが。
「―――仕方ありません。規格もそろったことですし、始めましょう」
一陣の風が吹き抜ける。
「赤い、赤い血の夜を」
***
すでに命を失い、体の中身すらもすでに人とはかけ離れたものにされた、『吸血鬼』の生み出した死者の群れが、島を埋め尽くす。
そして―――その事態に動いた者達がいた。
すでに命を失い、体の中身すらもすでに人とはかけ離れたものにされた、『吸血鬼』の生み出した死者の群れが、島を埋め尽くす。
そして―――その事態に動いた者達がいた。
「ハ―――ゾンビ映画は大抵パニックホラーものだから見たことがなかったんだが、いくら殺してもモブが湧いて吹き飛び続けるってのは盛り上がり所がねぇな!
うん、俺今度からゾンビ映画も見るよ! んで対処法覚える! 今回くらいしかこんなことは起きないだろうけどな!」
うん、俺今度からゾンビ映画も見るよ! んで対処法覚える! 今回くらいしかこんなことは起きないだろうけどな!」
言いながら、2丁拳銃で死者を吹き飛ばす虹色の『狂犬』。
「どうせ、どこかにいるんだろう。このゾンビ共を見てはしゃがないはずもないからな。
ついでに始末する機会ができた、と思っておくとしよう」
ついでに始末する機会ができた、と思っておくとしよう」
死者の群れの向こうに、1人の男の姿を幻視する黒衣の『忠犬』。
「眠い、寝たい。邪魔する、眠れない。お前たち、可愛くない。
だから殺す。壊す」
だから殺す。壊す」
無表情の中に、珍しく苛立ちを露にする白い白い『眠り姫』。
「島の中で空気を乱す者が死者とはな。目障りだ、もう一度獄卒のところに送ってやろう。
……まったく。貴様等のようなものが存在していては、愚か者が飛び込んだ時について頭を痛めなくてはならん」
……まったく。貴様等のようなものが存在していては、愚か者が飛び込んだ時について頭を痛めなくてはならん」
冷静の中に、形容しがたい感情を持て余す若き『西の長』。
「貴方たちは、この島で生きようとしてる人じゃない。この島に生きてる人でもない。
もう死んでる人たちに、この島を荒らされるのは我慢できないので―――私が、止めますね」
もう死んでる人たちに、この島を荒らされるのは我慢できないので―――私が、止めますね」
凶暴な二つの爪に、エンジンを灯す護衛部隊の隊長の『猫』。
「あーあ、潤も皆も行っちゃったんだし―――出てきなよ、いるんでしょ?」
「……ゴメン。ナズナさんに、あんな連中が触るかもしれないのは我慢できないから、来たよ」
「……ゴメン。ナズナさんに、あんな連中が触るかもしれないのは我慢できないから、来たよ」
護衛部隊の『刀使い』に呼ばれ、「島」で最高の『殺人鬼』が現れる。
「『洪水は、来る前に逃げろ。それができないなら出来る限り上に逃げろ』か。
一食分の恩義にしては、やけに大きな恩返しがきたね」
一食分の恩義にしては、やけに大きな恩返しがきたね」
廃ビルの屋上から下を見る、『小ネズミ』たちと『鼠の王』。
「言葉が聞こえているはずもない連中と話をするのは馬鹿げたことだとケリーの奴には言われたが、これが俺の流儀なんでな。
一応言うぞ―――全員、落ち着け」
一応言うぞ―――全員、落ち着け」
この島における、最強で最高のヒーロー。『番犬』。
そして。
***
空にかかるのはとろけたような三日月。島を埋め尽くす死者の群れ。
死のニオイに満ちる島の中、そこだけは死者がいない。
死のニオイに満ちる島の中、そこだけは死者がいない。
そんな場所で、1人月を見上げている人間がいた。まるで、自分にとっては死者の群れが脅威ではないとでもいうように。
ただただ、そいつは月を見る。ふぅ、と軽い溜め息をついた。
ただただ、そいつは月を見る。ふぅ、と軽い溜め息をついた。
そんな、月を見ている人間に街灯を遮る影が差した。
なんだろう、と思ってそちらを見れば、そこには同じく月を見上げる少女がいた。
少女は、月を見上げたままそいつに話しかける。
少女は、月を見上げたままそいつに話しかける。
「いい月夜でありますな。
白いお月様は、わたくし大好きでありますよ」
白いお月様は、わたくし大好きでありますよ」
まるでそれ以外の月は嫌いだとでもいうように。
少女は、あなたはどうでありますか? とたずねながら、目線を月からそいつへと移して続ける。
少女は、あなたはどうでありますか? とたずねながら、目線を月からそいつへと移して続ける。
「ねぇ―――『吸血鬼』さん?」
そいつは、少女の言葉に背筋を凍らせた。
少女の顔には、まるで今宵の月のようにまがまがしくとろけた笑みがある。
少女の顔には、まるで今宵の月のようにまがまがしくとろけた笑みがある。
***
ナイトウィザード×越佐大橋シリーズ
『ごく×ごく(吸血×奪血)』
『ごく×ごく(吸血×奪血)』
公開未定!
***
「カン違いされがちなのでありますが。
わたくし―――冤罪を受けて黙ってられるほど、甘くはないのでありますよ?」
わたくし―――冤罪を受けて黙ってられるほど、甘くはないのでありますよ?」
| ← Prev | List | Next → |