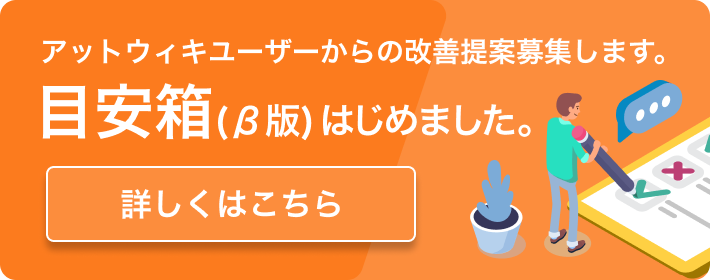END?? 『ひめの愛 ひめの鞭』
暗い……
真っ暗だ……
目を閉じているわけじゃない。
地下室は、一つも明かりが点けられていなかった。
「いま、な……んじ……だ……?」
つぶやいた声が、狭い部屋の中で反響する。
「ぅ……」
記憶がぼやけている。舌が痺れて、肺が苦しい。意識が定まらない。
姉さんに飲まされたクスリの影響だろうか。
手錠の鉄臭さを感じ取れるくらい神経は鋭敏なのに、それが何であるかを理解する脳の反応が落ちているようだった。
「いま、な……んじ……だ……?」
同じ言葉を繰り返す。
駄目だ。考えがまとまらない。
窓も明かりも時計も無いこの部屋で、後ろ手に手錠をはめられ、椅子に縛り付けられた状態では時間の経過なんて分かるわけがない。
姉さんに閉じ込められてから、一体どれくらいの時間が経ったのだろうか……
真っ暗だ……
目を閉じているわけじゃない。
地下室は、一つも明かりが点けられていなかった。
「いま、な……んじ……だ……?」
つぶやいた声が、狭い部屋の中で反響する。
「ぅ……」
記憶がぼやけている。舌が痺れて、肺が苦しい。意識が定まらない。
姉さんに飲まされたクスリの影響だろうか。
手錠の鉄臭さを感じ取れるくらい神経は鋭敏なのに、それが何であるかを理解する脳の反応が落ちているようだった。
「いま、な……んじ……だ……?」
同じ言葉を繰り返す。
駄目だ。考えがまとまらない。
窓も明かりも時計も無いこの部屋で、後ろ手に手錠をはめられ、椅子に縛り付けられた状態では時間の経過なんて分かるわけがない。
姉さんに閉じ込められてから、一体どれくらいの時間が経ったのだろうか……
ぎぃ……ぎぃ……
ゆっくりと階段を降りてくる足音が聞こえた。
俺は声を立てず、じっと身構えた。
俺は声を立てず、じっと身構えた。
ぎぃぃぃぃぃぃ……
錆ついた悲鳴を上げて、ドアが開く。
「くぅ……っ!」
階段の照明が暗闇に慣れた目に痛い。暖色の仄暗い電球の明かりが、まるで針のように俺の目を責め立てる。
「起きたかな? 起きる頃だと思ってたよ、稔くん」
部屋に入ってきたのは、姉さんだった。
逆光で顔は良く分からなかったが、あの声を俺が忘れるはずがない。
「ね……ねえさ……ん……」
痺れた舌で呼びかける。
そんな俺の姿を見て、姉さんは楽しげに微笑んだ。
「ねぇ、反省した?」
……何を、反省したというのだろう?
「な……ぁ……う……」
上手く言葉にならない。舌の痺れはますます強くなって、胸は締め付けられるように痛い。
バチン、という音がして地下室の電灯が点けられた。
階段よりも強く明るい照明に、俺は両目を強くつむった。
「……どうして目を閉じてるのかな?」
不愉快そうに姉さんが言った。
「どうして目を閉じているの? ひめのこと、見たくもないって言うの?」
「ぁ……う……あぁ……」
急に明るくするから目が痛いんだ――と言ってやりたいのに、舌はまともに動いてくれない。
姉さんの足音が近づいてくる。
一歩一歩、ゆっくりと。
「見なさい。稔くん、ひめのことを見て。お姉ちゃんを、見るの……っ!」
ぐいっ、と両手で頬を挟まれ、無理やり俺は顔を上げさせられた。
その強さは、姉さんの、あの白く細い両腕にこれほどの力があったのかと驚く程だった。
さらに姉さんは俺の閉じたまぶたを親指でこじ開けた。
「ひめを見て……稔くん……」
姉さんの顔が近い。
雪のように白く細い相貌には、慈しむような薄い微笑みが張り付いていた。
その微笑みは、ゆっくりと近づいてきて……俺の唇に触れた。
「ぅん……ちゅる……んん……っ」
痺れて動かない俺の舌を、門歯の間を滑り込んできた姉さんの舌が絡め取った。
ぞわぞわとした快感が俺の背骨を軋ませる。
とろとろに溶けた蜜のような姉の唾液が、くちゅりくちゅりと淫靡な音を立てて俺の喉へと流し込まれてゆく。
強く吸われて引きずり出された舌先に、姉さんの犬歯が甘く当てられる。動けないほど痺れているくせに、浴びせられる快感に俺の舌はビクっと震えた。
「んん…………ふぁ……んふぅ……」
姉さんの、柔らかな唇と舌による一方的な甘い陵辱が何分続けられたかは、よく分からない。
だが離れるとき、混ざり合ったお互いの唾液が糸となって、地下室の蛍光灯に照らされて銀に輝いていた。
「……勿体無いね、これ」
姉さんは自分の人差し指で唇の周りをぬぐい、指先についた汁気を丁寧に舌で舐め取り、
「ふふっ。稔くん分充填完了なのだ」
そう微笑んだ
「……ぁ……ぁぁ……」
……熱い。
全身が、悪い熱病にでもかかった様に熱くてたまらない。
心臓は今にも胸を突き破りそうな速さで鼓動し、酸素を求めて喉が擦れた音を立てる。
「どうしたのかな? 苦しいのかな、稔くんは?」
優しい笑顔のまま、姉さんは言った。
「でも、だめ。まだ、稔くんはひめだけを見てくれてないもの」
姉さんは俺から離れると、スカートのポケットから何かを取り出した。
「……これ、なんだか分かるよね?」
姉さんがポケットから出して俺に見せたのは――
「くぅ……っ!」
階段の照明が暗闇に慣れた目に痛い。暖色の仄暗い電球の明かりが、まるで針のように俺の目を責め立てる。
「起きたかな? 起きる頃だと思ってたよ、稔くん」
部屋に入ってきたのは、姉さんだった。
逆光で顔は良く分からなかったが、あの声を俺が忘れるはずがない。
「ね……ねえさ……ん……」
痺れた舌で呼びかける。
そんな俺の姿を見て、姉さんは楽しげに微笑んだ。
「ねぇ、反省した?」
……何を、反省したというのだろう?
「な……ぁ……う……」
上手く言葉にならない。舌の痺れはますます強くなって、胸は締め付けられるように痛い。
バチン、という音がして地下室の電灯が点けられた。
階段よりも強く明るい照明に、俺は両目を強くつむった。
「……どうして目を閉じてるのかな?」
不愉快そうに姉さんが言った。
「どうして目を閉じているの? ひめのこと、見たくもないって言うの?」
「ぁ……う……あぁ……」
急に明るくするから目が痛いんだ――と言ってやりたいのに、舌はまともに動いてくれない。
姉さんの足音が近づいてくる。
一歩一歩、ゆっくりと。
「見なさい。稔くん、ひめのことを見て。お姉ちゃんを、見るの……っ!」
ぐいっ、と両手で頬を挟まれ、無理やり俺は顔を上げさせられた。
その強さは、姉さんの、あの白く細い両腕にこれほどの力があったのかと驚く程だった。
さらに姉さんは俺の閉じたまぶたを親指でこじ開けた。
「ひめを見て……稔くん……」
姉さんの顔が近い。
雪のように白く細い相貌には、慈しむような薄い微笑みが張り付いていた。
その微笑みは、ゆっくりと近づいてきて……俺の唇に触れた。
「ぅん……ちゅる……んん……っ」
痺れて動かない俺の舌を、門歯の間を滑り込んできた姉さんの舌が絡め取った。
ぞわぞわとした快感が俺の背骨を軋ませる。
とろとろに溶けた蜜のような姉の唾液が、くちゅりくちゅりと淫靡な音を立てて俺の喉へと流し込まれてゆく。
強く吸われて引きずり出された舌先に、姉さんの犬歯が甘く当てられる。動けないほど痺れているくせに、浴びせられる快感に俺の舌はビクっと震えた。
「んん…………ふぁ……んふぅ……」
姉さんの、柔らかな唇と舌による一方的な甘い陵辱が何分続けられたかは、よく分からない。
だが離れるとき、混ざり合ったお互いの唾液が糸となって、地下室の蛍光灯に照らされて銀に輝いていた。
「……勿体無いね、これ」
姉さんは自分の人差し指で唇の周りをぬぐい、指先についた汁気を丁寧に舌で舐め取り、
「ふふっ。稔くん分充填完了なのだ」
そう微笑んだ
「……ぁ……ぁぁ……」
……熱い。
全身が、悪い熱病にでもかかった様に熱くてたまらない。
心臓は今にも胸を突き破りそうな速さで鼓動し、酸素を求めて喉が擦れた音を立てる。
「どうしたのかな? 苦しいのかな、稔くんは?」
優しい笑顔のまま、姉さんは言った。
「でも、だめ。まだ、稔くんはひめだけを見てくれてないもの」
姉さんは俺から離れると、スカートのポケットから何かを取り出した。
「……これ、なんだか分かるよね?」
姉さんがポケットから出して俺に見せたのは――
――――髪の毛だった。
「――っ!?」
全身の熱が一気に吹き飛んだ。
火照っていた身体は今や真逆の悪寒に支配されている。
舌の痺れは突き刺すような痛みに変わり、がちがちと歯の根が合わない。
……あれは、あの髪の毛は……
見覚えがあった。
いや、見覚えがあっちゃいけない。
あれは■■■の髪によく似ていて………………違うっ!
そんなわけがないっ!
姉さんが、血で汚れた■■■の髪の毛を持ってるなんておかしいじゃないか。
これが姉さんの悪質な冗談だと、俺は信じたかった。
そうだよ。いつだって俺やみんなを振り回してきたけど、姉さんは優しい人なんだ。
■■■を■■■するような、そんな酷いことするわけないじゃないっ!
……だが姉さんは俺の希望を打ち砕くかのごとく、
全身の熱が一気に吹き飛んだ。
火照っていた身体は今や真逆の悪寒に支配されている。
舌の痺れは突き刺すような痛みに変わり、がちがちと歯の根が合わない。
……あれは、あの髪の毛は……
見覚えがあった。
いや、見覚えがあっちゃいけない。
あれは■■■の髪によく似ていて………………違うっ!
そんなわけがないっ!
姉さんが、血で汚れた■■■の髪の毛を持ってるなんておかしいじゃないか。
これが姉さんの悪質な冗談だと、俺は信じたかった。
そうだよ。いつだって俺やみんなを振り回してきたけど、姉さんは優しい人なんだ。
■■■を■■■するような、そんな酷いことするわけないじゃないっ!
……だが姉さんは俺の希望を打ち砕くかのごとく、
「稔くん、分かるでしょ? これ、■■■、だよ」
三日月のように、唇を端を吊り上げて嗤った。
「ホント、嫌になるよね。あのオンナさ、稔くんに会わせろ会わせろってウルサイんだもん」
引きつった嗤いを、その白い貌に浮かべながら姉さんは続けた。
「終いには家の中に乗り込んでくるしねー……他人の家に図々しく上がりこんでくるなんて、一体どういう教育受けてたのかな? まあ、きっとロクなのじゃないよね」
……何を言ってるんだよ、姉さん?
目の前にいる姉さんは、俺の姉さんの顔で俺の知らない表情を見せた。
「でも良かった。稔くんが目を覚ます前に排除できて、本当に良かった。あんなオンナ、稔くんに会わせたら、また稔くんが毒されちゃうよ」
うっとりとして嬉しそうな顔。瞳は蕩け、恍惚にゆがんでいる。
だが、姉さんはその心地よさを振り払うかのように、頭を振った。
「ううん。もしかしたら、まだ毒されてるのかもしれない。だって稔くん、ひめのこと一番に見てくれなかったもん」
手にした髪を床に投げ捨て、姉さんは足で踏みにじった。
髪だと思っていたものが実はミミズだった、とでも言うように嫌悪感をあらわにして、姉さんは髪を踏み続ける。
「あんなオンナの色香に迷う稔くんにはお仕置きが必要だよね……」
姉さんの瞳に酷薄な光が宿るのを見た俺は、慌てて声を上げた。
「う……ぁ……ぅぁ…………ぁぁ……っ!」
……駄目だっ!
舌が言うことを聞いてくれない。言葉を発したいのに、姉さんをなだめたいのに俺の舌は痺れたままだった。
「稔くん、静かにしてなさい。近所迷惑になるでしょう」
焦る俺をあざ笑うように、姉さんは地下室の棚から靴箱のようなものを持ってきた。
フタを開けた姉さんは、俺の目の前に中身を取り出して見せた。
それは――昔、両親が購入して使わなくなった低周波マッサージ器だった。
「ふふ……これの電極を、目に当てたらどうなるか知ってるかなぁ? 理科の苦手な稔くんでも、最大で70V近い電流が眼球から視神経を伝わって脳に達したら、どうなっちゃうかぐらい想像できるよね?」
「あ……ぁ……ぁぅ……っ!!」
「視神経が焼き切れて失明しちゃうかもね……もしかしたら、最悪、脳が壊れちゃうかも」
「んんッ!! ん…………っ!! んぐ………………ッ!!!」
逃げないと――!!
身体をゆすり、どうにかこの縛めから逃れようともがくが、その度に手錠と手首が擦れて、鈍い痛みを俺に伝えてくる。
「だめだよ。逃げたら、稔くんのお仕置きにならないじゃない……」
姉さんは再び俺の頬を両手で挟んで固定すると、右のまぶたの上に唇を押し付けた。
「んっ……んぅ……じゅる……ちゅぱぁ……」
舌と唇でまぶたが嬲られる。眼球の表面を舌先が這いまわり、びちゃびちゃと唾液をまぶされてゆく。
愛撫の形をした陵辱だった。
「んっ……これぐらい濡らせば、電気も通りやすいよね……」
姉さんは片方の電極を俺の後頭部に押し当て、もう一方のコードを弄びながら、ゆっくり俺の右目へ近づけてくる。
「稔くんに目が二つあるからいけないんだ。二つもあるから、他の女に目が移るんだよ。一つだったら……ひめだけを見てくれるよね?」
「ぁ……ぁ……ぁぁ……ッ!」
や、やめろよ、姉さん。
じょ、冗談だろ?
こんなの、いつもの悪ふざけじゃないのかよ?
……嘘だ。
やめて……やめてよ、姉さんっ!
そんなものを近づけないで……やめろよ、やだよぉっ!
嫌だ、嫌だ、嫌だぁ――――――――――――っ!!!
「ホント、嫌になるよね。あのオンナさ、稔くんに会わせろ会わせろってウルサイんだもん」
引きつった嗤いを、その白い貌に浮かべながら姉さんは続けた。
「終いには家の中に乗り込んでくるしねー……他人の家に図々しく上がりこんでくるなんて、一体どういう教育受けてたのかな? まあ、きっとロクなのじゃないよね」
……何を言ってるんだよ、姉さん?
目の前にいる姉さんは、俺の姉さんの顔で俺の知らない表情を見せた。
「でも良かった。稔くんが目を覚ます前に排除できて、本当に良かった。あんなオンナ、稔くんに会わせたら、また稔くんが毒されちゃうよ」
うっとりとして嬉しそうな顔。瞳は蕩け、恍惚にゆがんでいる。
だが、姉さんはその心地よさを振り払うかのように、頭を振った。
「ううん。もしかしたら、まだ毒されてるのかもしれない。だって稔くん、ひめのこと一番に見てくれなかったもん」
手にした髪を床に投げ捨て、姉さんは足で踏みにじった。
髪だと思っていたものが実はミミズだった、とでも言うように嫌悪感をあらわにして、姉さんは髪を踏み続ける。
「あんなオンナの色香に迷う稔くんにはお仕置きが必要だよね……」
姉さんの瞳に酷薄な光が宿るのを見た俺は、慌てて声を上げた。
「う……ぁ……ぅぁ…………ぁぁ……っ!」
……駄目だっ!
舌が言うことを聞いてくれない。言葉を発したいのに、姉さんをなだめたいのに俺の舌は痺れたままだった。
「稔くん、静かにしてなさい。近所迷惑になるでしょう」
焦る俺をあざ笑うように、姉さんは地下室の棚から靴箱のようなものを持ってきた。
フタを開けた姉さんは、俺の目の前に中身を取り出して見せた。
それは――昔、両親が購入して使わなくなった低周波マッサージ器だった。
「ふふ……これの電極を、目に当てたらどうなるか知ってるかなぁ? 理科の苦手な稔くんでも、最大で70V近い電流が眼球から視神経を伝わって脳に達したら、どうなっちゃうかぐらい想像できるよね?」
「あ……ぁ……ぁぅ……っ!!」
「視神経が焼き切れて失明しちゃうかもね……もしかしたら、最悪、脳が壊れちゃうかも」
「んんッ!! ん…………っ!! んぐ………………ッ!!!」
逃げないと――!!
身体をゆすり、どうにかこの縛めから逃れようともがくが、その度に手錠と手首が擦れて、鈍い痛みを俺に伝えてくる。
「だめだよ。逃げたら、稔くんのお仕置きにならないじゃない……」
姉さんは再び俺の頬を両手で挟んで固定すると、右のまぶたの上に唇を押し付けた。
「んっ……んぅ……じゅる……ちゅぱぁ……」
舌と唇でまぶたが嬲られる。眼球の表面を舌先が這いまわり、びちゃびちゃと唾液をまぶされてゆく。
愛撫の形をした陵辱だった。
「んっ……これぐらい濡らせば、電気も通りやすいよね……」
姉さんは片方の電極を俺の後頭部に押し当て、もう一方のコードを弄びながら、ゆっくり俺の右目へ近づけてくる。
「稔くんに目が二つあるからいけないんだ。二つもあるから、他の女に目が移るんだよ。一つだったら……ひめだけを見てくれるよね?」
「ぁ……ぁ……ぁぁ……ッ!」
や、やめろよ、姉さん。
じょ、冗談だろ?
こんなの、いつもの悪ふざけじゃないのかよ?
……嘘だ。
やめて……やめてよ、姉さんっ!
そんなものを近づけないで……やめろよ、やだよぉっ!
嫌だ、嫌だ、嫌だぁ――――――――――――っ!!!
「すいっち、お~ん☆」
バチンッ、という何か破滅的な音と衝撃に俺の脳みそは揺さぶられ……
俺は、意識を、手放した――
俺は、意識を、手放した――
DEADEND