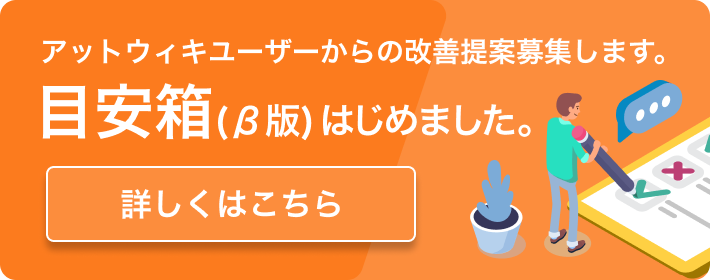追記、修正をかけた本編組み込みver.ではありません
タイムカプセルep 原文
車輪は回る。くるくる回る。みずきの押すマウンテンバイクの車輪だ。
俺たちは商店街を抜け、住宅地に入っていた。ここを抜ければすぐにでもみずきの家だ。
だが、その先頭を行く少女はこちらを振り向かない。
みずきは、俺たちの数歩前を無言で行く。あの活発なみずきがさっきから黙ったままだった。
俺は隣を歩く伊万里にそっと聞いてみた。
「なぁ、伊万里……みずきのやつ、いったいどうしたんだ? お前、なんか心当たりないか?」
「あ、あるわけないよ! ……ボクだってあんなみずきちを見たのはじめてだよ……」
こそこそと小声で話す俺たち。伊万里もみずきのあまりの消沈っぷりにどう接していいのかわからないらしい。
「みのりんこそ、なんか言っちゃいけないこと言っちゃったんじゃないの? そもそも今日はどういう話だったのさ?」
「どうもこうもない。みずきが家にゲームしに来ないかって言ったからお前も呼んだだけだ」
「そっかぁ……、むーん……むーん……」
いきなり、伊万里は頭を抱えて何かを考えだした。
「なんだよ。やっぱり心あたりあるのか」
「うーん……なんか引っかかる気がするんだけど……みのりんもうちょっと待っててね」
そしてそのまま数瞬考える。考えた後、笑顔で顔を上げた。
「何か浮かんだか?」
「全然! ……っひゃん!」
俺はすぐさま伊万里の額に必殺のデコピンを見舞った。
「ひ、ひどいよ! みのりん! ボクのおでこはそんなに何度も弾いていい所じゃないよ!?」
「うるさい」
「あうっ! ま、また弾いたぁ!」
まったくこの馬鹿は……。
向こうが黙っているなら、こっちからアクションを起こすしかないだろう。
とりあえず、まずは当たり障りのない話題から始めることにしよう。
「あー、そういえばあれだ、伊万里。あれ、面白かったよな? ほらこないだ姉さんがさ――」
「……え!? あ、うん。そうだね!」
「だよなー! いくら弟に指摘されたからって、あの狼狽っぷりはないよなー!」
「そうだよね! あれはないない! でもかわいかったよねーって……」
いつの間にか、みずきがこちらを向いていた。
「もうすぐ、家だよっ!」
「お、おう」
振り向いたみずきはいつも通りのみずきで、少し拍子抜けしてしまう。
なんだ、機嫌が悪いと思ったのは、気のせいだったのか……。
「伊万里」
「え、どうしたのみのりん。――あうん! ま、またやったぁ! 今日だけでもう四回目だよ!?」
「うるさい。全部お前のせいだ」
「ひ、ひどいよぉ」
全ての責任を伊万里に転嫁して八つ当たりする。まったく、余計な気を揉ませやがって……。
「こらっ! みのる、伊万里をいじめちゃだめ」
「苛めてない。愛情ゆえのスキンシップだ」
「あ、愛情!?」
伊万里が大げさに驚く。頬染めんな、寿司のくせに。
「おおーい。みずきちゃん」
そこで、声をかけられた。気がつくと俺たちは、みずきの家のそばにある木工場の前まで来ていた。
「あ、玄さん! お疲れ様っ」
みずきが笑顔で手を振る。
声をかけたのは、良く日に焼けた壮年の職人さんだった。玄さんと呼ばれたその人は笑顔でこちらに近づいてくる。
みずきの実家は木工所も経営している。きっと、ここがそうなのだろう。大きな倉庫のような場所に、沢山の材木が並べられていた。
木を切る電気のこぎりの音が聞こえる。腕利きの職人がかけるかんなの滑る音が聞こえる。舞い散るかんな屑。木工所内は活気に満ち溢れていた。
「おや、お嬢。いま帰りですかい」
そして職人さんがもう一人。首にかけたタオルで汗を拭きながら現れた。
「こんにちわ、鈴木さん。作業はかどってる?」
「はぁ、もちろんでさぁ。お嬢の為なら、わしら何でもしますからな」
「あはは、もう、調子いいねっ。……何か問題とかない? あったら何でも言ってね」
「日々順風満帆ですよ。あったとしても、とてもみずき嬢ちゃんには言えませんよ」
「そうそう、お嬢に相談なんかしたら、わしらの仕事全部取られちまいますからな」
「そりゃそうだ。それに何より、嬢ちゃんに怪我させたとあっちゃ、わしら親方に申し訳がたちませんわ」
「そんな事、気にしなくてもいいのにー」
みずきが親しげに数人の職人さんと会話をしている。職人さんたちの表情はみんな穏やかで、みずきは愛されているのだと感じた。
「みずきち、楽しそうだね」
伊万里が言う。
「そうだな」
俺たちは少し離れたところからそれを眺めていた。
俺は安心した。みずきはお人よしのおせっかい焼きだ。頼まれるとなんでも引き受けてしまう。
それゆえに危うい所があるのだが、この木工所の人たちはそんなみずきの性質をしっかり理解しているようだった。
「お待たせっ! それじゃあ、行こっか」
みずきがツインテールをはためかせて戻ってくる。
いつの間にか職人さんたちはそれぞれの仕事に戻っていた。
「みずきは木工所の人たちと仲がいいんだな」
俺は何気なく聞いてみた。
「そうだよ。子供の頃からよく見に行ってたからね」
みずきは無邪気に笑う。その笑顔に一切含むところは無い。心からこちらを信じきっているからこそ出来る表情だ。
「じゃあ、みずきちもあんなふうにがーって豪快に木を切ったりできるんだ」
伊万里も乗ってくる。大仰な身振りで真似る。
視線の先には、先ほど玄さんと呼ばれた職人さんが一抱えもある電気のこぎりで材木を切断しているところだった。
「もちろん! 一通りの作業出来るよ。こんど伊万里にも見せてあげる」
「……えっ。あ、うん、今度ね」
伊万里がしまったという顔をする。険しくなる眉間。この馬鹿……。
「おい、伊万里」
「わかってるよぅ……失言したんだよぅ」
まったく、みずきの性格を考えてものを喋れってんだ。
みずきにそんなことを言ったら、たとえ不慣れでも無理して見せようとするに違いない。それで怪我でもさせたら大変だろう。
みずきは優しい。どんな時でも自分より他人を優先する。人の為になら、自分を省みない。故に、危うい。
俺と伊万里はあの事故からそれを学んだはずだ。
だから、俺たちはみずきの身を案ずる。ここの人たちはそれを知っている。
けれど、学校でみずきの危うさを知っているやつは少ないのだ。
みずきは、俺たちが守らないと……。
俺たちは商店街を抜け、住宅地に入っていた。ここを抜ければすぐにでもみずきの家だ。
だが、その先頭を行く少女はこちらを振り向かない。
みずきは、俺たちの数歩前を無言で行く。あの活発なみずきがさっきから黙ったままだった。
俺は隣を歩く伊万里にそっと聞いてみた。
「なぁ、伊万里……みずきのやつ、いったいどうしたんだ? お前、なんか心当たりないか?」
「あ、あるわけないよ! ……ボクだってあんなみずきちを見たのはじめてだよ……」
こそこそと小声で話す俺たち。伊万里もみずきのあまりの消沈っぷりにどう接していいのかわからないらしい。
「みのりんこそ、なんか言っちゃいけないこと言っちゃったんじゃないの? そもそも今日はどういう話だったのさ?」
「どうもこうもない。みずきが家にゲームしに来ないかって言ったからお前も呼んだだけだ」
「そっかぁ……、むーん……むーん……」
いきなり、伊万里は頭を抱えて何かを考えだした。
「なんだよ。やっぱり心あたりあるのか」
「うーん……なんか引っかかる気がするんだけど……みのりんもうちょっと待っててね」
そしてそのまま数瞬考える。考えた後、笑顔で顔を上げた。
「何か浮かんだか?」
「全然! ……っひゃん!」
俺はすぐさま伊万里の額に必殺のデコピンを見舞った。
「ひ、ひどいよ! みのりん! ボクのおでこはそんなに何度も弾いていい所じゃないよ!?」
「うるさい」
「あうっ! ま、また弾いたぁ!」
まったくこの馬鹿は……。
向こうが黙っているなら、こっちからアクションを起こすしかないだろう。
とりあえず、まずは当たり障りのない話題から始めることにしよう。
「あー、そういえばあれだ、伊万里。あれ、面白かったよな? ほらこないだ姉さんがさ――」
「……え!? あ、うん。そうだね!」
「だよなー! いくら弟に指摘されたからって、あの狼狽っぷりはないよなー!」
「そうだよね! あれはないない! でもかわいかったよねーって……」
いつの間にか、みずきがこちらを向いていた。
「もうすぐ、家だよっ!」
「お、おう」
振り向いたみずきはいつも通りのみずきで、少し拍子抜けしてしまう。
なんだ、機嫌が悪いと思ったのは、気のせいだったのか……。
「伊万里」
「え、どうしたのみのりん。――あうん! ま、またやったぁ! 今日だけでもう四回目だよ!?」
「うるさい。全部お前のせいだ」
「ひ、ひどいよぉ」
全ての責任を伊万里に転嫁して八つ当たりする。まったく、余計な気を揉ませやがって……。
「こらっ! みのる、伊万里をいじめちゃだめ」
「苛めてない。愛情ゆえのスキンシップだ」
「あ、愛情!?」
伊万里が大げさに驚く。頬染めんな、寿司のくせに。
「おおーい。みずきちゃん」
そこで、声をかけられた。気がつくと俺たちは、みずきの家のそばにある木工場の前まで来ていた。
「あ、玄さん! お疲れ様っ」
みずきが笑顔で手を振る。
声をかけたのは、良く日に焼けた壮年の職人さんだった。玄さんと呼ばれたその人は笑顔でこちらに近づいてくる。
みずきの実家は木工所も経営している。きっと、ここがそうなのだろう。大きな倉庫のような場所に、沢山の材木が並べられていた。
木を切る電気のこぎりの音が聞こえる。腕利きの職人がかけるかんなの滑る音が聞こえる。舞い散るかんな屑。木工所内は活気に満ち溢れていた。
「おや、お嬢。いま帰りですかい」
そして職人さんがもう一人。首にかけたタオルで汗を拭きながら現れた。
「こんにちわ、鈴木さん。作業はかどってる?」
「はぁ、もちろんでさぁ。お嬢の為なら、わしら何でもしますからな」
「あはは、もう、調子いいねっ。……何か問題とかない? あったら何でも言ってね」
「日々順風満帆ですよ。あったとしても、とてもみずき嬢ちゃんには言えませんよ」
「そうそう、お嬢に相談なんかしたら、わしらの仕事全部取られちまいますからな」
「そりゃそうだ。それに何より、嬢ちゃんに怪我させたとあっちゃ、わしら親方に申し訳がたちませんわ」
「そんな事、気にしなくてもいいのにー」
みずきが親しげに数人の職人さんと会話をしている。職人さんたちの表情はみんな穏やかで、みずきは愛されているのだと感じた。
「みずきち、楽しそうだね」
伊万里が言う。
「そうだな」
俺たちは少し離れたところからそれを眺めていた。
俺は安心した。みずきはお人よしのおせっかい焼きだ。頼まれるとなんでも引き受けてしまう。
それゆえに危うい所があるのだが、この木工所の人たちはそんなみずきの性質をしっかり理解しているようだった。
「お待たせっ! それじゃあ、行こっか」
みずきがツインテールをはためかせて戻ってくる。
いつの間にか職人さんたちはそれぞれの仕事に戻っていた。
「みずきは木工所の人たちと仲がいいんだな」
俺は何気なく聞いてみた。
「そうだよ。子供の頃からよく見に行ってたからね」
みずきは無邪気に笑う。その笑顔に一切含むところは無い。心からこちらを信じきっているからこそ出来る表情だ。
「じゃあ、みずきちもあんなふうにがーって豪快に木を切ったりできるんだ」
伊万里も乗ってくる。大仰な身振りで真似る。
視線の先には、先ほど玄さんと呼ばれた職人さんが一抱えもある電気のこぎりで材木を切断しているところだった。
「もちろん! 一通りの作業出来るよ。こんど伊万里にも見せてあげる」
「……えっ。あ、うん、今度ね」
伊万里がしまったという顔をする。険しくなる眉間。この馬鹿……。
「おい、伊万里」
「わかってるよぅ……失言したんだよぅ」
まったく、みずきの性格を考えてものを喋れってんだ。
みずきにそんなことを言ったら、たとえ不慣れでも無理して見せようとするに違いない。それで怪我でもさせたら大変だろう。
みずきは優しい。どんな時でも自分より他人を優先する。人の為になら、自分を省みない。故に、危うい。
俺と伊万里はあの事故からそれを学んだはずだ。
だから、俺たちはみずきの身を案ずる。ここの人たちはそれを知っている。
けれど、学校でみずきの危うさを知っているやつは少ないのだ。
みずきは、俺たちが守らないと……。
不意にどこからか携帯のバイブが聞こえた。反射的にポケットの携帯を探る。
……違った。姉さんからでもかかってきたのかと思ったがどうやらそういう訳では無いらしい。
見ると、みずきでもないらしい。ふるふると首を振る。ツインテールがそれにあわせて揺れた。
「あれ……じゃ、ボクの携帯かな?」
伊万里が怪訝な顔をしてカバンを漁り始める。その間にも振動音は鳴り続ける。
カバンの底から発掘された携帯は、はたしてその音の発生源だった。
「うー……あーんー」
携帯の画面を確認し、唸り声をあげる伊万里。
「ううう~~~」
そして、急に涙を流しはじめた。なんだなんだ? どうしたんだ、いったい。
「どうした伊万里」
「うー……」
伊万里は言いよどむ。なんだ? 何かやましい事でもあるのだろうか?
「んー? どうしたの? 伊万里」
みずきも疑問に感じたのか、伊万里の顔を下から覗き込む。
「う~、みのり~ん! 遊びにいけなくなっちゃたかも~!」
……違った。姉さんからでもかかってきたのかと思ったがどうやらそういう訳では無いらしい。
見ると、みずきでもないらしい。ふるふると首を振る。ツインテールがそれにあわせて揺れた。
「あれ……じゃ、ボクの携帯かな?」
伊万里が怪訝な顔をしてカバンを漁り始める。その間にも振動音は鳴り続ける。
カバンの底から発掘された携帯は、はたしてその音の発生源だった。
「うー……あーんー」
携帯の画面を確認し、唸り声をあげる伊万里。
「ううう~~~」
そして、急に涙を流しはじめた。なんだなんだ? どうしたんだ、いったい。
「どうした伊万里」
「うー……」
伊万里は言いよどむ。なんだ? 何かやましい事でもあるのだろうか?
「んー? どうしたの? 伊万里」
みずきも疑問に感じたのか、伊万里の顔を下から覗き込む。
「う~、みのり~ん! 遊びにいけなくなっちゃたかも~!」
◇◆◇◆◇
「伊万里、残念だったねっ!」
台詞とは裏腹に、みずきの声は弾んでいた。
俺たちは如月家の所有する山の中を進んでいた。目的地はわからない。みずきだけが知っている。
二月の山はとても冷えて寒かったけれど、首に巻かれたマフラーが風を阻んでくれた。
「でもちょうど良かったよね。結局ゲームはできなかったんだし」
そのマフラーは俺の首を包み込み、そのまま隣をいくみずきの首筋に巻きついている。
両手はそのマフラーの端を大切そうに握り締めている。顔には満面の笑みが浮かんでいた。
「みのる、寒い?」
俺が無言でいることを怪訝に思ったのか、みずきが聞いてくる。いや、そうじゃないんだが……。
「なぁ、なんで俺たちはこんな恋人同士みたいなことしてるんだ?」
みずきは数瞬考えていたようだが、少し困ったような笑顔で聞いてくる。
「みのるは……嫌?」
「いや……」
確かに恥ずかしい。だが、別に誰かが見ているわけではない。ここは人気の無い山の中で、みずきと俺の二人しかいないのだ。
ここに伊万里や、姉さん。それに毒男や長岡でもいようものなら全力で逃げ出すところだが、幸いにして本当に二人きりだ。
そう、二人きり――。
「嫌なわけじゃないんだが、ちょっとはずかし――」
「じゃあ気にしないっ!」
みずきはそう言って笑った。
本当に上機嫌らしく、ツインテールがぴょこぴょこ跳ねている。本当にウサギの耳のようだと思う。
台詞とは裏腹に、みずきの声は弾んでいた。
俺たちは如月家の所有する山の中を進んでいた。目的地はわからない。みずきだけが知っている。
二月の山はとても冷えて寒かったけれど、首に巻かれたマフラーが風を阻んでくれた。
「でもちょうど良かったよね。結局ゲームはできなかったんだし」
そのマフラーは俺の首を包み込み、そのまま隣をいくみずきの首筋に巻きついている。
両手はそのマフラーの端を大切そうに握り締めている。顔には満面の笑みが浮かんでいた。
「みのる、寒い?」
俺が無言でいることを怪訝に思ったのか、みずきが聞いてくる。いや、そうじゃないんだが……。
「なぁ、なんで俺たちはこんな恋人同士みたいなことしてるんだ?」
みずきは数瞬考えていたようだが、少し困ったような笑顔で聞いてくる。
「みのるは……嫌?」
「いや……」
確かに恥ずかしい。だが、別に誰かが見ているわけではない。ここは人気の無い山の中で、みずきと俺の二人しかいないのだ。
ここに伊万里や、姉さん。それに毒男や長岡でもいようものなら全力で逃げ出すところだが、幸いにして本当に二人きりだ。
そう、二人きり――。
「嫌なわけじゃないんだが、ちょっとはずかし――」
「じゃあ気にしないっ!」
みずきはそう言って笑った。
本当に上機嫌らしく、ツインテールがぴょこぴょこ跳ねている。本当にウサギの耳のようだと思う。
伊万里にかかって来た電話は母親からだったらしく、どうしても手伝って欲しい用事が出来たから至急帰ってこいというものだった。
すぐに家にかけ直した伊万里だったが、抵抗の甲斐なく『ボクもみのりんと遊びたかったよ~~』という叫びを残しながら、後ろ髪を引かれまくりで帰っていった。
そしてその後、みずきの家へ向かおうとした俺たちを「おおーい、お嬢」と、先ほど鈴木さんと呼ばれていた人が呼び止めた。
そういえば、とこちらへやって来た彼が言うには、今日はどうやら地元の名士同士の会合がみずきの家であるらしい。
「あー、それじゃあ無理だねー」
みずきは困ったという顔をしながら言った。
「そんなに凄いものなのか?」
「家の前に黒塗りの車がたくさん止まってたり、私もよく知らない大人たちが大勢いてね、とてもじゃないけどお邪魔できる雰囲気じゃないと思うよ」
「黒塗りの車……もしかして田舎のお金持ちって、ヤクザのお偉いさんとあんまり変わんないじゃないか?」
「うーん、そうかもね。少なくとも車の趣味は似てるんじゃない?」
そう言って苦笑いした後、今度はにっこり笑って目の前の職人にお礼を言う。
「うん。ありがとうね、鈴木さん!」
「いやいや、礼を言われるほどのもんでもないでさぁ。にしても、お嬢。隣の兄ちゃんが例の――」
「うん、みのる」
「へぇ、君が稔君かぁ」
鈴木さんが品定めでもするかのように、上から下へ下から上へと俺を見る。
こういう風に見られることは正直気分のいいものではない。
「あの、何か……?」
「ああ、いや、すまんねぇ。噂の稔君がどんな色男かと思ってねぇ」
「い、色男なんてとんでもないです……」
「いやいや、お嬢が君の話をよくするもんでね。今日のみのるはこうだった、ああだったってね」
「はぁ」
「あんまり楽しそうに話すから一部では――」
「すーずーきーさーん!」
唐突に、大声を上げてみずきが会話をさえぎる。
「おっと、こりゃいけねぇ。ははは、それじゃあ邪魔なおっさんは戻りますかな」
豪快に笑って鈴木さんは木工所の方へと踵を返す。そうして去り際に、
「稔君、お嬢を頼んだよ」
と、俺にしか聞こえないような小声で言い残していった。
「もう。鈴木さんってね、ああやっていつもあたしのこと――」
そうやって文句をたれるみずきの顔は穏やかで、どこか楽しげで、本当に優しい人たちに囲まれているのだと実感した。
しかしそれもつかの間、みずきの家へ行くことができなくなったため、どうしたものかと思案しなければならない俺たち。
みずきも良いアイディアがすぐには思い浮かばないようで、しばらく二人で突っ立って考えをめぐらす。
やはり少し時間はかかるが、街にでも行ってゲームセンターにでも行くしかないのだろうか。
あまり良い案ではないが、そう提案しようと口を開こうとした瞬間、パッと顔を上げたみずきが言い放った言葉が――。
「じゃあさ、みのる、裏山にいってみようよ!」
であった。
すぐに家にかけ直した伊万里だったが、抵抗の甲斐なく『ボクもみのりんと遊びたかったよ~~』という叫びを残しながら、後ろ髪を引かれまくりで帰っていった。
そしてその後、みずきの家へ向かおうとした俺たちを「おおーい、お嬢」と、先ほど鈴木さんと呼ばれていた人が呼び止めた。
そういえば、とこちらへやって来た彼が言うには、今日はどうやら地元の名士同士の会合がみずきの家であるらしい。
「あー、それじゃあ無理だねー」
みずきは困ったという顔をしながら言った。
「そんなに凄いものなのか?」
「家の前に黒塗りの車がたくさん止まってたり、私もよく知らない大人たちが大勢いてね、とてもじゃないけどお邪魔できる雰囲気じゃないと思うよ」
「黒塗りの車……もしかして田舎のお金持ちって、ヤクザのお偉いさんとあんまり変わんないじゃないか?」
「うーん、そうかもね。少なくとも車の趣味は似てるんじゃない?」
そう言って苦笑いした後、今度はにっこり笑って目の前の職人にお礼を言う。
「うん。ありがとうね、鈴木さん!」
「いやいや、礼を言われるほどのもんでもないでさぁ。にしても、お嬢。隣の兄ちゃんが例の――」
「うん、みのる」
「へぇ、君が稔君かぁ」
鈴木さんが品定めでもするかのように、上から下へ下から上へと俺を見る。
こういう風に見られることは正直気分のいいものではない。
「あの、何か……?」
「ああ、いや、すまんねぇ。噂の稔君がどんな色男かと思ってねぇ」
「い、色男なんてとんでもないです……」
「いやいや、お嬢が君の話をよくするもんでね。今日のみのるはこうだった、ああだったってね」
「はぁ」
「あんまり楽しそうに話すから一部では――」
「すーずーきーさーん!」
唐突に、大声を上げてみずきが会話をさえぎる。
「おっと、こりゃいけねぇ。ははは、それじゃあ邪魔なおっさんは戻りますかな」
豪快に笑って鈴木さんは木工所の方へと踵を返す。そうして去り際に、
「稔君、お嬢を頼んだよ」
と、俺にしか聞こえないような小声で言い残していった。
「もう。鈴木さんってね、ああやっていつもあたしのこと――」
そうやって文句をたれるみずきの顔は穏やかで、どこか楽しげで、本当に優しい人たちに囲まれているのだと実感した。
しかしそれもつかの間、みずきの家へ行くことができなくなったため、どうしたものかと思案しなければならない俺たち。
みずきも良いアイディアがすぐには思い浮かばないようで、しばらく二人で突っ立って考えをめぐらす。
やはり少し時間はかかるが、街にでも行ってゲームセンターにでも行くしかないのだろうか。
あまり良い案ではないが、そう提案しようと口を開こうとした瞬間、パッと顔を上げたみずきが言い放った言葉が――。
「じゃあさ、みのる、裏山にいってみようよ!」
であった。
「みのる、マフラー暖かい?」
「ああ、暖かいよ」
「よかった。長いの買った甲斐があったね」
「……しかし、みずき。いきなり山に行こうだなんてどうしたんだよ。ここに何かあるのか?」
俺は少しばかり呆れ気味に聞く。
ざく、ざく、ざく
山の景色は無味乾燥としていて、葉っぱ一枚残らない裸の木が目立つ。二人分の土を踏みしめる足音だけが聞こえる。
寒風吹き荒む景色に、曇天の空はどこか物悲しげだ。いったいこんな寂しい場所に何があるというのだろう。
俺にはわからない。
「あれ? みのるは覚えてない?」
「何のことだよ」
「みのるは何度かここに来たことあるよ?」
「そうだったかな。覚えてないけど」
「もうすぐすれば、みのるも思い出すっ」
俺たちは荒れ果てた山道を登る。みずきのマフラーで俺たちは繋がっていた。だから二人ぴったりと並んで歩いた。
すこし開けた場所に出る。そこは森の境目で、ずいぶん長く放置されたのだろうか、変色した材木が積んである切り出し場の入り口だった。
材木の隣には小さな小屋が立っている。昔、ここが使われていた時の作業小屋だ。
「ここは……」
「みのる、思い出した?」
「ああ、そうだ。ここは確か……」
そうだ、ここは確かに何度か来たことがある。
それは、まだ俺たちが子供の頃の記憶。
まだ内気で人見知りだったみずきが初めて俺を遊びに誘い、今のように二人だけで訪れた思い出の場所……。
いつの間にか姉さんと伊万里が加わり、4人の秘密基地みたいになってたっけ。
「そうか。タイムカプセルか」
「あったり!」
ぴょこん、とウサギの耳が跳ねる。
するするとマフラーを解くと、みずきはそれを俺に押し付け「ちょっと待ってて」という言葉を残して走っていく。
走っていく先は、うら寂れた小屋。
みずきは小屋の扉の前まで行くと、しばらくガチャガチャと物音をたて、そして扉を開き、中に入っていった。
おそらく、家に寄ったときにでも鍵を預かってきたのだろう。
俺はそれを見送ると周りの風景に目を移した。
まぶたを閉じれば思い出す。これもまた小学生のころ。
俺とみずきは、それぞれ自分の宝物を持ち寄って、大きめのクッキー缶に入れてタイムカプセルとしてこの場所に埋めたのだ。
どちらが言い出した事かは忘れてしまった。忘れてしまったけれど、いつか大人になった時にそれを二人で掘り出しに来ようと誓ったのだ。
そうだ、確か埋めた場所は……。
「みのるー、ほらスコップ!」
『小屋、大きい木、そこから五歩、珍しい石』頭の中でリフレインする言葉。その言葉どおりに歩く。場所はすぐに見つかった。
小屋から数歩も離れていない。ただ、目印の大きな木は大きな切り株になっていたし、当時珍しい石だと思っていた岩も、いま見ればどうということもない変哲もない形をしていた。
「……子供の頃の記憶って、変わっちゃうものだね」
帰ってきたみずきが言う。
まったくだ。あの頃と俺たちの関係は何も変わっちゃいないのに、周りばかりがどんどん変わっていく。
「じゃ、日が暮れて寒くならないうちに掘り出しちゃおうよ」
「ああ、そうだな」
「おっけー、おっけー! 穴掘りはあたしにまっかせなさい!」
おなじみの台詞を口にすると、みずきは勢いよく、スコップを地面に突き立てた。
「ああ、暖かいよ」
「よかった。長いの買った甲斐があったね」
「……しかし、みずき。いきなり山に行こうだなんてどうしたんだよ。ここに何かあるのか?」
俺は少しばかり呆れ気味に聞く。
ざく、ざく、ざく
山の景色は無味乾燥としていて、葉っぱ一枚残らない裸の木が目立つ。二人分の土を踏みしめる足音だけが聞こえる。
寒風吹き荒む景色に、曇天の空はどこか物悲しげだ。いったいこんな寂しい場所に何があるというのだろう。
俺にはわからない。
「あれ? みのるは覚えてない?」
「何のことだよ」
「みのるは何度かここに来たことあるよ?」
「そうだったかな。覚えてないけど」
「もうすぐすれば、みのるも思い出すっ」
俺たちは荒れ果てた山道を登る。みずきのマフラーで俺たちは繋がっていた。だから二人ぴったりと並んで歩いた。
すこし開けた場所に出る。そこは森の境目で、ずいぶん長く放置されたのだろうか、変色した材木が積んである切り出し場の入り口だった。
材木の隣には小さな小屋が立っている。昔、ここが使われていた時の作業小屋だ。
「ここは……」
「みのる、思い出した?」
「ああ、そうだ。ここは確か……」
そうだ、ここは確かに何度か来たことがある。
それは、まだ俺たちが子供の頃の記憶。
まだ内気で人見知りだったみずきが初めて俺を遊びに誘い、今のように二人だけで訪れた思い出の場所……。
いつの間にか姉さんと伊万里が加わり、4人の秘密基地みたいになってたっけ。
「そうか。タイムカプセルか」
「あったり!」
ぴょこん、とウサギの耳が跳ねる。
するするとマフラーを解くと、みずきはそれを俺に押し付け「ちょっと待ってて」という言葉を残して走っていく。
走っていく先は、うら寂れた小屋。
みずきは小屋の扉の前まで行くと、しばらくガチャガチャと物音をたて、そして扉を開き、中に入っていった。
おそらく、家に寄ったときにでも鍵を預かってきたのだろう。
俺はそれを見送ると周りの風景に目を移した。
まぶたを閉じれば思い出す。これもまた小学生のころ。
俺とみずきは、それぞれ自分の宝物を持ち寄って、大きめのクッキー缶に入れてタイムカプセルとしてこの場所に埋めたのだ。
どちらが言い出した事かは忘れてしまった。忘れてしまったけれど、いつか大人になった時にそれを二人で掘り出しに来ようと誓ったのだ。
そうだ、確か埋めた場所は……。
「みのるー、ほらスコップ!」
『小屋、大きい木、そこから五歩、珍しい石』頭の中でリフレインする言葉。その言葉どおりに歩く。場所はすぐに見つかった。
小屋から数歩も離れていない。ただ、目印の大きな木は大きな切り株になっていたし、当時珍しい石だと思っていた岩も、いま見ればどうということもない変哲もない形をしていた。
「……子供の頃の記憶って、変わっちゃうものだね」
帰ってきたみずきが言う。
まったくだ。あの頃と俺たちの関係は何も変わっちゃいないのに、周りばかりがどんどん変わっていく。
「じゃ、日が暮れて寒くならないうちに掘り出しちゃおうよ」
「ああ、そうだな」
「おっけー、おっけー! 穴掘りはあたしにまっかせなさい!」
おなじみの台詞を口にすると、みずきは勢いよく、スコップを地面に突き立てた。
◇◆◇◆◇
「ふう、結構簡単に出てきたね」
「そうだな、子供の力だからな。そんなに深くまでは埋めれなかったんだろうな」
掘り出したそれは、やはり記憶とは微妙に違う小さな金属の缶だった。縁が微妙に錆びている。こんな薄っぺらな入れ物でよく今まで無事に埋まっていられたものだ。素直にそう思った。
「これはこのまま持ってて、小屋の中で開けようぜ」
二月という冬場でも運動をすれば少しは汗もかく。自分はともかくとして、このままここに居ればみずきが風邪を引きかねない。
それに、俺が風邪を引いたって、どうせみずきは世話を焼きに家までくるだろう。そこでうつしてしまっては元も子もない。
「そうだね……あ、でも」
素直にうなずくかと思ったみずきは少し悪戯っぽく笑って、踵を返した。
「みのる。ちょ~っとだけ、そこで待ってて」
そしてそのまま小屋まで駆けていくと、一抱えもあるやたら物騒な代物を抱えて帰ってきた。
「はい、みのるこれ持つ! 危ないから落としちゃダメだよ」
「お、おまえこれって……」
どしり、と確かな重量が両手にのしかかる。それは作業用の機械のようだった。
ただの機械じゃない。仄かに香るガソリンと、オイルのにおい。錆びた鉄。エンジンがついていた。
そしてそこからにょっきりと生えた剣呑で、黒光りするブレード――。
こ、これは……。
「チェ、チェーンソーじゃないか! なにすんだよ、こんなもん持ってきて!」
「みのるにあたしの特技見せてあげるっ!」
「と、特技ってお前……」
みずきは手早く、やたら厚手で丈夫そうなエプロンをかけ、手袋とゴーグルを装着した。
そして、材木置き場の方へ行くと、少し大きめの丸太を転がしてくる。それを手ごろな切り株の上に乗せた。
「本当は音がすごいからイヤープロテクターもつけなきゃいけないんだけど、今日は持ってきてないから」
みずきは俺からチェーンソーを受け取る。
「なんか……すげー格好だな」
俺は困惑していた。急にそんなものを持ち出したみずきの考えがわからなかった。
「大丈夫、大丈夫。あたしに任せておきなさいっ!」
そんな俺を無視して、みずきは得意そうに笑う。
「危ないから、みのるは離れててね」
そういって、エンジンスタータを一気に引っ張る。
どるんっ
低い音が鳴る。それに続き、ドッドッドッドという断続的なエンジン音が山間に響く。
「何するつもりなんだ?」
「えへへー、ひみつ~。みのる、しっかり見ててねっ」
みずきはそう宣誓するや否や、エンジンの回転をブレードに伝えるスイッチを入れた。
ギュアアアアアアァン
瞬間、悲鳴のような轟音が場を満たす。みずきの操る高速で回転するブレードが丸太の端に触れた時、その音はひと際高まった。
接地点が木屑で霞む。みずきはぐっと踏み込むと、押し返されないように力を込めた。
そしてそのまま、振りぬく。ぽーんと、切断された木片が飛んでいった。
みずきはブレードを器用に操り、丸太を寸断していく。さらに破片が飛び、粉が舞う。
その中でみずきは楽しそうにブレードを振り続けた。俺はそれを見て、まるで踊っているようだと感じる。
みずきが右にブレードを振れば、頂上部の出っ張りがあっさりと落ちる。みずきが左にブレードを捻れば、中ほどに大きな裂け目が生じた。
そして、見ているうちに、丸太が何がしかの形を取りはじめる。
最初に大まかに粗が落とされ、饅頭のような概観が見えてきた。次に、ブレードの先端を薄くあて、線が入れられる。
それに沿って、薄く表面を撫で削っていく。
いつの間にか、丸太は台座の上に座った立派なウサギの彫刻にかわっていた。
「よし、出来上がり!」
ぐいっと、ゴーグルをあげたみずきの頬には汗がにじんでいた。
「こ、これは……」
「すごいでしょ! チェーンソーカービングっていうの。チェーンソーを使って彫り物をするスポーツなんだけど、あたし最年少で大会だって出たことあるんだよ」
「た、確かに……これはすごいな」
本当にあっという間のことだった。時間にしても二十分もかかっていないだろう。その間にみずきはこのウサギの像を作り上げてしまった。
「でしょ? 家にある椅子だってあたしが作ったんだから」
そう胸を突き出すみずきは誇らしげだ。
「お前、昔からこんな事を?」
「そうだよ。木工所のみんなにだって、チェーンソーの取り扱いなら負けないの。新しく入ってきた人に教えてあげる事だってあるんだから」
俺はあっけに取られる。こいつ、こんな危ない事までしてたのか……。
「みずき、お前どうでもいいけど、怪我だけはすんなよ」
「んー? なになになにぃ? みのる、あたしのこと心配してくれるの? うれしい!」
チェーンソーを下ろし、プロテクター類を外したみずきが腕にしがみついてくる。ツインテールがまたぴょこんと跳ねた。
「ば、ちがっ……俺は前みたいな事故はごめんなだけだっ」
「んー、いいのいいの。あたしはちゃーんとわかってるから! ありがとう、みのる」
もう、みずきは俺の言葉なんか聞いちゃいない。
ひたすら笑顔で俺の腕に、その少しふくらんだ胸を押し付けてくる。
「う、あ……」
顔面が熱をもっていくのが自分でもわかった。俺は少し乱暴な態度でみずきを振り払う。
「と、とにかく! 危ない事はするな! 以上!」
急に引き離されたみずきはしばらく呆然としていたが、俺の顔に浮かんだ照れを理解したのか、にんまりと微笑んだ。
「うん……わかったよ、みのる。これから気をつけるね」
「お、おう……わかったのならいいんだよ。わかったのなら……」
「それじゃ、わかったところで、そろそろ帰ろうか! ほら、お日様も沈んじゃうよ?」
言われてみれば、周りはもう一面オレンジ色の光につつまれていた。
冬の日の入りは早い。ぼやぼやしていれば、あっという間に闇夜に包まれることだろう。
「それじゃあ帰るぞ。ほら、そのチェーンソー片付けてこいよ」
「おっけー、おっけー! 行ってくるからすこーし待っててね」
そう言い残して、みずきは駆けていく。俺はその後ろ姿を眺めながら、少し笑った。
「そうだな、子供の力だからな。そんなに深くまでは埋めれなかったんだろうな」
掘り出したそれは、やはり記憶とは微妙に違う小さな金属の缶だった。縁が微妙に錆びている。こんな薄っぺらな入れ物でよく今まで無事に埋まっていられたものだ。素直にそう思った。
「これはこのまま持ってて、小屋の中で開けようぜ」
二月という冬場でも運動をすれば少しは汗もかく。自分はともかくとして、このままここに居ればみずきが風邪を引きかねない。
それに、俺が風邪を引いたって、どうせみずきは世話を焼きに家までくるだろう。そこでうつしてしまっては元も子もない。
「そうだね……あ、でも」
素直にうなずくかと思ったみずきは少し悪戯っぽく笑って、踵を返した。
「みのる。ちょ~っとだけ、そこで待ってて」
そしてそのまま小屋まで駆けていくと、一抱えもあるやたら物騒な代物を抱えて帰ってきた。
「はい、みのるこれ持つ! 危ないから落としちゃダメだよ」
「お、おまえこれって……」
どしり、と確かな重量が両手にのしかかる。それは作業用の機械のようだった。
ただの機械じゃない。仄かに香るガソリンと、オイルのにおい。錆びた鉄。エンジンがついていた。
そしてそこからにょっきりと生えた剣呑で、黒光りするブレード――。
こ、これは……。
「チェ、チェーンソーじゃないか! なにすんだよ、こんなもん持ってきて!」
「みのるにあたしの特技見せてあげるっ!」
「と、特技ってお前……」
みずきは手早く、やたら厚手で丈夫そうなエプロンをかけ、手袋とゴーグルを装着した。
そして、材木置き場の方へ行くと、少し大きめの丸太を転がしてくる。それを手ごろな切り株の上に乗せた。
「本当は音がすごいからイヤープロテクターもつけなきゃいけないんだけど、今日は持ってきてないから」
みずきは俺からチェーンソーを受け取る。
「なんか……すげー格好だな」
俺は困惑していた。急にそんなものを持ち出したみずきの考えがわからなかった。
「大丈夫、大丈夫。あたしに任せておきなさいっ!」
そんな俺を無視して、みずきは得意そうに笑う。
「危ないから、みのるは離れててね」
そういって、エンジンスタータを一気に引っ張る。
どるんっ
低い音が鳴る。それに続き、ドッドッドッドという断続的なエンジン音が山間に響く。
「何するつもりなんだ?」
「えへへー、ひみつ~。みのる、しっかり見ててねっ」
みずきはそう宣誓するや否や、エンジンの回転をブレードに伝えるスイッチを入れた。
ギュアアアアアアァン
瞬間、悲鳴のような轟音が場を満たす。みずきの操る高速で回転するブレードが丸太の端に触れた時、その音はひと際高まった。
接地点が木屑で霞む。みずきはぐっと踏み込むと、押し返されないように力を込めた。
そしてそのまま、振りぬく。ぽーんと、切断された木片が飛んでいった。
みずきはブレードを器用に操り、丸太を寸断していく。さらに破片が飛び、粉が舞う。
その中でみずきは楽しそうにブレードを振り続けた。俺はそれを見て、まるで踊っているようだと感じる。
みずきが右にブレードを振れば、頂上部の出っ張りがあっさりと落ちる。みずきが左にブレードを捻れば、中ほどに大きな裂け目が生じた。
そして、見ているうちに、丸太が何がしかの形を取りはじめる。
最初に大まかに粗が落とされ、饅頭のような概観が見えてきた。次に、ブレードの先端を薄くあて、線が入れられる。
それに沿って、薄く表面を撫で削っていく。
いつの間にか、丸太は台座の上に座った立派なウサギの彫刻にかわっていた。
「よし、出来上がり!」
ぐいっと、ゴーグルをあげたみずきの頬には汗がにじんでいた。
「こ、これは……」
「すごいでしょ! チェーンソーカービングっていうの。チェーンソーを使って彫り物をするスポーツなんだけど、あたし最年少で大会だって出たことあるんだよ」
「た、確かに……これはすごいな」
本当にあっという間のことだった。時間にしても二十分もかかっていないだろう。その間にみずきはこのウサギの像を作り上げてしまった。
「でしょ? 家にある椅子だってあたしが作ったんだから」
そう胸を突き出すみずきは誇らしげだ。
「お前、昔からこんな事を?」
「そうだよ。木工所のみんなにだって、チェーンソーの取り扱いなら負けないの。新しく入ってきた人に教えてあげる事だってあるんだから」
俺はあっけに取られる。こいつ、こんな危ない事までしてたのか……。
「みずき、お前どうでもいいけど、怪我だけはすんなよ」
「んー? なになになにぃ? みのる、あたしのこと心配してくれるの? うれしい!」
チェーンソーを下ろし、プロテクター類を外したみずきが腕にしがみついてくる。ツインテールがまたぴょこんと跳ねた。
「ば、ちがっ……俺は前みたいな事故はごめんなだけだっ」
「んー、いいのいいの。あたしはちゃーんとわかってるから! ありがとう、みのる」
もう、みずきは俺の言葉なんか聞いちゃいない。
ひたすら笑顔で俺の腕に、その少しふくらんだ胸を押し付けてくる。
「う、あ……」
顔面が熱をもっていくのが自分でもわかった。俺は少し乱暴な態度でみずきを振り払う。
「と、とにかく! 危ない事はするな! 以上!」
急に引き離されたみずきはしばらく呆然としていたが、俺の顔に浮かんだ照れを理解したのか、にんまりと微笑んだ。
「うん……わかったよ、みのる。これから気をつけるね」
「お、おう……わかったのならいいんだよ。わかったのなら……」
「それじゃ、わかったところで、そろそろ帰ろうか! ほら、お日様も沈んじゃうよ?」
言われてみれば、周りはもう一面オレンジ色の光につつまれていた。
冬の日の入りは早い。ぼやぼやしていれば、あっという間に闇夜に包まれることだろう。
「それじゃあ帰るぞ。ほら、そのチェーンソー片付けてこいよ」
「おっけー、おっけー! 行ってくるからすこーし待っててね」
そう言い残して、みずきは駆けていく。俺はその後ろ姿を眺めながら、少し笑った。