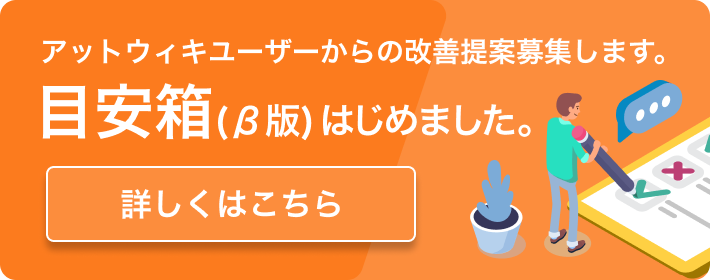早紀2/8支援SS
小さなノイズ。
とても、微弱な音だけど、俺の耳はそれを逃がさない。
とても、微弱な音だけど、俺の耳はそれを逃がさない。
「よし、今日はここまで。分からないところはググレカス」
そういってググレカスこと数学教師九暮和也は、既にまとめてあった用具を持参してドアを出て行った。
ちょうどよく、チャイムの鐘がこれでもかと学校中に響き渡る。
そういってググレカスこと数学教師九暮和也は、既にまとめてあった用具を持参してドアを出て行った。
ちょうどよく、チャイムの鐘がこれでもかと学校中に響き渡る。
やっと終わった。
今日の授業はこれで終わりだ。まだHRが残っているが、自分のクラスのHRはあってないようなもの。
なんせ担任があのググレカスだ。連絡が無ければ10秒もかからずに終わるだろう。
人によっては、連絡に私情を挟みこんでどうたらこうたら話を引き伸ばす先生を担任として受け入れてしまい、
先にHRを終えた生徒達ぞろぞろと廊下を通っても、一番目の前の席にいる生徒があからさまに嫌そうな顔をしても
中々終わらない可哀相なクラスが大体学年に一つは必ずあるものだ。
その点、ググレカスのHRはいつも学年で最短だ。これは、唯一の感謝、そして尊敬するべき点でもあるだろう。
それ以外はクソだが。
なんせ担任があのググレカスだ。連絡が無ければ10秒もかからずに終わるだろう。
人によっては、連絡に私情を挟みこんでどうたらこうたら話を引き伸ばす先生を担任として受け入れてしまい、
先にHRを終えた生徒達ぞろぞろと廊下を通っても、一番目の前の席にいる生徒があからさまに嫌そうな顔をしても
中々終わらない可哀相なクラスが大体学年に一つは必ずあるものだ。
その点、ググレカスのHRはいつも学年で最短だ。これは、唯一の感謝、そして尊敬するべき点でもあるだろう。
それ以外はクソだが。
荷物整理を始めると、戸がガラガラと音を立てて開いた。
「いいか静かにしろHR始めるぞ連絡事項特になしおわりだ散れッ!」
荒々しく戸が閉まる。
「いいか静かにしろHR始めるぞ連絡事項特になしおわりだ散れッ!」
荒々しく戸が閉まる。
本日のHRは8秒なり。
「みのりーん」
「伊万里か」
「ちょっと早いよ、はぁ」
廊下で伊万里とエンカウント。
伊万里のクラスは少しHRが長引いたようで、どうやら走ってきたみたいだった。
だが、今の俺に伊万里を待つ理由は残念ながら無い。
「なんでそんな早足なのさぁー」
「生者の最大の敵は時間だ。時間の向こうには必ず死が待っている」
「へ?」
「時間は限られている。一分一秒でも無駄にすることは死を意味する」
「何言ってるかわかんないけど行き急ぐと早死にするよ」
「まぁそれもそうだな。」
少し歩調を緩める。
「でさ、なんでそんな急いでるの?」
「我が家の食糧事情が芳しくなくてね」
前を向いたまま質問に答える。
「冷蔵庫の中身が無いから商店街に食料買出しに行かなきゃならんのだ。姉さんはこういうのしないタイプだし、
仮に行ってくれたとしても渡したお金で何を買ってくるか分からん」
商店街は学校帰りに寄るのには少し遠い。急がねば商店街に着く頃に日が暮れてしまう。
「そっかー、せっかくなら付き合おうか?」
伊万里が笑いかけてくる。なんだかからかわれてる気がしてきた。
「付き合わなくていい」
男だからといって家事ができないと思ったら大間違いだ。伊達にこの不景気の中姉さんと二人暮ししてきたわけではない。
主夫を舐めてもらっては困るのだ。
「それよりみずきと一緒に帰ってやれよ。寂しがるぞ」
「あっ、そう…じゃあね」
「じゃあな」
つまらないような、それでいて少しムスっとしているような微妙な表情を浮かべて、伊万里は掛けて行った。
「伊万里か」
「ちょっと早いよ、はぁ」
廊下で伊万里とエンカウント。
伊万里のクラスは少しHRが長引いたようで、どうやら走ってきたみたいだった。
だが、今の俺に伊万里を待つ理由は残念ながら無い。
「なんでそんな早足なのさぁー」
「生者の最大の敵は時間だ。時間の向こうには必ず死が待っている」
「へ?」
「時間は限られている。一分一秒でも無駄にすることは死を意味する」
「何言ってるかわかんないけど行き急ぐと早死にするよ」
「まぁそれもそうだな。」
少し歩調を緩める。
「でさ、なんでそんな急いでるの?」
「我が家の食糧事情が芳しくなくてね」
前を向いたまま質問に答える。
「冷蔵庫の中身が無いから商店街に食料買出しに行かなきゃならんのだ。姉さんはこういうのしないタイプだし、
仮に行ってくれたとしても渡したお金で何を買ってくるか分からん」
商店街は学校帰りに寄るのには少し遠い。急がねば商店街に着く頃に日が暮れてしまう。
「そっかー、せっかくなら付き合おうか?」
伊万里が笑いかけてくる。なんだかからかわれてる気がしてきた。
「付き合わなくていい」
男だからといって家事ができないと思ったら大間違いだ。伊達にこの不景気の中姉さんと二人暮ししてきたわけではない。
主夫を舐めてもらっては困るのだ。
「それよりみずきと一緒に帰ってやれよ。寂しがるぞ」
「あっ、そう…じゃあね」
「じゃあな」
つまらないような、それでいて少しムスっとしているような微妙な表情を浮かべて、伊万里は掛けて行った。
さて、早足に戻しますかね。
商店街に到着。太陽がオレンジ色の光を発し、日が沈むのが近いことを告げている。
早く帰らないと晩飯を作るのが遅れる。急がねば。
いつものスーパーに寄る。とりあえず、一回りして値段を確認してから、安い食材メインでできるメニューを考えつつ買い物を済ませよう。
早く帰らないと晩飯を作るのが遅れる。急がねば。
いつものスーパーに寄る。とりあえず、一回りして値段を確認してから、安い食材メインでできるメニューを考えつつ買い物を済ませよう。
「卵安いな…たまねぎも安い」
最近野菜中心のメニュー続きだったので、今日はハンバーグにでもするかな。
卵、たまねぎ、更に切らしてた牛乳やら調味料やらを籠に入れていく。ホントはタイムサービスを待ちたかったのだが、
あんまり帰りが遅いと姉のご機嫌を損ねてしまうのでしょうがない。
レジは少し混み気味だ。適当に早く終わりそうなところへと並ぶ。
最近野菜中心のメニュー続きだったので、今日はハンバーグにでもするかな。
卵、たまねぎ、更に切らしてた牛乳やら調味料やらを籠に入れていく。ホントはタイムサービスを待ちたかったのだが、
あんまり帰りが遅いと姉のご機嫌を損ねてしまうのでしょうがない。
レジは少し混み気味だ。適当に早く終わりそうなところへと並ぶ。
それにしても、本当に我ながら自分ってデキてる主夫だよなと再認識する。しかし、姉のような妻は正直ゴメンだ。
そう思うと、なんだか姉が不安になってきた。人並み以下の家事スキルで、他にこれといった長所がない。金遣いも荒い。
…需要は低そうだな。
そう思うと、なんだか姉が不安になってきた。人並み以下の家事スキルで、他にこれといった長所がない。金遣いも荒い。
…需要は低そうだな。
そうこう考えてるうちに、自分の前にレジが並んできた。店員がせっせと清算をする。
「1749円になります。袋はどうされますか?」
「いえ、結構です」
「1749円になります。袋はどうされますか?」
「いえ、結構です」
今レジの後ろに並んでいた人は思うだろう。この学生、只者じゃないと…!家事スキルだけではなく環境にも配慮する
優しい心遣いに感銘をうけて、後列に並ぶ人々は明日からマイトートバッグを持参してくるに違いない。
光悦な笑みを浮かべて自己陶酔におぼれながら、ふとある事実に気付いた。
優しい心遣いに感銘をうけて、後列に並ぶ人々は明日からマイトートバッグを持参してくるに違いない。
光悦な笑みを浮かべて自己陶酔におぼれながら、ふとある事実に気付いた。
無い。無い。ポケットのふくらみが無い。財布がない。
忘れた。ぬかった…!
この完璧なる主夫の稔様が財布を忘れるというような愚行をしてしまうとは…!
どうしようどうすればいい。主婦達の冷たい視線と高らかなせせら笑いを浴び、「あの子全然甘いわね」という熟練の先輩方の
鋭利なバッシングの嵐の中、自分が最良と思って選んだ獲物を棚に戻し他人にみすみす引き渡すなんて主夫の名が廃る!
本当にどうしよう。もしそうなったらもうこのスーパーに二度と顔なんて見せられない…!もう主夫引退するしかないわ!
しかし、そうせざるを得ない状況だった。事実、払う金が一銭も無いのだ。
どうしようどうすればいい。主婦達の冷たい視線と高らかなせせら笑いを浴び、「あの子全然甘いわね」という熟練の先輩方の
鋭利なバッシングの嵐の中、自分が最良と思って選んだ獲物を棚に戻し他人にみすみす引き渡すなんて主夫の名が廃る!
本当にどうしよう。もしそうなったらもうこのスーパーに二度と顔なんて見せられない…!もう主夫引退するしかないわ!
しかし、そうせざるを得ない状況だった。事実、払う金が一銭も無いのだ。
開けたくない口を開ける。
「すみません、その―」
「ああちょっと」
突如自分の言葉が遮られた。
「すいません、これも一緒にお願いします」
レジの小銭受けに1万円札、更にレジにいっぱい食材の詰まったカゴがポンと置かれる。
思わずその行為にびっくりして、後ろを振り返る。
「あ、あなたは…!」
「すみません、その―」
「ああちょっと」
突如自分の言葉が遮られた。
「すいません、これも一緒にお願いします」
レジの小銭受けに1万円札、更にレジにいっぱい食材の詰まったカゴがポンと置かれる。
思わずその行為にびっくりして、後ろを振り返る。
「あ、あなたは…!」
「本当にありがとうございます。もうなんとお礼を言っていいか」
「いえいえ、お気になさらず」
「もう何度でもお礼言わせてください蓬山先輩」
「いえいえ、お気になさらず」
「もう何度でもお礼言わせてください蓬山先輩」
俺の名誉は守られた。後ろから一万円札を出してくれたのは、偶然にも自分の一つ後ろに並んでた蓬山先輩だった。
「お金は明日必ず返します」
「あら、お金なら別にいいのよ、私も買い物したんだし」
「いや、ここで甘えたら主夫の名が廃ります」
「うふふ、稔君ったら面白い人」
くすくすと、口に手を沿え上品に笑う仕草は、姉とは正反対の大人らしい可愛さをかもし出す。
「最初うちの学校の制服を見かけたから気になってはいたけど、まさか稔君だったなんてね」
「すごい観察眼ですね。自分は先輩がいるなんて、あの時まで全く気付きませんでしたよ」
先輩は制服だ。今時の女の子が履くようなものではない、膝下まで伸びる長めのスカートが、ゆらゆらと歩くごとに揺れている。
見た目的には目立つんだが、急いでることもあってか全く目に入らなかったのだろう。
「これでも視力は結構いいのよ」
「とりあえず、この借りはいずれ返します」
「あら、まるでライバルみたいな物言いね」
「一度言ってみたかったんですよ」
「お金は明日必ず返します」
「あら、お金なら別にいいのよ、私も買い物したんだし」
「いや、ここで甘えたら主夫の名が廃ります」
「うふふ、稔君ったら面白い人」
くすくすと、口に手を沿え上品に笑う仕草は、姉とは正反対の大人らしい可愛さをかもし出す。
「最初うちの学校の制服を見かけたから気になってはいたけど、まさか稔君だったなんてね」
「すごい観察眼ですね。自分は先輩がいるなんて、あの時まで全く気付きませんでしたよ」
先輩は制服だ。今時の女の子が履くようなものではない、膝下まで伸びる長めのスカートが、ゆらゆらと歩くごとに揺れている。
見た目的には目立つんだが、急いでることもあってか全く目に入らなかったのだろう。
「これでも視力は結構いいのよ」
「とりあえず、この借りはいずれ返します」
「あら、まるでライバルみたいな物言いね」
「一度言ってみたかったんですよ」
二人で談笑しながら、商店街の入り口まで歩いていく。
もし、他人から見てみたらカップルに見えるのだろうか。背は結構近く、同じ学校の制服。
そんな男女が笑いあいながら一緒に商店街の通りを歩いている。
もし蓬山先輩が彼女だったらどうしよう。先輩は正直顔もいいし、性格もこれといって問題は無い。
むしろ俺のほうが先輩と比べて見劣りするんじゃ…って何を考えてるんだ俺は。
もし、他人から見てみたらカップルに見えるのだろうか。背は結構近く、同じ学校の制服。
そんな男女が笑いあいながら一緒に商店街の通りを歩いている。
もし蓬山先輩が彼女だったらどうしよう。先輩は正直顔もいいし、性格もこれといって問題は無い。
むしろ俺のほうが先輩と比べて見劣りするんじゃ…って何を考えてるんだ俺は。
少し顔が火照ってきたが、先輩に悟られないように話を続けた。太陽が沈みかけてるのも手伝ってバレることはないだろう。
ってもう太陽が沈む頃か。先輩と別れたら少し急ぐか。
ってもう太陽が沈む頃か。先輩と別れたら少し急ぐか。
商店街の入り口に付いて先輩に声をかけようとしたときだった。
「稔君、あれ見て」
先輩が指指した方向には小さな女の子が一人。
「え?あの子がどうかしたんですか?」
「よく見て」
そう言われたので、言われるがままによく見ると、キョロキョロしてる。
その顔はどこか不安そうで、まるで泣きたいのを必死に抑えているようだ。
「たぶん親とはぐれちゃったのかしら」
「親に待たされてるだけじゃないんですか?」
太陽は沈みかけて、赤色になり、辺りはより一層薄暗くなっている。
あの女の子を見捨てるのは気が引けるが、あんまり面倒事を起して帰りが遅れるのも正直避けたい。
…のだが、気付いたときには、先輩は子供に話しかけていた。
こんな薄暗い中でも発揮される観察力に脱帽しながら、自分はその様子を傍観することにした。
恐らく、大丈夫?お母さんは?などと先輩は声をかけているのだろう。
子供は少し身構えている。やっぱり知らない人は怖いのだろう。
ふと、先輩は自分のバッグから飴玉らしき物を取り出した。
―ああ、これどっかで見たことある。ついさっき、一万円札を差し出してくれた手。
「稔君、あれ見て」
先輩が指指した方向には小さな女の子が一人。
「え?あの子がどうかしたんですか?」
「よく見て」
そう言われたので、言われるがままによく見ると、キョロキョロしてる。
その顔はどこか不安そうで、まるで泣きたいのを必死に抑えているようだ。
「たぶん親とはぐれちゃったのかしら」
「親に待たされてるだけじゃないんですか?」
太陽は沈みかけて、赤色になり、辺りはより一層薄暗くなっている。
あの女の子を見捨てるのは気が引けるが、あんまり面倒事を起して帰りが遅れるのも正直避けたい。
…のだが、気付いたときには、先輩は子供に話しかけていた。
こんな薄暗い中でも発揮される観察力に脱帽しながら、自分はその様子を傍観することにした。
恐らく、大丈夫?お母さんは?などと先輩は声をかけているのだろう。
子供は少し身構えている。やっぱり知らない人は怖いのだろう。
ふと、先輩は自分のバッグから飴玉らしき物を取り出した。
―ああ、これどっかで見たことある。ついさっき、一万円札を差し出してくれた手。
困ったを人を見捨てれない、人の良い性格。そういった性格をしている人が、一番世の中で間抜けだと思っていた。
他人を見捨てれないがために、自らの身をすり減らしてまで相手に尽くす。
だからといって、その後相手が自分に何かをしてくれるわけでもないのに。
分からない。なぜそんな分の悪い賭けをするのか。俺には、そんな人の思考が理解できなかった。
でも、困っていた時、先輩は助けてくれた。そして今、飴玉を渡された女の子は美味しそうにそれを笑いながら頬張っている。
先輩に近づいた。
「あ、稔君」
「親、居なかったんでしょう。探しましょうよ。荷物は僕が持ちますから、その子と手をつないであげてください」
「…ありがとう、稔君」
他人を見捨てれないがために、自らの身をすり減らしてまで相手に尽くす。
だからといって、その後相手が自分に何かをしてくれるわけでもないのに。
分からない。なぜそんな分の悪い賭けをするのか。俺には、そんな人の思考が理解できなかった。
でも、困っていた時、先輩は助けてくれた。そして今、飴玉を渡された女の子は美味しそうにそれを笑いながら頬張っている。
先輩に近づいた。
「あ、稔君」
「親、居なかったんでしょう。探しましょうよ。荷物は僕が持ちますから、その子と手をつないであげてください」
「…ありがとう、稔君」
「みのるくんおーそーいー」
時計は8時を過ぎていた。
無言の帰宅に、姉さんは口を屁の字に曲げながらこちらを睨んでくる。
「お腹すいたんだけどー」
「…今作るよ」
「はやくぅー」
学生服のまま、買ってきた食材でさっさと調理を始める。俺が料理を始めるのを確認したのか、姉はテレビを見始めた。
時計は8時を過ぎていた。
無言の帰宅に、姉さんは口を屁の字に曲げながらこちらを睨んでくる。
「お腹すいたんだけどー」
「…今作るよ」
「はやくぅー」
学生服のまま、買ってきた食材でさっさと調理を始める。俺が料理を始めるのを確認したのか、姉はテレビを見始めた。
迷子になった子は、結論だけ言うと、親に引き渡すことができた。
親は、子供が迷子になったのに気付くとすぐに交番に行って、そこで待機してたらしい。
しかし、肝心の子供達を連れた俺らはというと、7時過ぎまで商店街で親を探し、彷徨い歩いていた。
親は子供が心配なあまり、商店街で必死に探していると俺たちは思ったのだが、
どうやら最近ここに越してきたらしく、地理に疎いので交番で待機してたらしい。
結局2時間以上も俺たちは無駄な時間を過ごしたわけだが、7時過ぎて諦め半分で交番に行って母親を見つけた時の、
先輩と女の子の幸せそうな笑顔はそれだけの価値があったと思う。
そんでその後少しだけ警察に話を聞かれて帰ってきたら、こんな時間になっていたというわけだ。
姉さんにこの話をしたら許してくれそうではあるが、主夫としてのプライドがなんとなくそれを拒んだので黙秘権を行使するにいたった。
親は、子供が迷子になったのに気付くとすぐに交番に行って、そこで待機してたらしい。
しかし、肝心の子供達を連れた俺らはというと、7時過ぎまで商店街で親を探し、彷徨い歩いていた。
親は子供が心配なあまり、商店街で必死に探していると俺たちは思ったのだが、
どうやら最近ここに越してきたらしく、地理に疎いので交番で待機してたらしい。
結局2時間以上も俺たちは無駄な時間を過ごしたわけだが、7時過ぎて諦め半分で交番に行って母親を見つけた時の、
先輩と女の子の幸せそうな笑顔はそれだけの価値があったと思う。
そんでその後少しだけ警察に話を聞かれて帰ってきたら、こんな時間になっていたというわけだ。
姉さんにこの話をしたら許してくれそうではあるが、主夫としてのプライドがなんとなくそれを拒んだので黙秘権を行使するにいたった。
「できたよ姉さん」
「おおー、ハンバーグ!」
主夫たるもの、疲れてた状態であっても料理なんて楽勝だ。
目の前につやのある肉汁をまといながら香ばしい匂いを漂わせるハンバーグがそう物語っている。
『いただきます』
フォークで肉片を口に運ぼうとしたそのとき。
「ねえ、稔くん」
「ん?」
「今日遅れたでしょ」
「うん、悪かったよ、ごめん」
「悪いと思ってるなら、おねえちゃんにハンバーグを食べさせて」
「俺疲れてるんだから、こっちが食べさせて欲しい気分だよ」
そういって、先輩の分の荷物を持って疲労しきった腕で、食事を口に運ぶ。
「わかった。でもおねえちゃんフォーク使えないから口移しね!」
ぶっ、と咀嚼した肉片を吐き出した。
「うっわー、ばっちぃ」
「うるさい!姉さんがとんでも発言するからだろっ」
そういってティッシュで肉片をつまんでいく。
「おねーちゃんのにもかかったんだけど」
「どうしろっていうのさ」
すると、フォークでハンバーグを切り取って、掲げて見せた。てかフォーク使えるじゃん。
「これが、稔くんの唾液がついたハンバーグ…」
そういうと、一気にフォークを口元へ運んだ。
しばらく咀嚼してから、
「稔くんの味がして、おいしいよぉ…」
と身を悶えさせて味をかみ締めていた。
なんだか同じ姉弟だとは思えない。てか思いたくない。
「おおー、ハンバーグ!」
主夫たるもの、疲れてた状態であっても料理なんて楽勝だ。
目の前につやのある肉汁をまといながら香ばしい匂いを漂わせるハンバーグがそう物語っている。
『いただきます』
フォークで肉片を口に運ぼうとしたそのとき。
「ねえ、稔くん」
「ん?」
「今日遅れたでしょ」
「うん、悪かったよ、ごめん」
「悪いと思ってるなら、おねえちゃんにハンバーグを食べさせて」
「俺疲れてるんだから、こっちが食べさせて欲しい気分だよ」
そういって、先輩の分の荷物を持って疲労しきった腕で、食事を口に運ぶ。
「わかった。でもおねえちゃんフォーク使えないから口移しね!」
ぶっ、と咀嚼した肉片を吐き出した。
「うっわー、ばっちぃ」
「うるさい!姉さんがとんでも発言するからだろっ」
そういってティッシュで肉片をつまんでいく。
「おねーちゃんのにもかかったんだけど」
「どうしろっていうのさ」
すると、フォークでハンバーグを切り取って、掲げて見せた。てかフォーク使えるじゃん。
「これが、稔くんの唾液がついたハンバーグ…」
そういうと、一気にフォークを口元へ運んだ。
しばらく咀嚼してから、
「稔くんの味がして、おいしいよぉ…」
と身を悶えさせて味をかみ締めていた。
なんだか同じ姉弟だとは思えない。てか思いたくない。
食事を終えて、ベッドに横たわる。少し食べ過ぎたか、お腹が張っているのが分かる。
なんだか今日は歩き過ぎて疲れたが、玉にはこういうのもいいか。
久しぶりの疲労感と、ちょうどいい眠気で、今すぐにでも寝れそうだった。
風呂は明日にでもしよう。そう思って、寝巻きに着替えると床についた。
なんだか今日は歩き過ぎて疲れたが、玉にはこういうのもいいか。
久しぶりの疲労感と、ちょうどいい眠気で、今すぐにでも寝れそうだった。
風呂は明日にでもしよう。そう思って、寝巻きに着替えると床についた。