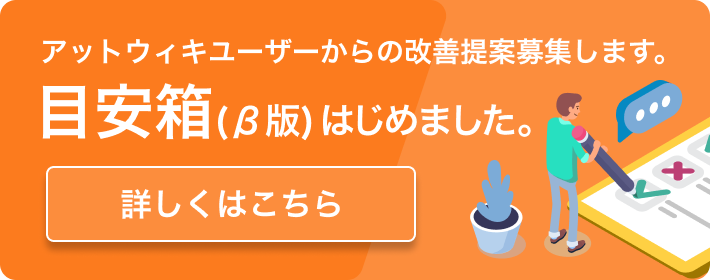ジャリッ、ジャリッ――
段を一つ登る事に、乾いた砂やゴミの、擦れてぶつかり合う音が、埃っぽく薄暗い空間に響きわたる。汚く、いかにも長年もの間ほったらかしにされてたと言わんばかりの階段。顔を少し挙げてみれば、四角い隙間から微かに漏れる淡い光に照らされた無数の埃がこれまたとなくこの空間の不潔さを主張する。そして、そのメッセージを受けとるかのごとく、咳をしたい欲求に駆られながらも、なるべく埃をたてまいと慎重に足を置いていく。
ゴオオオオオ――
四角い隙間から、光と共に風も入り込んでくる。それらは埃を巻き上げ、まるで侵入者を排除する番人のごとく壁となってぶつかっていく。そして、自らの体に真っ二つに裂かれた番人は、負けたのが悲しいのか、獣のような叫び声と共に下の方へと渦巻いてく。
そのほうこう(なぜか変換ry)に悲しんだのか、侵入者は、口元を手で押さえて目を細める。実際は、風が吹き荒れたせいで今までになく吹き上げた埃からの必死の防衛策だったが。
頂上にやっとついた。隙間だったそれはいつのまにか大きくなって、顔を突っ込めるくらいの大きさになっており、その向こうは狂うように輝いていて、思わず目を細める。
右手で、探る。
――ガチャリ
乾いた金属音を立てたあと、悲鳴のような鳴き声を上げてドアが開く。甲高く、か細い音。一歩踏み出すと、薄暗い空間とは対照的な、首筋を撫でるように涼しく、いつまでも触れていたい風が底にあった。
段を一つ登る事に、乾いた砂やゴミの、擦れてぶつかり合う音が、埃っぽく薄暗い空間に響きわたる。汚く、いかにも長年もの間ほったらかしにされてたと言わんばかりの階段。顔を少し挙げてみれば、四角い隙間から微かに漏れる淡い光に照らされた無数の埃がこれまたとなくこの空間の不潔さを主張する。そして、そのメッセージを受けとるかのごとく、咳をしたい欲求に駆られながらも、なるべく埃をたてまいと慎重に足を置いていく。
ゴオオオオオ――
四角い隙間から、光と共に風も入り込んでくる。それらは埃を巻き上げ、まるで侵入者を排除する番人のごとく壁となってぶつかっていく。そして、自らの体に真っ二つに裂かれた番人は、負けたのが悲しいのか、獣のような叫び声と共に下の方へと渦巻いてく。
そのほうこう(なぜか変換ry)に悲しんだのか、侵入者は、口元を手で押さえて目を細める。実際は、風が吹き荒れたせいで今までになく吹き上げた埃からの必死の防衛策だったが。
頂上にやっとついた。隙間だったそれはいつのまにか大きくなって、顔を突っ込めるくらいの大きさになっており、その向こうは狂うように輝いていて、思わず目を細める。
右手で、探る。
――ガチャリ
乾いた金属音を立てたあと、悲鳴のような鳴き声を上げてドアが開く。甲高く、か細い音。一歩踏み出すと、薄暗い空間とは対照的な、首筋を撫でるように涼しく、いつまでも触れていたい風が底にあった。
あまりの清々しさに、その姿はまるで今まで牢に入れられてた人間のように見えた。今まで悔い改め償ってきたはずの罪を、たった目の前のわずかな感覚に忘れさせられた。
ここは、屋上。
自殺とか言った物騒事は幸いこの学校には無かったみたいだが、危ないといった至極単純極まりない形容詞は、こことそれを繋ぐ階段を封鎖する理由に十分な説得力を有していた。
だから、この学校の屋上へ続く階段は汚く、閉鎖されてから掃除すら行われていない。屋上は飾りのフェンスに囲まれ、今までただ雨をしのぐ屋根としての役割を全うしてきた。
だから、ここには誰も来ない。話題にすらなることも少ない。恐らく、歴代の生徒でここを訪れたのは自分くらいではなかろうか。かすかな征服感と独占欲に浸りながらまた一歩を踏み出した時、静寂が破られた。
「珍しいわね」
すかさず後ろを振り向く。
「先生にチクっちゃおうかしら」
声の主はどこか陰湿な笑みを浮かべてそういった。
よく見れば、この学校の制服。それに気付くと、さっきまでのかすかな征服感と独占欲が砕かれた気がして、少し不愉快になった。
「そうしたらあんたも困るんじゃないか」
そういうと、さっきまで緑色のフェンスにもたれている女の顔から笑みが消えた。驚いているというか呆気にとられているというか、とにかく期待とは全然違う反応をされたので、なんだか困ってしまった。
すると、そんな自分の表情を読み取ったのか、今度ははくすくすと、上品だけども少し幼い、背伸びした少女のように笑い始めた。その笑顔には、さっきまでの嫌味ったらしい感じは全く感じられなかったが、自分はますますこの女性の事が分からなくなった。
制服の上からでも分かる、男を虜にする柔らかでいて豊かなスタイル。少し短い黒のスカートから覗く足は、太陽の光に照らされて白い絹のように輝き、この学校の校則に思わず感謝せざるを得ない。そして上品で整った、癖の無い顔立ちはどこか令嬢っぽい雰囲気を漂わせる。更に、軽くウェーブがかかった髪は、その一本一本が風になびいて、かなり丁寧に手入れされてることを教えてくれる。色はフェンスと同じ緑系だが、南国の浅い珊瑚礁の海を思わせる鮮やかなライトグリーン。太陽の光によって生み出される光と陰、色の濃淡の動きは、まるで自然が作り出す海の波のように、彼女の髪の表面をさらさらと流れていき、まるで今の季節が夏じゃないかと錯覚させる。
―ああ、彼女には黒いビキニが似合うだろう。彼女の少し悪戯めいた笑顔には、暗い色がきっとよく似合う。その中でも一番の、暗黒めいたうるわしの黒は、彼女の笑みとあいまって、きっと彼女を人から悪魔へと仕立てあげるに違いない。そして、その漆黒は艶やかでなまめかしい彼女の太陽で照らされて眩しく白い肌と対を無し、白と黒でおりなすコントラストと抜群のスタイルは、獣の視線を釘付けにして、心を奪い、性欲という性欲を掻き乱しては打ち付けるだろう。そして心から思うのだ、彼女はまさに淫魔だ、彼女と海に行ける奴は幸せものだと―
「知らないのね」
「え?」
「いや、なんでもないわ」
突如思考が中断された。彼女の声がやまびこのように頭の中をぐるぐる回って、ドラッグ常用者も真っ青の妄想の大海原の中から脳を現実へと引き戻す。
「あなた、名前は?」
「ん、あぁ、藤宮稔。2年だ」
「そう…あなた年下だから敬語使いなさい」
そういって、またお決まりの小悪魔スマイルを放つ。
しかし、さっきの妄想のせいか、はたまた彼女の時々見せる乙女チックな仕草のせいか、さっきまでの嫌悪感は風に吹かれてどこかいってしまったようだった。
ここは、屋上。
自殺とか言った物騒事は幸いこの学校には無かったみたいだが、危ないといった至極単純極まりない形容詞は、こことそれを繋ぐ階段を封鎖する理由に十分な説得力を有していた。
だから、この学校の屋上へ続く階段は汚く、閉鎖されてから掃除すら行われていない。屋上は飾りのフェンスに囲まれ、今までただ雨をしのぐ屋根としての役割を全うしてきた。
だから、ここには誰も来ない。話題にすらなることも少ない。恐らく、歴代の生徒でここを訪れたのは自分くらいではなかろうか。かすかな征服感と独占欲に浸りながらまた一歩を踏み出した時、静寂が破られた。
「珍しいわね」
すかさず後ろを振り向く。
「先生にチクっちゃおうかしら」
声の主はどこか陰湿な笑みを浮かべてそういった。
よく見れば、この学校の制服。それに気付くと、さっきまでのかすかな征服感と独占欲が砕かれた気がして、少し不愉快になった。
「そうしたらあんたも困るんじゃないか」
そういうと、さっきまで緑色のフェンスにもたれている女の顔から笑みが消えた。驚いているというか呆気にとられているというか、とにかく期待とは全然違う反応をされたので、なんだか困ってしまった。
すると、そんな自分の表情を読み取ったのか、今度ははくすくすと、上品だけども少し幼い、背伸びした少女のように笑い始めた。その笑顔には、さっきまでの嫌味ったらしい感じは全く感じられなかったが、自分はますますこの女性の事が分からなくなった。
制服の上からでも分かる、男を虜にする柔らかでいて豊かなスタイル。少し短い黒のスカートから覗く足は、太陽の光に照らされて白い絹のように輝き、この学校の校則に思わず感謝せざるを得ない。そして上品で整った、癖の無い顔立ちはどこか令嬢っぽい雰囲気を漂わせる。更に、軽くウェーブがかかった髪は、その一本一本が風になびいて、かなり丁寧に手入れされてることを教えてくれる。色はフェンスと同じ緑系だが、南国の浅い珊瑚礁の海を思わせる鮮やかなライトグリーン。太陽の光によって生み出される光と陰、色の濃淡の動きは、まるで自然が作り出す海の波のように、彼女の髪の表面をさらさらと流れていき、まるで今の季節が夏じゃないかと錯覚させる。
―ああ、彼女には黒いビキニが似合うだろう。彼女の少し悪戯めいた笑顔には、暗い色がきっとよく似合う。その中でも一番の、暗黒めいたうるわしの黒は、彼女の笑みとあいまって、きっと彼女を人から悪魔へと仕立てあげるに違いない。そして、その漆黒は艶やかでなまめかしい彼女の太陽で照らされて眩しく白い肌と対を無し、白と黒でおりなすコントラストと抜群のスタイルは、獣の視線を釘付けにして、心を奪い、性欲という性欲を掻き乱しては打ち付けるだろう。そして心から思うのだ、彼女はまさに淫魔だ、彼女と海に行ける奴は幸せものだと―
「知らないのね」
「え?」
「いや、なんでもないわ」
突如思考が中断された。彼女の声がやまびこのように頭の中をぐるぐる回って、ドラッグ常用者も真っ青の妄想の大海原の中から脳を現実へと引き戻す。
「あなた、名前は?」
「ん、あぁ、藤宮稔。2年だ」
「そう…あなた年下だから敬語使いなさい」
そういって、またお決まりの小悪魔スマイルを放つ。
しかし、さっきの妄想のせいか、はたまた彼女の時々見せる乙女チックな仕草のせいか、さっきまでの嫌悪感は風に吹かれてどこかいってしまったようだった。
しばらくの静寂。
「…名乗れよ」
「…」
「おい」
「…」
彼女は澄ました顔でいる。
再び嫌悪感が混み上げる。人から聞いておいて自分は言わないなんて非常識極まりない態度に、怒りに身をまかせて歩み寄る。
「お前日本語分かってんのk―」
「けーいーごー。」
何を言ってるんだこいつは…。
「あなたの言葉、そのままそっくりお返しするわ。敬語使いなさいって言ったじゃない」
その言葉にあっと気付かせられるのと同時に、相手のペースに完全に飲み込まれてるのと、小指で持て遊ばれるような感覚がかなりの不快感を呼び起こす。
「…名乗ってください」
「なんか違う気がするけどまぁいいわ。蓬山早紀。3年生よ」
二年生の年上と行ったら三年生しか居ないのは分かっていたのだが黙っていた。
「三年生って言ったらもう受験生じゃないですか。なのに屋上でサボりとは呑気な物ですね」
わざと嫌味ったらしく言ってみる。
「なんか特別な理由でもあるんですか?」
そういうと、彼女はそうね、と呟いて、ポケットから白い箱と何かを取り出しながら移動し始めた。
「あっ…」
もう答えは出ているが、その一連の動作を見つめている。自分より一つ上の女性が、煙草を吸うのを。
高そうな銀のライターで、口元にくわえた煙草に火を点ける。彼女は一服するためにここへ来たのだ。風下に移動したあたり、配慮はしてくれてるのだが、彼女が逐一吐き出す白い煙は彼女の美しさとあいまって、とても綺麗なものに感じた。煙というより、白い吐息。まるで彼女と煙の二つは美しい芸術品みたいで、この屋上と同じように人々に忘れられ、ここに取り残されているようでもあった。
「あのね…」
ふぅと口から白煙が漏れる。こんなものに何種類以上の発ガン物質が含まれているなんて信じられないほど、緩やかに、優しく流されていく。決して煙草を美化しているわけではない。彼女が美しいからこそ、まわりにあるものも美しくある、といった感じに。それは必然なのだ。
「…名乗れよ」
「…」
「おい」
「…」
彼女は澄ました顔でいる。
再び嫌悪感が混み上げる。人から聞いておいて自分は言わないなんて非常識極まりない態度に、怒りに身をまかせて歩み寄る。
「お前日本語分かってんのk―」
「けーいーごー。」
何を言ってるんだこいつは…。
「あなたの言葉、そのままそっくりお返しするわ。敬語使いなさいって言ったじゃない」
その言葉にあっと気付かせられるのと同時に、相手のペースに完全に飲み込まれてるのと、小指で持て遊ばれるような感覚がかなりの不快感を呼び起こす。
「…名乗ってください」
「なんか違う気がするけどまぁいいわ。蓬山早紀。3年生よ」
二年生の年上と行ったら三年生しか居ないのは分かっていたのだが黙っていた。
「三年生って言ったらもう受験生じゃないですか。なのに屋上でサボりとは呑気な物ですね」
わざと嫌味ったらしく言ってみる。
「なんか特別な理由でもあるんですか?」
そういうと、彼女はそうね、と呟いて、ポケットから白い箱と何かを取り出しながら移動し始めた。
「あっ…」
もう答えは出ているが、その一連の動作を見つめている。自分より一つ上の女性が、煙草を吸うのを。
高そうな銀のライターで、口元にくわえた煙草に火を点ける。彼女は一服するためにここへ来たのだ。風下に移動したあたり、配慮はしてくれてるのだが、彼女が逐一吐き出す白い煙は彼女の美しさとあいまって、とても綺麗なものに感じた。煙というより、白い吐息。まるで彼女と煙の二つは美しい芸術品みたいで、この屋上と同じように人々に忘れられ、ここに取り残されているようでもあった。
「あのね…」
ふぅと口から白煙が漏れる。こんなものに何種類以上の発ガン物質が含まれているなんて信じられないほど、緩やかに、優しく流されていく。決して煙草を美化しているわけではない。彼女が美しいからこそ、まわりにあるものも美しくある、といった感じに。それは必然なのだ。
「今の時間調理実習なのよ」
「はぁ…」
彼女は白い溜め息を着いた。自分も、別の意味で溜め息をする。
「今日のメニューは青椒肉絲なの」
「はぁ」
「ピーマンだめなのよね、わたし」
「はぁ…」
彼女は白い溜め息を着いた。自分も、別の意味で溜め息をする。
「今日のメニューは青椒肉絲なの」
「はぁ」
「ピーマンだめなのよね、わたし」
最初にピーマンを見つけた人はこう思ったに違いない。『こんなにみずみずしい輝きを持つ野菜が美味しくないはずがない!』そう思ってかぶりついたに違いない。自分はその偉人に言いたい。あんたは偉いと。でも実際は違ったのだ。すっからかんの中身に、苦味しか存在しない薄い皮、『自分が想像していた、中身は表面に劣るとも勝らないみずみずしさに自然の甘味を合わせ持った、果実と呼んでもなんら謙遜の無いピーマンはどこへ言ってしまったのだ!』と苦味に顔を渋らせながらも叫び雄叫び、ピーマンごときに期待を裏切られて人間不信に陥りながら、毎晩枕を涙で濡らす自分を慰め続け、しまいにはピーマンは甘かったと自分の現実逃避を皆に露呈したピーマンおじさんの末路はとても目を向けられるもの出はなかった。
そんなことはどうでもよく、自分は局この女の仕草にまんまと騙されたわけだ。
そうしてうろたえる姿は、出会いを求める悲しい人が集まる掲示板でサクラという舞い落ちる花びらに邪魔されながら、やっとの思いで初めての相手を見付けるも、夜を沿い遂げいざ朝が明けたとなれば、相手がお腹をさすっていてさあ大変、ゴムの付け方が悪かったのかいやちゃんとつけてたはずだ、でもお腹を摩ってるから妊娠したんだよどうするよ、やれ責任問題だのできっちゃった婚にしてもあんま可愛くねーぞこの女だの、いやいやきっと男を騙して金をとる悪女に違いないだの脳内会議を開いているうちに、相手がそっと口を開いて「やっぱ下痢だ」と呟きお手洗いに駆け込む姿を見て、呆気に取られてる元童貞の姿にそっくりに違いない。
ちなみに余談だが、この元童貞は相手が毎回熱い夜を向かえるごとに腹が冷えて下痢を起こし、それが原因でことごとく男に捨てられるのを知って、可愛そうに思ったかこの女性と付き合い始めてなんと昨年クリスマスに入籍、結婚時に結婚指輪と称して腹巻きをプレゼントし、それはもう彼女に大変喜ばれ、指輪をつけた彼女といつもになく熱い夜を向かえ、指輪のお陰で彼女が二度と腹を下すことは無かったようだ。夫曰く裸に腹巻きはそうとうグッと来るモノがあるらしい。
―話が大分それたので戻そう。
とりあえずあんまりにもすんなり騙されたので言葉を失った。それを言い表したかったのだ。
「多少の好き嫌いはしょうがないでしょ」
白い煙を蒸かしながら彼女は言う。ピーマンおじさんが聞いたら悲しむに違いない。
「そんなことでサボって単位取れなくても知らないですよ」
「いいのよ、いくらサボったって。」
この人は果たして本当に卒業する気があるのだろうか。いや、ないだろう。
「あなたは?」
「ん、オレ?」
「うん」
「何が?」
「だからあなたの理由よ!」
苛立っているのか、煙草を中指と親指で持っている煙草を人指し指でふりふりと揺らす。
「ほら、男って一度くらい悪いことしてみたいじゃないですか」
「あっそう」
苛立たせてしまったせいかもう興味は失せてるようだった。
そうしてうろたえる姿は、出会いを求める悲しい人が集まる掲示板でサクラという舞い落ちる花びらに邪魔されながら、やっとの思いで初めての相手を見付けるも、夜を沿い遂げいざ朝が明けたとなれば、相手がお腹をさすっていてさあ大変、ゴムの付け方が悪かったのかいやちゃんとつけてたはずだ、でもお腹を摩ってるから妊娠したんだよどうするよ、やれ責任問題だのできっちゃった婚にしてもあんま可愛くねーぞこの女だの、いやいやきっと男を騙して金をとる悪女に違いないだの脳内会議を開いているうちに、相手がそっと口を開いて「やっぱ下痢だ」と呟きお手洗いに駆け込む姿を見て、呆気に取られてる元童貞の姿にそっくりに違いない。
ちなみに余談だが、この元童貞は相手が毎回熱い夜を向かえるごとに腹が冷えて下痢を起こし、それが原因でことごとく男に捨てられるのを知って、可愛そうに思ったかこの女性と付き合い始めてなんと昨年クリスマスに入籍、結婚時に結婚指輪と称して腹巻きをプレゼントし、それはもう彼女に大変喜ばれ、指輪をつけた彼女といつもになく熱い夜を向かえ、指輪のお陰で彼女が二度と腹を下すことは無かったようだ。夫曰く裸に腹巻きはそうとうグッと来るモノがあるらしい。
―話が大分それたので戻そう。
とりあえずあんまりにもすんなり騙されたので言葉を失った。それを言い表したかったのだ。
「多少の好き嫌いはしょうがないでしょ」
白い煙を蒸かしながら彼女は言う。ピーマンおじさんが聞いたら悲しむに違いない。
「そんなことでサボって単位取れなくても知らないですよ」
「いいのよ、いくらサボったって。」
この人は果たして本当に卒業する気があるのだろうか。いや、ないだろう。
「あなたは?」
「ん、オレ?」
「うん」
「何が?」
「だからあなたの理由よ!」
苛立っているのか、煙草を中指と親指で持っている煙草を人指し指でふりふりと揺らす。
「ほら、男って一度くらい悪いことしてみたいじゃないですか」
「あっそう」
苛立たせてしまったせいかもう興味は失せてるようだった。
とりあえずオレは座って日向ぼっこでもしようと考えた時、彼女の手にある煙草が目に入った。
そういえば、この状況を教師に見付かったら非常にまずいんじゃないか?彼女の処分は関係無いにしてもこっちまで巻き添えを食らうのは正直御免だ。そう思って歩み寄る。
「ちょっと、何!?」
「この状況を誰かに見られたら困るんですよ」
「何よそれあなたと恋人になったつもりはないわ!」
ちげえ、と心の中で突っ込んだ。
「そうじゃなくて、これ!」
「…これ?って」
そうやって、髪と同じくエメラルドグリーンの色をした瞳を煙草に移す。まるで得対のしれないものを眼前に置かれて興味津々の猫のようだ。
「この状況を教師に見られたら、あなたはともかく、オレにも喫煙の疑いがかかります。あなたはどうでもいいですが、オレまで処分になったら困ります、だから止めてもらいたい」
「サボり魔が何を言う!」
「お前だって―」
こうなることは分かっていた。そして、たいてい男は口喧嘩に負けるのだ。どうでもいい喧嘩ならすぐにでも譲ってやりたいのだが、ここは自分の高校生活がかかっている。あわよくば、大学に進学して毎日ヤりたい放題のアパート生活を一日も早く向かえるには避けては通れない。
そういえば、この状況を教師に見付かったら非常にまずいんじゃないか?彼女の処分は関係無いにしてもこっちまで巻き添えを食らうのは正直御免だ。そう思って歩み寄る。
「ちょっと、何!?」
「この状況を誰かに見られたら困るんですよ」
「何よそれあなたと恋人になったつもりはないわ!」
ちげえ、と心の中で突っ込んだ。
「そうじゃなくて、これ!」
「…これ?って」
そうやって、髪と同じくエメラルドグリーンの色をした瞳を煙草に移す。まるで得対のしれないものを眼前に置かれて興味津々の猫のようだ。
「この状況を教師に見られたら、あなたはともかく、オレにも喫煙の疑いがかかります。あなたはどうでもいいですが、オレまで処分になったら困ります、だから止めてもらいたい」
「サボり魔が何を言う!」
「お前だって―」
こうなることは分かっていた。そして、たいてい男は口喧嘩に負けるのだ。どうでもいい喧嘩ならすぐにでも譲ってやりたいのだが、ここは自分の高校生活がかかっている。あわよくば、大学に進学して毎日ヤりたい放題のアパート生活を一日も早く向かえるには避けては通れない。
しょうがないか。
腹を決めた自分は、そんなことお構い無しに口元へ煙草を運んでいる彼女の右手をがっしりキャッチする。
「ひぅぁ!?」
男が女に勝るものは、力。
藤宮稔が選んだのは実力行使だった。
突然手を掴まれてか、悲鳴じみた鳴き声を上げる。そして、驚いた拍子で抜け落ちた煙草を好かさず右足でクラッシュ。
「あぁぁぁぁ!?ちょっと何すんのよッ!痛ッ!」
少し捻っただけのつもりなのだが、思ったより痛そうだ。現に痛みに顔を歪め、頬を深紅に紅潮させて、くぐもった吐息に時々混ざる短い悲鳴は、まるで自分が違う何かに目覚めそうなほどの興奮を巻き起こす。
と、そんなこと考えてる場合ではない。
「そっちの煙草の箱もおとなしくよこすんだ」
「ゃ、やめッ、あッ、ん―」
文章だけなら確実に犯罪モノだ。現に間近で聞いてる自分でさえ行為の最中かと錯覚するほど―とりあえずこれは早めにとり上げないと。
左手で彼女の右手をがっちり掴んで逃がさないようにし、彼女の左手にある煙草の箱を自分の右手で追い求める。…チクショー、ちょこまかと!
以外に長い間逃走したが、そのかいも虚しく彼女の左手首を捕まえることに成功した。
しかし。
「しまった!」
今は両手が塞がってる。彼女の左手には煙草の箱。どうやっても取り上げれない。安易に彼女の右手を自由にしたらどうなるか分からないから迂濶にも話せない。
しばらくの頓着状態。
「早く降参したらどうかしら?」
「それはどうみてもあんたのセリフだと思うが」
腹を決めた自分は、そんなことお構い無しに口元へ煙草を運んでいる彼女の右手をがっしりキャッチする。
「ひぅぁ!?」
男が女に勝るものは、力。
藤宮稔が選んだのは実力行使だった。
突然手を掴まれてか、悲鳴じみた鳴き声を上げる。そして、驚いた拍子で抜け落ちた煙草を好かさず右足でクラッシュ。
「あぁぁぁぁ!?ちょっと何すんのよッ!痛ッ!」
少し捻っただけのつもりなのだが、思ったより痛そうだ。現に痛みに顔を歪め、頬を深紅に紅潮させて、くぐもった吐息に時々混ざる短い悲鳴は、まるで自分が違う何かに目覚めそうなほどの興奮を巻き起こす。
と、そんなこと考えてる場合ではない。
「そっちの煙草の箱もおとなしくよこすんだ」
「ゃ、やめッ、あッ、ん―」
文章だけなら確実に犯罪モノだ。現に間近で聞いてる自分でさえ行為の最中かと錯覚するほど―とりあえずこれは早めにとり上げないと。
左手で彼女の右手をがっちり掴んで逃がさないようにし、彼女の左手にある煙草の箱を自分の右手で追い求める。…チクショー、ちょこまかと!
以外に長い間逃走したが、そのかいも虚しく彼女の左手首を捕まえることに成功した。
しかし。
「しまった!」
今は両手が塞がってる。彼女の左手には煙草の箱。どうやっても取り上げれない。安易に彼女の右手を自由にしたらどうなるか分からないから迂濶にも話せない。
しばらくの頓着状態。
「早く降参したらどうかしら?」
「それはどうみてもあんたのセリフだと思うが」
「何をこんんッ!」
何もしてないのに声を上げる彼女。そして閃いた。
「そうか、痛みに弱いんだな」
「え?」と呆然とする彼女の両手首を急に強く、キュっと握る。怪我をしないように加減を込めて。
「――ッ?!はぅッ!」
はたから聞いたらエロボイスにしか聞こえない鳴き声と同時に、ビクンと体をよじらせる。そして、二人の足元に落ちる煙草の箱。
「痛いッ…!」
痛さに身をよじらせて、落ちた煙草に気付かない彼女に心の中でそっと謝りながら、踵で箱をおもいっきり後ろに蹴飛ばした。そして心の中でガッツポーズ。オレは勝ったのだ。
手をそっと放してやる。
ガクンと膝をつき、更には手をついてよつんばいの格好になった。なんともあわれな姿なことだ。オレのせいだが。でも決して事後とかそういうのじゃない。そういうのじゃないんだ。
「…なあ、大丈夫か」
「…」
…返事がない。いや、なぜ返事がないんだ。女の子の大事なものでも失ったわけではなかろう。というか『初めては好きな人にあげたいの』とか言ってる子に限って、張り切って守りすぎちゃって死ぬまで開かずの穴になっちゃうんだからいっそのこと早い内に…
「よくも触ってくれたわね…」
「…まぁ、その、ごめんなさい」
とっさに謝罪しなければならないと本能が悟った。彼女の珊瑚礁の海の瞳からクラーケンとかいった怪物でも出てきそうな勢いだったので
その時、チャイムが鳴ると同時に、屋上のドアがガチャガチャと鳴った。身構えて振り向くとそこには―
「早紀、ピーマン抜き青椒肉絲持ってき…」
しばらく時が止まった。
「あ、ひめっち」
「あ、あぁ早紀、どうしてここに?」
ねーさんが壊れた。
しかも、それを言ったら今姉さんの持ってるピーマン抜き青椒肉絲の存在意義が無くなる気がする。
「あは、あははそっか。…じゃあ二人の邪魔しちゃまずいし…」
ひきつった笑みを浮かべる姉さん。駄目だ、螺子が外れた上とんでもない誤解を姉さんはしている。とりあえず蓬山さんに助けてアイコンタクトを送る。
(何とかしてくれ、頼むよ、このままじゃ姉さんは人として壊れちゃう)
(あれ?二人って姉弟なの?)
(そんな呑気なことはいいから早く!)
(しょうがないわね、ひめっちは私の親友だしここは引き下がってあげるわ)
(サンキュ!)
(でも私がひめっちの親友と言うことは私が壊そうと思えば簡単に…)
(そんなことあとでいいから!ほら、姉さんフェンスによじ登ってるよ!)
そういいうと蓬山早紀はブツブツいいながらフェンスをよじ登る藤宮稔の姉、藤宮ひめに説得しに向かった。
何もしてないのに声を上げる彼女。そして閃いた。
「そうか、痛みに弱いんだな」
「え?」と呆然とする彼女の両手首を急に強く、キュっと握る。怪我をしないように加減を込めて。
「――ッ?!はぅッ!」
はたから聞いたらエロボイスにしか聞こえない鳴き声と同時に、ビクンと体をよじらせる。そして、二人の足元に落ちる煙草の箱。
「痛いッ…!」
痛さに身をよじらせて、落ちた煙草に気付かない彼女に心の中でそっと謝りながら、踵で箱をおもいっきり後ろに蹴飛ばした。そして心の中でガッツポーズ。オレは勝ったのだ。
手をそっと放してやる。
ガクンと膝をつき、更には手をついてよつんばいの格好になった。なんともあわれな姿なことだ。オレのせいだが。でも決して事後とかそういうのじゃない。そういうのじゃないんだ。
「…なあ、大丈夫か」
「…」
…返事がない。いや、なぜ返事がないんだ。女の子の大事なものでも失ったわけではなかろう。というか『初めては好きな人にあげたいの』とか言ってる子に限って、張り切って守りすぎちゃって死ぬまで開かずの穴になっちゃうんだからいっそのこと早い内に…
「よくも触ってくれたわね…」
「…まぁ、その、ごめんなさい」
とっさに謝罪しなければならないと本能が悟った。彼女の珊瑚礁の海の瞳からクラーケンとかいった怪物でも出てきそうな勢いだったので
その時、チャイムが鳴ると同時に、屋上のドアがガチャガチャと鳴った。身構えて振り向くとそこには―
「早紀、ピーマン抜き青椒肉絲持ってき…」
しばらく時が止まった。
「あ、ひめっち」
「あ、あぁ早紀、どうしてここに?」
ねーさんが壊れた。
しかも、それを言ったら今姉さんの持ってるピーマン抜き青椒肉絲の存在意義が無くなる気がする。
「あは、あははそっか。…じゃあ二人の邪魔しちゃまずいし…」
ひきつった笑みを浮かべる姉さん。駄目だ、螺子が外れた上とんでもない誤解を姉さんはしている。とりあえず蓬山さんに助けてアイコンタクトを送る。
(何とかしてくれ、頼むよ、このままじゃ姉さんは人として壊れちゃう)
(あれ?二人って姉弟なの?)
(そんな呑気なことはいいから早く!)
(しょうがないわね、ひめっちは私の親友だしここは引き下がってあげるわ)
(サンキュ!)
(でも私がひめっちの親友と言うことは私が壊そうと思えば簡単に…)
(そんなことあとでいいから!ほら、姉さんフェンスによじ登ってるよ!)
そういいうと蓬山早紀はブツブツいいながらフェンスをよじ登る藤宮稔の姉、藤宮ひめに説得しに向かった。
―教室、戻るか。
教室に戻った自分を真っ先に出迎えたのは小金沢伊万里。
「ねえねぇ、体育サボったってマジ?」
「マジ」
高校では違うクラスだが、幼馴染みのせいかいつの間にかつるんでいることが多い。
「あの鬼教官相当怒ってたってよ~」
「まぁそうだろうな」
自分の学年の体育を受け持ってる先生がこれまたアホみたいに厳しいから困ったものだ。
「分かっててなんでサボったのさー」
「知りたい?」
「知りたい!」
「知りたい?」
「知りたい!!」
しばしの沈黙。
「…気持ちが伝わってこんな」
「えぇ~…」
窓際を挟んで廊下でガッカリする伊万里にホレと袋を渡す。
「え、何」
「中見てみろ」
そうすると、しばらく考え込んでから顔を真っ赤にして、変態と叫びやがった。
窓際のオレに、皆からの冷ややかな視線がグサリと刺さる。
「なんでそうなるんだよ!ちょっと貸せ」
少し声を荒げて窓越しに袋を引ったくる。そして力まかせに少々荒く手を突っ込むと、目的の物を見付けてとりだし、高々と上げた。再び声を荒げて述べる。
「ほらみろ、姉のブルマだ!なんだかんだで入れ違ったみたいだが、このことをあいつに言ったらあいつに姉のブルマを穿いて体育やれと言われかねんだろ!」
遅かった。気付くのが。
姉のブルマを堂々と掲げた時に教室に沸き起こった「うわぁ…」という、男子は溜め息まじり、女子は中には悲鳴じみた声さえ出すほどの悲観の声。それと同時にクラス中の皆が一斉に自分から距離を取り、中にはいきおい余って机を引きずったり倒したりするものがいた。自分が振り向いた時には、窓際にいる自分と対岸をなすように、クラス全員が一人残らず向こう岸に避難していた。まるで、教室の真ん中に川が流れているように。クラスの全員が、藤宮稔を犯罪者を見る目で見つめていた。藤宮稔は悟った。オレの高校生活は終わったと。
「ねえねぇ、体育サボったってマジ?」
「マジ」
高校では違うクラスだが、幼馴染みのせいかいつの間にかつるんでいることが多い。
「あの鬼教官相当怒ってたってよ~」
「まぁそうだろうな」
自分の学年の体育を受け持ってる先生がこれまたアホみたいに厳しいから困ったものだ。
「分かっててなんでサボったのさー」
「知りたい?」
「知りたい!」
「知りたい?」
「知りたい!!」
しばしの沈黙。
「…気持ちが伝わってこんな」
「えぇ~…」
窓際を挟んで廊下でガッカリする伊万里にホレと袋を渡す。
「え、何」
「中見てみろ」
そうすると、しばらく考え込んでから顔を真っ赤にして、変態と叫びやがった。
窓際のオレに、皆からの冷ややかな視線がグサリと刺さる。
「なんでそうなるんだよ!ちょっと貸せ」
少し声を荒げて窓越しに袋を引ったくる。そして力まかせに少々荒く手を突っ込むと、目的の物を見付けてとりだし、高々と上げた。再び声を荒げて述べる。
「ほらみろ、姉のブルマだ!なんだかんだで入れ違ったみたいだが、このことをあいつに言ったらあいつに姉のブルマを穿いて体育やれと言われかねんだろ!」
遅かった。気付くのが。
姉のブルマを堂々と掲げた時に教室に沸き起こった「うわぁ…」という、男子は溜め息まじり、女子は中には悲鳴じみた声さえ出すほどの悲観の声。それと同時にクラス中の皆が一斉に自分から距離を取り、中にはいきおい余って机を引きずったり倒したりするものがいた。自分が振り向いた時には、窓際にいる自分と対岸をなすように、クラス全員が一人残らず向こう岸に避難していた。まるで、教室の真ん中に川が流れているように。クラスの全員が、藤宮稔を犯罪者を見る目で見つめていた。藤宮稔は悟った。オレの高校生活は終わったと。
帰り道。
オレは如月みずきと帰り道を共にしていた。
伊万里はブルマの一件で連絡がとれなくて、誤解は結局晴れなかった。
でもみずきはそんなオレを分かってくれるいい子だ。
「みずき、オレにはもうお前しかいない」
「え、そんな急に…!」
「オレのこと分かってくれるのはみずきしかいないんだ」
「う、うん…」
みずきの肩が寄り添ってきたのが感触でわかった。きっと犯罪者扱いされてるオレのこと気遣ってくれてるんだろう…。なんて優しい子だ。
「そ、そういえばさぁ、体育サボって何やってたの?」
「いやー、やることないから屋上行ってて、そしたら蓬山っていう三年の先輩に会って―」
「え?」
みずきが止まった。
オレは如月みずきと帰り道を共にしていた。
伊万里はブルマの一件で連絡がとれなくて、誤解は結局晴れなかった。
でもみずきはそんなオレを分かってくれるいい子だ。
「みずき、オレにはもうお前しかいない」
「え、そんな急に…!」
「オレのこと分かってくれるのはみずきしかいないんだ」
「う、うん…」
みずきの肩が寄り添ってきたのが感触でわかった。きっと犯罪者扱いされてるオレのこと気遣ってくれてるんだろう…。なんて優しい子だ。
「そ、そういえばさぁ、体育サボって何やってたの?」
「いやー、やることないから屋上行ってて、そしたら蓬山っていう三年の先輩に会って―」
「え?」
みずきが止まった。
「蓬山さんって?」
「あー、三年の蓬山早紀って言って…」
「喋った?」
「うん」
「なんかされた?」
「されたと言うよりはしてやっただな。悪いことしてたから懲らしめてやったよ」
そういってから、1分ほど気まずい時間が流れた。なぜそんな空気になったのかオレには分からなかった。
「…うっ、うぅッ」
みずきは泣き始めた。
「おい、大丈夫か…?」
突然の展開に、自分はただ、自分のどこに非があっか探すくらいしかできなかった。
そのとき、彼女はゆっくりと口を開いた。
「あたしのッ、言うこと、うぅ…、よく聞いてッ…!」
みずきは、泣きじゃくりながらも、ゆっくりと話始めた―
「あー、三年の蓬山早紀って言って…」
「喋った?」
「うん」
「なんかされた?」
「されたと言うよりはしてやっただな。悪いことしてたから懲らしめてやったよ」
そういってから、1分ほど気まずい時間が流れた。なぜそんな空気になったのかオレには分からなかった。
「…うっ、うぅッ」
みずきは泣き始めた。
「おい、大丈夫か…?」
突然の展開に、自分はただ、自分のどこに非があっか探すくらいしかできなかった。
そのとき、彼女はゆっくりと口を開いた。
「あたしのッ、言うこと、うぅ…、よく聞いてッ…!」
みずきは、泣きじゃくりながらも、ゆっくりと話始めた―
蓬山家ってのはここらへん一体の元地主で、今はその大半を手放したものの、それで得た資金を元に会社を設立し資金を得て、更には国会議員まで排出し、今や日本の政治を牛耳る一員となったらしい。その蓬山家に産まれた蓬山早紀は、どうやら今の蓬山家当主に大変気に入られて大変厚い保護を受けており、近付くものがいようものなら、社会的存在はおろか、戸籍さえ抹消してこの世の中に居なかったことにされるらしい。だからこそ彼女に近付くものはほとんど居らず、授業に参加しなくても、圧力で単位が貰える仕組みだという。
「…マジかよ、冗談キツイぜ」
ハハハ、とひきつった笑みを浮かべる稔をみて、みずきは思っていた。
「…マジかよ、冗談キツイぜ」
ハハハ、とひきつった笑みを浮かべる稔をみて、みずきは思っていた。
残念ながらあたし一人、いや、友達を含めたとしてもどうしようもできないだろう。むしろ話したことを公開していた。彼はこれからいつ殺されるか分からないまま、人生に希望を抱くことなく生きていくのだ。むしろ日常の何気無い日々の中でいつの間にか死んでたほうが幸せだったろうに。そう思うと、目の前の好きな人の残り好くない人生を踏みにじってしまったように思われて、また自然と涙がこぼれた。そんな自分の頭に、温かいものが置かれる。
「教えてくれてありがとう。お前が悪い分けじゃないから泣き止んでくれよ」
どうして自分が悲しいのに、あたしを慰めるの…。みずきは、泣き続けた。もし、もうすぐ好きな人が死ぬなら。最後まで幸せでいてほしい。あたしでよかったら、あたしの初めてを―
「教えてくれてありがとう。お前が悪い分けじゃないから泣き止んでくれよ」
どうして自分が悲しいのに、あたしを慰めるの…。みずきは、泣き続けた。もし、もうすぐ好きな人が死ぬなら。最後まで幸せでいてほしい。あたしでよかったら、あたしの初めてを―
藤宮は相変わらずひきつった笑みを浮かべていた。それもそのはずである。一年入院してやっと戻ってきたかと思えば、いつの間にか可愛かった幼馴染みは電波っ娘になってしまっていたのだ。顔がよければ宇宙と交信できていいと思ったら大間違いだ。火星語とか喋られたら尚更困る。きっと伊万里やひめあたりが冗談半分で言ったことを間に受けただけだろうだが、こんなにも簡単に人を信じてしまう心はむしろ今のご時世にはデメリットだ。きっとパソコンの使い方を一通り教えて2chのアドレスを教えたら、オカ板に張り付いては事あるごとに「私がサボってたせいで地震が来そうです。皆さん本当にごめんなさい。北関東の玄武の結界が緩んでいます。私のキトウで厄を北に少しずらしましたが三日後に赤い朝焼けのあと世界が終わるでしょう」などと痛い子全快のスレを毎回立てかねない。ああ、みずきがパソコンもったら絶対に2chに行かないように教えとこう。たとえ行っても、PINKの女神スレ以外は許可しない、絶対に。
「ねぇ、みのるぅ…」
思考が一段落したところでみずきが話しかけてきた。すると急に向き合って、その小さな手で自分の手をきゅっと握った。
「ねぇ、みのるぅ…」
思考が一段落したところでみずきが話しかけてきた。すると急に向き合って、その小さな手で自分の手をきゅっと握った。
「あ、明日学校サボってさ、…う、うちに、来ない?」
「…へ?」
「そ、そのっ、学校の間なら親居ないし、その、一杯遊べるっていうかっ」
話の脈絡が全く理解できないでいる自分に話しかけ続けるみずき。
「その、気持いいこととかもっ、もし、もししたいならッ、あたしでいいなら、あたしで…」
もごもご言っててよく聞こえない。だんだんみずきの顔が真っ赤になって来た。ろれつも回らなくなってきている。
「あ、あひゃぁ…今のこ、とッ、忘られて!」
急に大声でそういってみずきは一目散に逃げてしまった。
「…忘られてって、パソコンでよくある誤爆集かよ」
「…へ?」
「そ、そのっ、学校の間なら親居ないし、その、一杯遊べるっていうかっ」
話の脈絡が全く理解できないでいる自分に話しかけ続けるみずき。
「その、気持いいこととかもっ、もし、もししたいならッ、あたしでいいなら、あたしで…」
もごもご言っててよく聞こえない。だんだんみずきの顔が真っ赤になって来た。ろれつも回らなくなってきている。
「あ、あひゃぁ…今のこ、とッ、忘られて!」
急に大声でそういってみずきは一目散に逃げてしまった。
「…忘られてって、パソコンでよくある誤爆集かよ」
家に帰って、みずきはすぐお風呂に入った。両親は共働き、日が暮れてもしばらくは一人ぼっちなのだ。小さい頃は寂しくてしょうがなかったが、近頃は乙女の事情によって両親の帰りの遅いことと一人っ子であることに感謝している。風呂が早いのももちろん乙女の事情。
(結局、言い切らずに帰ってきちゃった…)
お風呂でぷくぷくと泡を立てる。泡は、浮かんではすぐはぜて小気味いい音を響かせている。
みずきとして、稔の前であんな事を言ったのは、稔に言わなくていいことを言った責任を取る反面、稔のことが本当に好きであることも含まれていた。でももし言えたとしても、考えてみれば稔はそういうの嫌いそうだし、偽善がましいと思われるの嫌だし、恥ずかしさで言い切れなかったことは結果オーライだったかもしれない。
(あんなこと言っちゃったし、やっぱ変態って思われてるかも…)
あの時のことを思い出すと、またカァっと顔が燃え上がる。
(結局、言い切らずに帰ってきちゃった…)
お風呂でぷくぷくと泡を立てる。泡は、浮かんではすぐはぜて小気味いい音を響かせている。
みずきとして、稔の前であんな事を言ったのは、稔に言わなくていいことを言った責任を取る反面、稔のことが本当に好きであることも含まれていた。でももし言えたとしても、考えてみれば稔はそういうの嫌いそうだし、偽善がましいと思われるの嫌だし、恥ずかしさで言い切れなかったことは結果オーライだったかもしれない。
(あんなこと言っちゃったし、やっぱ変態って思われてるかも…)
あの時のことを思い出すと、またカァっと顔が燃え上がる。
(こういうときはさっさとアレやって寝ちゃおう)
そう思ってバスタオル一枚でリビングの時計を確かめ、両親が戻ってくるまでだいぶ時間があるのを確認してから、うきうきとバスルームへ戻るのだった。
アレに比べたら、結局藤宮稔の生死ははみずきにとってどうでもいいレベルまでなり下がってしまうのであった。
そう思ってバスタオル一枚でリビングの時計を確かめ、両親が戻ってくるまでだいぶ時間があるのを確認してから、うきうきとバスルームへ戻るのだった。
アレに比べたら、結局藤宮稔の生死ははみずきにとってどうでもいいレベルまでなり下がってしまうのであった。
「ただいまー」
「おかえりみのるくーん、遅いから先風呂入っちゃったよ」
どうやら昼間の精神的苦痛をなんとか乗り越えたみたいだ。ナイスだ蓬山さん。
「あーごめん、みずきと話してたら遅れた」
「ふーん」
「それで聞きたいことがあるんだが、」
「うん」
とりあえずここに座ってくれと座布団を置く。よいしょ、と姉さんは腰を降ろした。
「…で何これ」
姉さんの両のこめかみに、きつく握られた拳がスタンバイしている。
「今からの質問に正直に答えて」
「答えなかったら」
「みずきに蓬山さんの家の事情をかなり婉曲して伝えたよね」
姉さんの疑問を自分の質問で覆い被せる。文句を言おうものなら即ぐりぐりだ。「そうよっていだぁぁぁあ!!」
姉さんは正直に言った。でもそれで許すわけには行かんのだ。可愛い幼馴染みがオカ板に張り付き毎日痛い書き込みばっかするようになっては色々と困る。
「はいおわり」
「いったぁ…!正直に言ったら許すって稔くんいったじゃん」
ぷぃと横を向いて膨れる姉さん。
「みずきはまだ色々と子どもだし、年上である姉さんがしっかりしなきゃだめなの。わかる?」
「うー、へいへい」
そういって横を向きながら返事する姉さんの頭を撫でてやる。
「こ、子どもじゃないんだから止めてよ」
内心嬉しいくせに、顔に出てるんだよと心で呟く。産まれたときから一緒だから、どうも姉の気持ちが分かってしまうのだ。
「んじゃ疲れたし風呂入って今日はもう寝るから」
そういって自分の部屋に戻っていく。ふと背後から声がした。
「稔くん…また一緒にお風呂入れる日が来るといいね…」
訂正。姉の気持ちはやっぱり分からん。
「おかえりみのるくーん、遅いから先風呂入っちゃったよ」
どうやら昼間の精神的苦痛をなんとか乗り越えたみたいだ。ナイスだ蓬山さん。
「あーごめん、みずきと話してたら遅れた」
「ふーん」
「それで聞きたいことがあるんだが、」
「うん」
とりあえずここに座ってくれと座布団を置く。よいしょ、と姉さんは腰を降ろした。
「…で何これ」
姉さんの両のこめかみに、きつく握られた拳がスタンバイしている。
「今からの質問に正直に答えて」
「答えなかったら」
「みずきに蓬山さんの家の事情をかなり婉曲して伝えたよね」
姉さんの疑問を自分の質問で覆い被せる。文句を言おうものなら即ぐりぐりだ。「そうよっていだぁぁぁあ!!」
姉さんは正直に言った。でもそれで許すわけには行かんのだ。可愛い幼馴染みがオカ板に張り付き毎日痛い書き込みばっかするようになっては色々と困る。
「はいおわり」
「いったぁ…!正直に言ったら許すって稔くんいったじゃん」
ぷぃと横を向いて膨れる姉さん。
「みずきはまだ色々と子どもだし、年上である姉さんがしっかりしなきゃだめなの。わかる?」
「うー、へいへい」
そういって横を向きながら返事する姉さんの頭を撫でてやる。
「こ、子どもじゃないんだから止めてよ」
内心嬉しいくせに、顔に出てるんだよと心で呟く。産まれたときから一緒だから、どうも姉の気持ちが分かってしまうのだ。
「んじゃ疲れたし風呂入って今日はもう寝るから」
そういって自分の部屋に戻っていく。ふと背後から声がした。
「稔くん…また一緒にお風呂入れる日が来るといいね…」
訂正。姉の気持ちはやっぱり分からん。
次の日。
「うおおお、またブルマかよぉぉ!」
オレの体操服の袋には、また半ズボンが入ってなくて、また姉のブルマが入っていた。
ちなみにブルマを取り出した瞬間にうわぁ…というお決まりのセリフが流れたが気にしない。朝の一時間目からずっと教室のみんなは自分を避けてる。あの委員長でさえ、朝からずっと対岸で立ちながら授業ノート取ってたし。
とりあえず今回も体育はサボりなので屋上に行くことにした。さすがに今日も調理実習でしかもピーマンが出てくる、なんてことは無いだろう。
薄暗い階段を、昨日のように昇って行く。相変わらず、歩く事に誇りは舞い、風が吹く事に口元を手で押さえる。でも、頂上に付けば優しい風が、きっと自分の呼吸器官を癒してくれるに違いない。
「うおおお、またブルマかよぉぉ!」
オレの体操服の袋には、また半ズボンが入ってなくて、また姉のブルマが入っていた。
ちなみにブルマを取り出した瞬間にうわぁ…というお決まりのセリフが流れたが気にしない。朝の一時間目からずっと教室のみんなは自分を避けてる。あの委員長でさえ、朝からずっと対岸で立ちながら授業ノート取ってたし。
とりあえず今回も体育はサボりなので屋上に行くことにした。さすがに今日も調理実習でしかもピーマンが出てくる、なんてことは無いだろう。
薄暗い階段を、昨日のように昇って行く。相変わらず、歩く事に誇りは舞い、風が吹く事に口元を手で押さえる。でも、頂上に付けば優しい風が、きっと自分の呼吸器官を癒してくれるに違いない。
昨日のようにドアを開け、吹きこむなだらかな風に呼吸をまかせる。何故こんなにも建物の中は汚いのに、外はこんなにも透き通って綺麗なのだろう。
「あら、早かったわね」
そう、昨日も大体こんな感じで人に声をかけられ
「えええええぇ!?蓬山早紀!?なんでここにいるの!?」
昨日と全く同じ場所に、彼女が居た。
「ちょっと、年上に向かってそれは失礼じゃない?」
「あ、すいません蓬山さん」
「なんかしっくり来ないわね」
「んじゃなんて呼べばいいんですか?」
「そうね…」
そういうと、彼女は屋上の真ん中あたりに移動した。昨日のように、偉くなれた手付きで煙草に火をつけ始めた。
「っ…」
思わず眉を細めた。昨日は自分に対して風下だったのに、今日は自分に対してきっかり風上だ。だから、煙草独特の臭いが鼻につく。昨日も今日も、彼女は幾分の迷いもなく風の向きを判断して動いた。だから今日のは恐らくわざとだ。明らかに喧嘩を売ってきている。
ふぅと白い綿をゆっくり吐いて、彼女は言った。
「いい匂いでしょ」
「…正直ヤニ臭くて堪りません。…今日も調理実習なんですか?」
「そうだけど、正確にはたった今さっきそうなったの」
「…それはどういう?」
理解しかねた。わけわかめだ。
「お祖父様に、この時間を調理実習にするように頼んだの。もちろんメニューは青椒肉絲よ」
まさか。
「稔くん、あなた鈍感。」
「なっ…」
「蓬山家の人間にとって、この時間を青椒肉絲の調理実習に代えて、あなたの半ズボンをブルマに摩り替えることくらい造作もないのよ」
ってことはみずきの言ったことはあながち間違いじゃないってことか…?だとしたらオレは…!
彼女は見下すように白い息を吹きかけてきた。
「今日は本気よ。昨日みたいな生易しい勝負するつもりはないわ」
微かに拳が震えた。それは恐怖におののく小動物か、あるいは怒りにうち震える古の猛者のものか
「…あんたが勝ったら?」
「そうね、昨日は負けたことだし、大まけにまけて女王様」
「じゃあオレが勝ったら奴隷だな」
―オレには、自分の為に泣いてくれた女の子がいた。この勝負は、みずきのために。あいつの溢した涙を、勝利の杯で"すくう"のだ。
「決まりね―」
「あら、早かったわね」
そう、昨日も大体こんな感じで人に声をかけられ
「えええええぇ!?蓬山早紀!?なんでここにいるの!?」
昨日と全く同じ場所に、彼女が居た。
「ちょっと、年上に向かってそれは失礼じゃない?」
「あ、すいません蓬山さん」
「なんかしっくり来ないわね」
「んじゃなんて呼べばいいんですか?」
「そうね…」
そういうと、彼女は屋上の真ん中あたりに移動した。昨日のように、偉くなれた手付きで煙草に火をつけ始めた。
「っ…」
思わず眉を細めた。昨日は自分に対して風下だったのに、今日は自分に対してきっかり風上だ。だから、煙草独特の臭いが鼻につく。昨日も今日も、彼女は幾分の迷いもなく風の向きを判断して動いた。だから今日のは恐らくわざとだ。明らかに喧嘩を売ってきている。
ふぅと白い綿をゆっくり吐いて、彼女は言った。
「いい匂いでしょ」
「…正直ヤニ臭くて堪りません。…今日も調理実習なんですか?」
「そうだけど、正確にはたった今さっきそうなったの」
「…それはどういう?」
理解しかねた。わけわかめだ。
「お祖父様に、この時間を調理実習にするように頼んだの。もちろんメニューは青椒肉絲よ」
まさか。
「稔くん、あなた鈍感。」
「なっ…」
「蓬山家の人間にとって、この時間を青椒肉絲の調理実習に代えて、あなたの半ズボンをブルマに摩り替えることくらい造作もないのよ」
ってことはみずきの言ったことはあながち間違いじゃないってことか…?だとしたらオレは…!
彼女は見下すように白い息を吹きかけてきた。
「今日は本気よ。昨日みたいな生易しい勝負するつもりはないわ」
微かに拳が震えた。それは恐怖におののく小動物か、あるいは怒りにうち震える古の猛者のものか
「…あんたが勝ったら?」
「そうね、昨日は負けたことだし、大まけにまけて女王様」
「じゃあオレが勝ったら奴隷だな」
―オレには、自分の為に泣いてくれた女の子がいた。この勝負は、みずきのために。あいつの溢した涙を、勝利の杯で"すくう"のだ。
「決まりね―」
賽は、投げられた。
あとがきらしきもの
「はぁッ、うぅんッ」
「フン、体は正直なようだな…それッ!」
「いやぁッ―ぁぁぁぁああああんッ!!」
ポロッ。
「はいオレの勝ち。」
そういって煙草の箱を拾う自分。
「そんなぁ…」
ヘナヘナと座り込む女性。
「元気出せよ、『ド・レ・イ』」
「嫌、嫌よ、いゃぁ…」
「蓬山家の人間たるものが、そんな無様な呼ばれでざまぁないですね」
オレは勝負に勝った。もっと言えば、最初から勝ちは決まっていた。投げられた賽は、どの目にも1が書かれていたのである。手首をちょっと握るだけで堕ちる姿は、彼女に興奮を覚えるばかりか、征服欲が満たされていらぬ性癖に目覚めさせられそうだった。それでも、まんざらではなかったが。
そういって煙草の箱を拾う自分。
「そんなぁ…」
ヘナヘナと座り込む女性。
「元気出せよ、『ド・レ・イ』」
「嫌、嫌よ、いゃぁ…」
「蓬山家の人間たるものが、そんな無様な呼ばれでざまぁないですね」
オレは勝負に勝った。もっと言えば、最初から勝ちは決まっていた。投げられた賽は、どの目にも1が書かれていたのである。手首をちょっと握るだけで堕ちる姿は、彼女に興奮を覚えるばかりか、征服欲が満たされていらぬ性癖に目覚めさせられそうだった。それでも、まんざらではなかったが。
「ねぇ、その呼び名だけはどうにもならない?」
「言い出しっぺはあなたじゃないですか」
これはただ単にあだ名を決める戦いだったのだ。彼女が勝ったら女王様、自分が勝ったら奴隷、ようするに命名権の奪い合い。それに晴れて勝った自分は、目の前で落ち込み助けを求める女性に、どんなひわいな名前を付けたって構わない権利をついさっき手に入れた。
「じゃぁあれだわ、あなたのその勝ちを私が買うわ」
「勝ちだけに買った!ってか、寒いな」
「私はそんなセンスない冗談言わないわ」
しばらくの沈黙。
「…で、いくらで買い取りになられます?」
「そうね、希望とかあるかしら」
希望、か。折角だからなんか高いものでも買うか?とも思ったが、相手はあの蓬山家のご令嬢。学校にも顔がきくみたいだし、ここらは金で買えないものを頼むのも面白そうだ。
「言い出しっぺはあなたじゃないですか」
これはただ単にあだ名を決める戦いだったのだ。彼女が勝ったら女王様、自分が勝ったら奴隷、ようするに命名権の奪い合い。それに晴れて勝った自分は、目の前で落ち込み助けを求める女性に、どんなひわいな名前を付けたって構わない権利をついさっき手に入れた。
「じゃぁあれだわ、あなたのその勝ちを私が買うわ」
「勝ちだけに買った!ってか、寒いな」
「私はそんなセンスない冗談言わないわ」
しばらくの沈黙。
「…で、いくらで買い取りになられます?」
「そうね、希望とかあるかしら」
希望、か。折角だからなんか高いものでも買うか?とも思ったが、相手はあの蓬山家のご令嬢。学校にも顔がきくみたいだし、ここらは金で買えないものを頼むのも面白そうだ。
「決まった?」
しばらく考え込む。
「んー、そうだな、あなたみたいにサボっても単位とれるようにしてください、あと赤点と補修免除も頼みます」
「注文多いわね」
「…そこをなんとか頼みます!」
両手を合わせ、目をつむって頭を下げる。
「さすがにそれだと不釣り合いすぎるわね…」
しかし、こんな頼みができるのはこの先千回輪廻転生しても無いだろう。だから食い下がる。
「頼むよ!」
「…いい事思い付いたわ」
その言葉に思わず目を開けて、耳を傾ける自分。
「これから毎日この時間に私と戦って、卒業までずっと勝てたら全部の単位ゲット。一度でも負けたり、来なかったりで不戦勝になったら即退学。よし、決まりね!」
「ちょ、それはいくらなんでも無理矢理過ぎる!一回負けたら留年って酷すぎないか?!」
あまりの理不尽なハイリスクに思わず声が大きくなる。
しばらく考え込む。
「んー、そうだな、あなたみたいにサボっても単位とれるようにしてください、あと赤点と補修免除も頼みます」
「注文多いわね」
「…そこをなんとか頼みます!」
両手を合わせ、目をつむって頭を下げる。
「さすがにそれだと不釣り合いすぎるわね…」
しかし、こんな頼みができるのはこの先千回輪廻転生しても無いだろう。だから食い下がる。
「頼むよ!」
「…いい事思い付いたわ」
その言葉に思わず目を開けて、耳を傾ける自分。
「これから毎日この時間に私と戦って、卒業までずっと勝てたら全部の単位ゲット。一度でも負けたり、来なかったりで不戦勝になったら即退学。よし、決まりね!」
「ちょ、それはいくらなんでも無理矢理過ぎる!一回負けたら留年って酷すぎないか?!」
あまりの理不尽なハイリスクに思わず声が大きくなる。
「いいじゃない、あなたずっと勝ってるんだから」
確かにそう言われてみれば、向こう50年は怪我や病気しないかぎり負けのまの字も見えない。まぁ勝つのは楽だし、勝負もまんざらでもないからいいか。
「…分かった、乗るよ乗る」
「ちなみに一日のノルマは5勝ね!」
「んなぁ!」
悪戯な笑みで理不尽な条件を提示され、どうせ条件を飲むしかないので追い掛ける。
「それと!私のことは先輩って呼びなさい!」
ちょこまかと逃げながら先輩は叫んだ。それに呼応するように自分も叫ぶ。
「待て、このクソ先輩!!」
「誰がクソ―へぁぶッ!」
後ろを向いて注意しようとしたら、どうやら前に注意が行ってなかったようだ。ずでっと派手に転んだ。そこに容赦なくのしかかり、起き上がれないように肩を捻りあげる。
「あぁ、んはぁッ」
ポロッ。
「これで二勝目」
一日のノルマは5勝。
残り、あと3勝。
確かにそう言われてみれば、向こう50年は怪我や病気しないかぎり負けのまの字も見えない。まぁ勝つのは楽だし、勝負もまんざらでもないからいいか。
「…分かった、乗るよ乗る」
「ちなみに一日のノルマは5勝ね!」
「んなぁ!」
悪戯な笑みで理不尽な条件を提示され、どうせ条件を飲むしかないので追い掛ける。
「それと!私のことは先輩って呼びなさい!」
ちょこまかと逃げながら先輩は叫んだ。それに呼応するように自分も叫ぶ。
「待て、このクソ先輩!!」
「誰がクソ―へぁぶッ!」
後ろを向いて注意しようとしたら、どうやら前に注意が行ってなかったようだ。ずでっと派手に転んだ。そこに容赦なくのしかかり、起き上がれないように肩を捻りあげる。
「あぁ、んはぁッ」
ポロッ。
「これで二勝目」
一日のノルマは5勝。
残り、あと3勝。