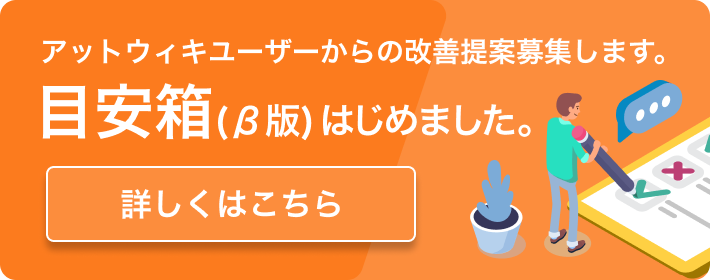「伊万里14」(2008/09/27 (土) 15:58:56) の最新版変更点
追加された行は緑色になります。
削除された行は赤色になります。
< 【[[back>伊万里13]]】
// 【[[next>]]】 >
*注意
>性的表現を連想させたり、性的表現そのものが含まれる作品です
>これらに苦手意識や嫌悪感を抱く方が見るのはお勧めしませんが、文章なので18禁ではありません
「ひぁ……みの、りんっ……!」
仄暗い部屋の中、噛み殺しきれなかった嬌声が響く。
ぬいぐるみに囲まれた部屋の中央、小さなベッドに身を横たえながら、小金沢伊万里は大きく息をついた。
この場に彼女を知っているものがいれば、目を疑っただろう。
『そういう系』の話題には拒絶反応を示す彼女が、まさかこのような行為に及んでいようとは。
しかし、今の彼女はいつもの彼女ではない。その頭にあるのは、愛しい愛しい想い人のことだけ。
一緒の登校は彼の姉に妨害され、
休み時間には既に親友が談笑していて、
昼は彼が上級生を手伝っていて、
帰りは一緒に帰ろうとすれば、彼は忘れ物をして引き返し、そのまま教室で学級委員長と……。
「んぅぅぅっ!」
彼だけのために今まで秘めてきた部分を、強くつねりあげる。
きゅうっと体に力が入り、顔をうずめていた枕が湿り気を帯びていく。
せつなかった。
熱っぽい喘ぎ声は、嗚咽でもあった。それに重なるように、くちゅくちゅと卑猥な水音が混じり始めた。
とろとろと見えざる炎が神経を炙る。内に育っていく悦楽の芽。
しかし伊万里はその性格ゆえに、少なからず罪悪感を抱かずにはいられなかった。
「んくっ……ボクっ、てば、こんな……に」
粘液をまとった指を、胸に抱いたテディベアに見せつける。
何年も何年も想いをぶつけてきた、彼女にとっては思い出の品。幼い頃に他ならない彼から貰ったプレゼントなのだ。
「あ、んっ……ボク、の……」
自分は想い人に痴態を晒している――そんな異常な妄想がふと脳裏を掠める。
同時に押し寄せてきた快楽の波が、躊躇わせていた罪悪感を押し流していく。
怯えたように動いていた指は、いまやかつてない激しさで上へ下へ往復し始めた。下着などとうに穿いていない。
直接触れると、その刺激はまた格別だった。
「ひぃあぁぁぁ……い、いっ!?」
もうどうでもよい。この、張り裂けそうな胸の苦しみと、やり場のないもどかしさ。
それを忘れさせてくれるならば、魔の悦楽であってもかまわない。
それに――
「みのりん……っ!」
小さな窓に向かって呟く。普段は閉め切っているカーテンは、今日このときに限っては全開だった。
彼女と彼の家は隣同士である。その気になれば、相手の部屋を覗くくらい造作もない。
色気のない下着のみを身に着けた、半裸の肢体。
あられもない姿を見られるかもしれない――だが、それをどこかで期待している自分がいることに、伊万里は気づき始めていた。
幼馴染という名の殻を打ち破りたかった。恋人になりたかった。
いつも考え、いつもできない。失敗したら――そればかりが考えを占めてしまうのだ。
そして、その可能性は低くない。彼の周りには魅力的な女性がたくさんいるのだから……。
異性への興味でもかまわない、せめて彼を惹きつけられれば。
今まで彼の幼馴染をやってきて、性別の違いを考えさせられたことがなかったとは言わない。
自分の貧相な肢体にコンプレックスを抱いていることも認めよう。
それでも、これほどまでに『女』を意識したことはなかった。
「ひぁう……くんっ!」
募る苛立ちに胸を握りつぶす。強すぎる刺激に痛みさえ感じた。
薄い薄い胸。掴むと言うのもおこがましい、慎ましやかな隆起。女性的な柔らかさはなく、芯でも入っているかのように固い。
――みのりんは……。
こんな貧相な肢体でも振り向いてくれるのだろうか?
いや、考えてみれば、彼も男なのだ。人並みに性欲はあるだろうし、ならば女性に求めるのは……。
――イヤ、イヤ、だよぅ……。
そんなことは認めたくなかった。
指が乱暴に陰核を押し潰す。
「ひきぁっ!?」
――助けて、みのりん……。
痛々しいほどに歪む蕾。遅れて悦楽の波が背筋を駆け上った。
彼の名を叫びながら、テディベアを強く強く逃がさないように抱きしめる。
――ボクってば、みのりんを……。
悩みも苦しみもない。すべて消える。視界は真っ白になる。そして二人っきり。目の前には彼が……。
――アイ、シテ……。
< 【[[back>伊万里13]]】
// 【[[next>]]】 >
< 【[[back>伊万里13]]】 【[[next>伊万里15]]】 >
*注意
>性的表現を連想させたり、性的表現そのものが含まれる作品です
>これらに苦手意識や嫌悪感を抱く方が見るのはお勧めしませんが、文章なので18禁ではありません
「ひぁ……みの、りんっ……!」
仄暗い部屋の中、噛み殺しきれなかった嬌声が響く。
ぬいぐるみに囲まれた部屋の中央、小さなベッドに身を横たえながら、小金沢伊万里は大きく息をついた。
この場に彼女を知っているものがいれば、目を疑っただろう。
『そういう系』の話題には拒絶反応を示す彼女が、まさかこのような行為に及んでいようとは。
しかし、今の彼女はいつもの彼女ではない。その頭にあるのは、愛しい愛しい想い人のことだけ。
一緒の登校は彼の姉に妨害され、
休み時間には既に親友が談笑していて、
昼は彼が上級生を手伝っていて、
帰りは一緒に帰ろうとすれば、彼は忘れ物をして引き返し、そのまま教室で学級委員長と……。
「んぅぅぅっ!」
彼だけのために今まで秘めてきた部分を、強くつねりあげる。
きゅうっと体に力が入り、顔をうずめていた枕が湿り気を帯びていく。
せつなかった。
熱っぽい喘ぎ声は、嗚咽でもあった。それに重なるように、くちゅくちゅと卑猥な水音が混じり始めた。
とろとろと見えざる炎が神経を炙る。内に育っていく悦楽の芽。
しかし伊万里はその性格ゆえに、少なからず罪悪感を抱かずにはいられなかった。
「んくっ……ボクっ、てば、こんな……に」
粘液をまとった指を、胸に抱いたテディベアに見せつける。
何年も何年も想いをぶつけてきた、彼女にとっては思い出の品。幼い頃に他ならない彼から貰ったプレゼントなのだ。
「あ、んっ……ボク、の……」
自分は想い人に痴態を晒している――そんな異常な妄想がふと脳裏を掠める。
同時に押し寄せてきた快楽の波が、躊躇わせていた罪悪感を押し流していく。
怯えたように動いていた指は、いまやかつてない激しさで上へ下へ往復し始めた。下着などとうに穿いていない。
直接触れると、その刺激はまた格別だった。
「ひぃあぁぁぁ……い、いっ!?」
もうどうでもよい。この、張り裂けそうな胸の苦しみと、やり場のないもどかしさ。
それを忘れさせてくれるならば、魔の悦楽であってもかまわない。
それに――
「みのりん……っ!」
小さな窓に向かって呟く。普段は閉め切っているカーテンは、今日このときに限っては全開だった。
彼女と彼の家は隣同士である。その気になれば、相手の部屋を覗くくらい造作もない。
色気のない下着のみを身に着けた、半裸の肢体。
あられもない姿を見られるかもしれない――だが、それをどこかで期待している自分がいることに、伊万里は気づき始めていた。
幼馴染という名の殻を打ち破りたかった。恋人になりたかった。
いつも考え、いつもできない。失敗したら――そればかりが考えを占めてしまうのだ。
そして、その可能性は低くない。彼の周りには魅力的な女性がたくさんいるのだから……。
異性への興味でもかまわない、せめて彼を惹きつけられれば。
今まで彼の幼馴染をやってきて、性別の違いを考えさせられたことがなかったとは言わない。
自分の貧相な肢体にコンプレックスを抱いていることも認めよう。
それでも、これほどまでに『女』を意識したことはなかった。
「ひぁう……くんっ!」
募る苛立ちに胸を握りつぶす。強すぎる刺激に痛みさえ感じた。
薄い薄い胸。掴むと言うのもおこがましい、慎ましやかな隆起。女性的な柔らかさはなく、芯でも入っているかのように固い。
――みのりんは……。
こんな貧相な肢体でも振り向いてくれるのだろうか?
いや、考えてみれば、彼も男なのだ。人並みに性欲はあるだろうし、ならば女性に求めるのは……。
――イヤ、イヤ、だよぅ……。
そんなことは認めたくなかった。
指が乱暴に陰核を押し潰す。
「ひきぁっ!?」
――助けて、みのりん……。
痛々しいほどに歪む蕾。遅れて悦楽の波が背筋を駆け上った。
彼の名を叫びながら、テディベアを強く強く逃がさないように抱きしめる。
――ボクってば、みのりんを……。
悩みも苦しみもない。すべて消える。視界は真っ白になる。そして二人っきり。目の前には彼が……。
――アイ、シテ……。
< 【[[back>伊万里13]]】 【[[next>伊万里15]]】 >
表示オプション
横に並べて表示:
変化行の前後のみ表示: