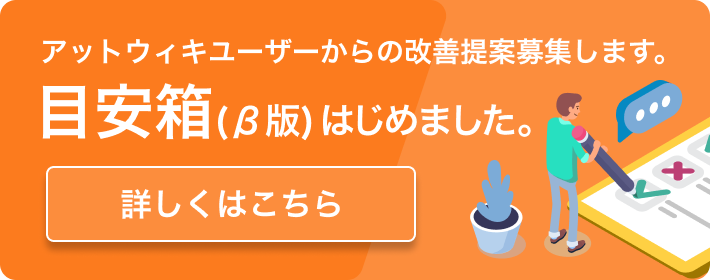「→藤宮ひめ」(2009/06/06 (土) 01:07:16) の最新版変更点
追加された行は緑色になります。
削除された行は赤色になります。
**夢のS S ○ロ描写アリなので注意! 1/1
ずっと一緒に居た姉さんの表情、あれは嘘なんて微塵も無い本気の表情だった。
姉さんからの「ずっと一緒に居て下さい」という熱いラブコールを受けて一日、まだ信じられない気持ちが強い。
一つ屋根の下住んでいるにも関わらず、俺の一方的な気まずさからずっと顔を合わせていない。
何日かたった。まだ姉さんとは殆ど会話をしていない。
それは見かけたり声をかけられそうになったら姉さんから逃げているから…。
「稔…」
学校帰り、後ろから姉さんの声が聞こえたが俺は走り出した。
「どうしてダメなの?」
そんな声が聞こえた気がした。だけど俺は走るスピードを変えることなくそこから走り去る。
家についたらすぐに俺は部屋に閉じこもる。
「このままじゃいけない」
そう独り言をつぶやいていつの間にか眠ってしまった。
目覚めると体が妙に軽く感じる。ふと時計を見るとまだ7時前だった。
「風邪でも引いたかな…」
とりあえず昨日までのことを謝る為にもとびっきりの朝ご飯を作る事にした。
キッチンに向かうと既に姉さんがいた。フライパン片手に鼻歌交じりで朝から何か作っていた。
「姉さん」
呼びかけてみるが返事が無い。
「姉さん?」
もう一度呼びかけてみるがやはり返事が無い。
「いつ…………緒…食べ………」
何か歌っているようだけど完全には聞き取れない。
ふとキッチンのテーブルを見ると大きな肉のブロックがあった。
見たことがある塊のような気がしたが、どうにも思い出せない。
姉さん、いつになったら俺に気がついてくれますか…?
**まるでイリュージョン
「やあ(´・ω・`)
どうしたの? まるでイリュージョンでも見たか、って感じ。
ああ、この服? ○○(運悪く競合した他ヒロイン)ちゃんに借りたの。ちょっと大きいけど……。
ん? ○○ちゃんには私の服を来て帰ってもらったよ。これは姉弟の問題だしね。
お姉ちゃん、悲しいなあ……。
稔君が自分の部屋に鍵をかけるようになったのは気にしてなかったんだよ。この部屋は元々お姉ちゃんからのお下がりだもの。その気になれば合い鍵くらい、ね。
どうしてバレないと思ったのかな。稔の部屋から、椅子が軋む音と本棚が揺れる音が同時に聞こえるんだよ? お姉ちゃんを嘗めてないかなぁ……。
そんなつもりじゃない? ……まだ分かってないみたいだね。
健全とか不健全とかじゃないの。稔がまだ私から離れようとしているのが許せないの」
とりあえず暇つぶしの思いつき。
この間、首にはキリキリと爪痕が……
**無題
厚手のベッドの上で横になっている。
俺はどうやら、もうじき死ぬらしい。
西側に一つ窓の付いた部屋で、昼の間は薄暗い。
朝などはいつ日の出た事か分からない。
ただ夕方になると、深紅の血を透かした様な色で、一人きりの部屋が一面に染まる。
原因不明の病気なのだという。
医者はさじをなげた。
それで、自室で一人横になって、僅かな時間を過ごしている。
感染力は弱く、同じ部屋で長い時間を過ごさぬ限り、他者にうつる心配は無いらしい。
それでも俺を訪ねて来る者は誰一人なかった。
当然だと思う。
死に至る病を有した者と、例えばコップ一杯分の唾液を交換すれば、感染したとする。
会話やくしゃみで飛散するつば程度なら問題ない、と言われた所で、実際は不安になる者の方が多いだろう。
夕日の紅が薄らいで、やがて夜が来た。
部屋のドアが控えめにノックされる。
「ただいま稔くん、お姉ちゃんだよ~。
起きてるかな?」
「おかえり、姉さん」
今では此処のただ一人となった訪問者。
姉さんが照明のスイッチを入れ、ベッドの脇へ添えられたチェアに腰を下ろした。
「あのね稔くん、今日は体育の時間にね……」
体も弱り、外出すら出来なくなった俺の退屈を紛らわそうと、学校で起きた珍事や騒動の数々を、姉さんは今日も面白おかしく聞かせてくれる。
相づちを打ちながらその声に耳を傾ける時間こそが、今の俺に残された唯一の幸福だった。
伊万里はどうしてるかな、とふと考える。
姉さんの話に彼女の名は出てこない。
いや、彼女だけでない、先輩、委員長、みずき……一度は俺を見舞いに訪れても良さそうな人達の話が、その口から語られる事はない。
きっと、姉さんは俺を気遣ってくれているのだ。
別に裏切られただなんて思っちゃいない。
が、病を患ってから一度も顔を見せてくれないというのは、やはり寂しさの胸来するものがあった。
「さて、お姉ちゃんはそろそろ夕ご飯の支度。
稔君、何か食べたい物はある~?」
「姉さんが作ってくれるものなら、なんでも」
いつも通りの受け答えに微笑むと、姉さんはそっと照明を落とし、部屋を出て行った。
彼女の体温がまだベッドの脇に残されていて、手を伸ばせばそれを掴み取れそうな気さえする。
階下で姉さんが料理を始めたのだろう、ガチャガチャと金属音が聞こえてきた。
俺の生活の全ては姉さんに支えられていた。
いや、今では姉さんそのものが俺の全てになったと言っていい。
肉体も精神も含め、否応無しに彼女へと依存していく。
いよいよ最後の刻が来た。
姉さんは学校を休み、朝からずっと俺の手を握ったまま、何も言わない。
部屋にはやはり俺と姉さんの二人きりだった。
「実くん、苦しいの?」
ぜえぜえという俺のあえぎが、彼女の胸を刺すのだろうか。
ゆっくり目を開き、姉さんの顔を見やると、そこには沈痛の色を浮かべた彼女の顔が――無い。
笑っている。
慈母のように。
「大丈夫だよ。
あのね、息が苦しいのは最後の数分だけ。
お姉ちゃんの調合は完璧なんだから!
今までだって、苦痛らしい苦痛は何一つ無かったでしょ?
ただ体に力が入らなくなるだけで」
ああそうか、とようやく納得する。
「致死量の計算もばっちり!
mgのズレだって無いよ。
もうすぐその苦しさも無くなって、心拍も段々ゆっくりになって……そうして、眠るように死ねるの」
だから、原因不明の病だったのだ。
心音が次第に弱まっていく。
息苦しさも消えてきた。
「そしたら稔くんを一つ一つ、丁寧にホルマリンへ漬けるの。
永遠に綺麗なままでいられるよ?
それをお姉ちゃんだけが眺めるの、眺めてていいの。
毎日毎日、朝も昼も夜も……『お姉ちゃんだけのもの』になった稔くんを見つめて過ごすの」
意識もそろそろと遠のき始める。
誰も部屋へ訪ねに来てくれなかったのは、きっと。
「これでやっと本当の『二人きり』になれたね、稔くん」
**原文
→藤宮ひめ
(黒背景)
いや、実の姉は…まあいいか。
稔「俺、姉さんが…ひめの事が好きだ!姉弟とか、家族とかそういう好きじゃないんだ。分かって…くれるかな?」
ひめ「分かってるよ。稔くんのことはおねえちゃんが一番分かってるんだから。おねえちゃんも稔くんの事、大好きだよ!」
――数ヵ月後
足元から風が吹き抜ける音がする。どうやら高い所に俺達はいるらしい。
ひめ「綺麗な夜景だね、稔くん」
稔「え?う、うん」
俺には真っ暗闇しか見えていないが、姉さんには何かが見えているのだろう。ここは合わせておいてあげよう。
ひめ「ふぅん。何が見える?ねぇ、何?どう綺麗なの?」
稔「え、ええと…その…」
ひめ「嘘はいけないなぁ稔くん。おねえちゃんに嘘つく稔くんはこうしちゃうんだから」
ドン
小柄で華奢な姉とは思えない力で僕の体は深い闇へと放り出された。
何も見えない闇の中を僕の体は落ちていく。
稔「うわあ!」
いつの間にか少し眠ってしまったらしい。全く馬鹿馬鹿しい妄想をしてしまったもんだ。
近親相姦はあり得ないよ、まったく。明日どう姉さんと接すればいいんだ。
俺は姿勢を正し、改めて寝る事にした。
稔「でも…なんだか妙にリアルな夢だったな…」
**夢のS S ○ロ描写アリなので注意! 1/1
ずっと一緒に居た姉さんの表情、あれは嘘なんて微塵も無い本気の表情だった。
姉さんからの「ずっと一緒に居て下さい」という熱いラブコールを受けて一日、まだ信じられない気持ちが強い。
一つ屋根の下住んでいるにも関わらず、俺の一方的な気まずさからずっと顔を合わせていない。
何日かたった。まだ姉さんとは殆ど会話をしていない。
それは見かけたり声をかけられそうになったら姉さんから逃げているから…。
「稔…」
学校帰り、後ろから姉さんの声が聞こえたが俺は走り出した。
「どうしてダメなの?」
そんな声が聞こえた気がした。だけど俺は走るスピードを変えることなくそこから走り去る。
家についたらすぐに俺は部屋に閉じこもる。
「このままじゃいけない」
そう独り言をつぶやいていつの間にか眠ってしまった。
目覚めると体が妙に軽く感じる。ふと時計を見るとまだ7時前だった。
「風邪でも引いたかな…」
とりあえず昨日までのことを謝る為にもとびっきりの朝ご飯を作る事にした。
キッチンに向かうと既に姉さんがいた。フライパン片手に鼻歌交じりで朝から何か作っていた。
「姉さん」
呼びかけてみるが返事が無い。
「姉さん?」
もう一度呼びかけてみるがやはり返事が無い。
「いつ…………緒…食べ………」
何か歌っているようだけど完全には聞き取れない。
ふとキッチンのテーブルを見ると大きな肉のブロックがあった。
見たことがある塊のような気がしたが、どうにも思い出せない。
姉さん、いつになったら俺に気がついてくれますか…?
**まるでイリュージョン
「やあ(´・ω・`)
どうしたの? まるでイリュージョンでも見たか、って感じ。
ああ、この服? ○○(運悪く競合した他ヒロイン)ちゃんに借りたの。ちょっと大きいけど……。
ん? ○○ちゃんには私の服を来て帰ってもらったよ。これは姉弟の問題だしね。
お姉ちゃん、悲しいなあ……。
稔君が自分の部屋に鍵をかけるようになったのは気にしてなかったんだよ。この部屋は元々お姉ちゃんからのお下がりだもの。その気になれば合い鍵くらい、ね。
どうしてバレないと思ったのかな。稔の部屋から、椅子が軋む音と本棚が揺れる音が同時に聞こえるんだよ? お姉ちゃんを嘗めてないかなぁ……。
そんなつもりじゃない? ……まだ分かってないみたいだね。
健全とか不健全とかじゃないの。稔がまだ私から離れようとしているのが許せないの」
とりあえず暇つぶしの思いつき。
この間、首にはキリキリと爪痕が……
**無題
厚手のベッドの上で横になっている。
俺はどうやら、もうじき死ぬらしい。
西側に一つ窓の付いた部屋で、昼の間は薄暗い。
朝などはいつ日の出た事か分からない。
ただ夕方になると、深紅の血を透かした様な色で、一人きりの部屋が一面に染まる。
原因不明の病気なのだという。
医者はさじをなげた。
それで、自室で一人横になって、僅かな時間を過ごしている。
感染力は弱く、同じ部屋で長い時間を過ごさぬ限り、他者にうつる心配は無いらしい。
それでも俺を訪ねて来る者は誰一人なかった。
当然だと思う。
死に至る病を有した者と、例えばコップ一杯分の唾液を交換すれば、感染したとする。
会話やくしゃみで飛散するつば程度なら問題ない、と言われた所で、実際は不安になる者の方が多いだろう。
夕日の紅が薄らいで、やがて夜が来た。
部屋のドアが控えめにノックされる。
「ただいま稔くん、お姉ちゃんだよ~。
起きてるかな?」
「おかえり、姉さん」
今では此処のただ一人となった訪問者。
姉さんが照明のスイッチを入れ、ベッドの脇へ添えられたチェアに腰を下ろした。
「あのね稔くん、今日は体育の時間にね……」
体も弱り、外出すら出来なくなった俺の退屈を紛らわそうと、学校で起きた珍事や騒動の数々を、姉さんは今日も面白おかしく聞かせてくれる。
相づちを打ちながらその声に耳を傾ける時間こそが、今の俺に残された唯一の幸福だった。
伊万里はどうしてるかな、とふと考える。
姉さんの話に彼女の名は出てこない。
いや、彼女だけでない、先輩、委員長、みずき……一度は俺を見舞いに訪れても良さそうな人達の話が、その口から語られる事はない。
きっと、姉さんは俺を気遣ってくれているのだ。
別に裏切られただなんて思っちゃいない。
が、病を患ってから一度も顔を見せてくれないというのは、やはり寂しさの胸来するものがあった。
「さて、お姉ちゃんはそろそろ夕ご飯の支度。
稔君、何か食べたい物はある~?」
「姉さんが作ってくれるものなら、なんでも」
いつも通りの受け答えに微笑むと、姉さんはそっと照明を落とし、部屋を出て行った。
彼女の体温がまだベッドの脇に残されていて、手を伸ばせばそれを掴み取れそうな気さえする。
階下で姉さんが料理を始めたのだろう、ガチャガチャと金属音が聞こえてきた。
俺の生活の全ては姉さんに支えられていた。
いや、今では姉さんそのものが俺の全てになったと言っていい。
肉体も精神も含め、否応無しに彼女へと依存していく。
いよいよ最後の刻が来た。
姉さんは学校を休み、朝からずっと俺の手を握ったまま、何も言わない。
部屋にはやはり俺と姉さんの二人きりだった。
「実くん、苦しいの?」
ぜえぜえという俺のあえぎが、彼女の胸を刺すのだろうか。
ゆっくり目を開き、姉さんの顔を見やると、そこには沈痛の色を浮かべた彼女の顔が――無い。
笑っている。
慈母のように。
「大丈夫だよ。
あのね、息が苦しいのは最後の数分だけ。
お姉ちゃんの調合は完璧なんだから!
今までだって、苦痛らしい苦痛は何一つ無かったでしょ?
ただ体に力が入らなくなるだけで」
ああそうか、とようやく納得する。
「致死量の計算もばっちり!
mgのズレだって無いよ。
もうすぐその苦しさも無くなって、心拍も段々ゆっくりになって……そうして、眠るように死ねるの」
だから、原因不明の病だったのだ。
心音が次第に弱まっていく。
息苦しさも消えてきた。
「そしたら稔くんを一つ一つ、丁寧にホルマリンへ漬けるの。
永遠に綺麗なままでいられるよ?
それをお姉ちゃんだけが眺めるの、眺めてていいの。
毎日毎日、朝も昼も夜も……『お姉ちゃんだけのもの』になった稔くんを見つめて過ごすの」
意識もそろそろと遠のき始める。
誰も部屋へ訪ねに来てくれなかったのは、きっと。
「これでやっと本当の『二人きり』になれたね、稔くん」
表示オプション
横に並べて表示:
変化行の前後のみ表示: