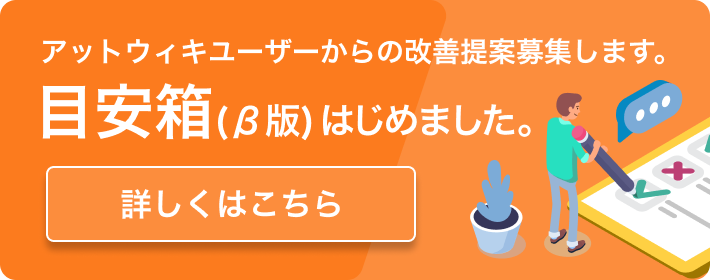「第九次ダンゲロス武勇伝-夢売 誘子編-」の編集履歴(バックアップ)一覧はこちら
「第九次ダンゲロス武勇伝-夢売 誘子編-」(2012/06/29 (金) 19:47:05) の最新版変更点
追加された行は緑色になります。
削除された行は赤色になります。
----
ドリームカンパニーは所属グループの戦費を賄うために、1億円を融資している。利率は0.001パーセント(単利)である。
所属グループ以外に対する融資を含めると、その総額は20億円にも上るが、返済された額は1億にも満たない。
来栖曰く、「これじゃ、いいように利用されているだけだ」であるが、あながち間違いでもない。
誘子自身は「ボランティアでやってることだから、儲けはいらない」と語り、受け取った利息は全てボランティア団体に寄付している。
「いいよ」
無表情で頷く少女。彼女こそが誘子その人である。
周囲には誘子のほかに眼鏡をかけた少年と、2人の少女がいる。うち一人は氷雨であり、もう一方は3年生と思われた。
「ありがとう! きっと返すからね!」
3年生と思しき少女が、その場で跳ねる。
「いつでもいいよ」
「もう、ほんと誘子ちゃん大好き!」
少女は誘子の頬にキスをした。
その側でトランクを担いだ少年――来栖は、その少女を蔑むような目で見つめる。
「ほら」
来栖はトランクを少女へと投げた。少女は慌てて手を伸ばす。
「あ、サンキューねー!」
少女はトランクを受け取ると、瞬く間に姿を消した。
「きっと返ってきませんよ」
ぼそりと来栖は告げた。
「そんなことないですよ! とってもいい先輩なんですから」
氷雨は頬を膨らませた。その様子を見て来栖は目を細める。
「何を根拠に……」
「どうしてそう言いきれるの?」
誘子は来栖の方を向き、そう尋ねた。
すると、来栖は待ってましたと言わんばかりに、中指で眼鏡を上げた。
「これで五度目ですからね。あのサークルにはすでに2350万円ほど貸し付けています」
その言葉を聞き、氷雨は呆然と口を開いた。
「なるほど」
それを聞き、誘子はぽんっと手のひらを打つ。
氷雨は申し訳なさそうに、しゅんっとした。
しかし、来栖は誘子の方を向いたまま、深くため息をつく。
「知ってて貸しましたよね?」
「まぁ、見過ごせなかったから」
「……」
その言葉に来栖は呆れと悲しみの入り混じった表情を浮かべる。
「もっと助けるべき人はたくさんいますよ」
「それでも、あの人が使ったお金は、また別の誰かへと渡るでしょ? それは回りまわって、私の手が届かない誰かを救うことになるかもしれない」
その言葉を聞き、氷雨の顔がぱっと明るくなる。
それを見て来栖は氷雨を睨んだ。眼鏡のレンズがギラリと光った。来栖の視線に気づいた氷雨はしょぼんとまた俯く。
「誘子はもっと、自分のためにお金を使うべきだ。人が良すぎる」
来栖は誘子にそう告げた。しかし、誘子は首を振る。
「私はみんなが言うような聖人君子じゃないよ、人が良いってのも買い被りだよ」
「僕はもっと贅沢をすべきだと言ってるんです。その理屈なら、もっと自分のためにお金をかけても良いじゃないですか」
「かけてるよ、もう。十分に私は贅沢だよ、こんな贅沢なことない」
「失礼ですが、客観的に見て、そうは見えませんよ。現実をみてください。そんな状態になってまで、身を削って誘子は働いたのに、手元には何が残りました?」
「うん。だから、また頑張って働かなきゃ」
誘子は無表情でそう告げる。その奥でどのような感情が渦巻いているのか、もはや窺いしれない。
「私もお手伝いします!」
いつの間にか氷雨も、けろっとしており、また張り切っている。
来栖は拳を固く握りしめる。はじめの頃は、来栖も誘子を止めるべく実力をもって阻止していたが、来栖がどれほどかんばっても誘子を止められなかった。
それに、誘子のこの行動は、この学園において誘子自身を結果的に守ることに繋がっている。
故に今は、来栖は静かにただ流れに従うことにした。だが、それは自らの無力さをより自覚することになる。
『キシシ』
来栖は聞いた。宙空から彼をあざ笑う、その声を。
仔貘の姿をしたその影は、誘子のすぐ傍らで浮遊している。
誘子はその仔貘の頭を撫でた。
◆
「私の両親は……、何の役にも立たない理想論を唱えて死んだの」
誘子は遠い目でそう告げた。
大銀河超一郎。彼の存在を知った時、誘子は確信した。
――彼しかいない。
誘子の目にも、彼はカリスマに映った。この狂った学園を元に戻すだけの魅力と強さを秘めた存在。誘子は彼に全てを託そうと思った。
――人殺しに加担するのか?
莫大な融資の申し出をしたとき、彼の取り巻きらが誘子に向ける視線は冷ややかだった。
蔑み、嘲笑。もの言わずとも、誘子には彼らが内心で自身を偽善者と罵っているのがよく分かった。
誘子自身に自覚は無かったが、周囲は誘子の在り方を「聖人」のようにあれと望んでいた。
争いを否定し、愛と平和を唱え、自ら率先して人を癒す、そんな聖者としてのイメージを彼女に押し付けていた。。
今回、誘子が大銀河超一郎との対話を望んだ時、誰もが誘子は彼を批判し平和的な解決を要求するものだと信じていた。しかし、実際に彼女が対話のさなか申し出たのは「批判」ではなく「協力」だった。
「――お前のような子娘が、進んで人殺しに協力したいとは、いったいどういう了見だ?」
若干の怒気と、わずかな戸惑い。
大銀河超一郎も、誘子がどのような人間か、聞きかじっていたのだろう。誘子の申し出に対して、わずかに驚きの表情を見せ、そしてそう尋ねたのだ。
どのような正義を掲げていても、力で捩じ伏せれば、行き着く先は畜生道。大銀河超一郎、彼が自らの所業を「人殺し」と皮肉ったのも、自らの掲げた正義に対する矛盾をどこかで感じていたからかもしれない。
そして、誘子もそれは十分に承知していた。そして、ここで返答を誤れば、自分が築き上げてきた全ての信頼を失うことも。
静寂が支配する中、誘子は静かに口を開き、大銀河の目を見据える。
「私の両親は……」
ゆっくりと、しかし強い意志を伴って、誘子は言葉を紡いだ。
「何の役にも立たない理想論を唱えて死んだの。それじゃ、誰も救われない」
高尚な理念や言葉など必要ない。ただ、事実だけを述べ、誘子はすっと頭を下げた。
「協力させてください」
それが、大銀河超一郎の問いに対する誘子の答えだった。
しかし、誘子が期待した大銀河超一郎は今いない。
誰かが大銀河の後を継がなければ全てが無駄になる。だから、誘子はそのために自分のできることをするだけだった。
----
GK評:2点
大銀河さん借金したまま失踪してたんだね……。
表示オプション
横に並べて表示:
変化行の前後のみ表示: